今日はブログお休みするつもりでした。
最近午前中は色々用事があり出かけていて、お昼を食べに家に戻り、食後は夕食まで図書館、夜はメールを書いたりブログを更新したりという生活だった。
今晩は久々にテレビで見たい映画をやるので、図書館にいる時間を延長、夕食を遅くすることにした。
さて、21時10分から、って宣伝しているくせに・・・15分くらいだったのかな始まったの
これイタリアで公開されたのは2008年だったのかな?(日本は2009年)
公開された時、見たいと思っていたのだが、こういうメッセージ性の強い外国映画は扱っている映画館が少なく、結局劇場では見られなかった。
余談ですが、Firenzeでは先日、また古い映画館が閉館になった。
シネコンに押され、古い映画館が存亡の危機に陥っているらしい。
更にここをこわしてアパートにする、という計画が持ち上がっているからさぁ大変。
こういう市民の思い入れの有る建物を簡単に壊せないのがイタリアのいいところ(?)
一応計画は暗礁に乗り上げているようですが・・・
で、何を見たのか、といいますと
Il bambino con il pigiama a righe(縞模様のパジャマの少年)
第2次大戦中、ブルーノは軍人である父親の仕事の都合でベルリンから遠く郊外へ引っ越してきたが、遊び相手もおらず、退屈な日々を過ごしていた。
ある日、探検に出かけ、巨大なフェンス越しに縞模様のパジャマの少年と出会う。二人に友情が芽生えるが…。
イタリアでは1月27日はGiornata della memoriaと呼ばれ、ナチスの被害を忘れないように、という記念日になっている。
こちらToscanaでは、毎年この日には当時と同じようにSanta Maria Novella駅からアウシュビッツに向かう電車が出る。
その電車に乗った学生たちが当時の歴史を振り返り、忘れないようにする為である。
ということで、この時期は戦争関係の特番や映画を放映することが多い。
この手の作品にハッピーエンドはないと分かっていながらも、いたたまれない終わり方だった。
この映画、状況説明が全くない。
でも私たちは知識として色々知っているから、主人公が言う"農場"が強制収容所であることも、白い煙や悪臭がなんであるかも気づいている。
でも、登場人物はそれを知らない。
事実を知った主人公の母は、旦那の行為を否定はするが・・・
フィクションだと分かっていながらも・・・虚しい。
ブルーノ(イタリア人向けだからイタリア名前にしたのかと思ったらオリジナルもブルーノなのね)無邪気で無知だからこそ・・・あ~虚しい。
そんな簡単に壁は超えられないだろう、と思いながらも・・・本当に虚しいです、はい。
でも原作読んでみたいかも・・・
そんなことを思いながら、ふと違うことを考えていた。
ドイツ人が作ったナチス関係の映画ってあるのかな?
ドイツのことは分からないけど、日本の戦争映画を考えてみると、日本の若者たちがいかに悲劇だったか、という話ばかり。
日本が中国や韓国で犯した罪を、日本を正当化しないで語っている映画って有るんですか?
本当に語らなければいけないのは、日本人が犯してきた罪の方ではないのだろうか?
日本を出て、日本を一歩離れたところから見る機会に恵まれた現在、歴史の教え方を考えるべきだと思う。
先の大戦が遠い過去となりつつある現在だからこそ、もっと自分たちの罪を学ぶべきなのではないだろうか?
今、平和で何の不自由のない日本だからこそ、もう一度過去を見つめなおす必要があるのではないだろうか?
って今日はちょっとまじめなお話になってしまいました・・・













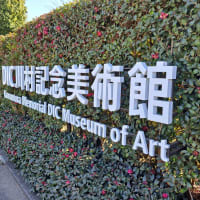






仲間に暗殺をされそうになった時に、必ず運よく助かっていたけど、その時に暗殺が成功していればたくさんの人の命が助かっていたのです。残念。
あ、それとご心配ありがとうございます。風邪は治りました。ブログももう少し頻繁に書かなくては、、、。
ヒットラーと言う独裁者を望んだのは、紛れもなく彼自身ではなく、ドイツ民衆ですよね。
私も全然歴史に詳しくはないけれど、じゃあ何故ドイツ国民は彼を、独裁者を喝采を持って迎えたかといえば、時代を遡れば、やはり第1次世界大戦でドイツはコテンパンにやられているわけですよね。
苛め抜いた他の西欧諸国にも、私は実は、原因はあると思っています。
大変なインフレと貧困に苦しんだドイツ国民を彼が経済的に救った事実は、あるわけですし。
(GDPの伸び率は半端ないですよ)
彼を狂気に走らせた国民、またその国民を狂気に走らせた列強諸国の思惑、、、すべての糸が複雑に絡み合って生まれたヒットラーと言う人物は、稀代の人物なんだと思います。
ドイツが勝利していたら、彼は英雄だったでしょうね。
勝てば官軍、負ければ賊軍です。
明治維新もこれ然り。
当時の日本だって、狂気だったし。
国際連盟を脱退した松岡洋右(ただ、彼の意思としては脱退は避けたかったそうです)が、拍手喝采で日本人に迎えられたという事実がそれを物語っていると思います。
個人の力では、もう止めようがない『狂気』。
戦争を回避するには、その『狂気』から全体が遠ざからないといけないのかなぁと、ふと思ってしまいます。
余談ですが。。。
色々美術館に通っていて思うのですが、
歴史を学ぶことは出来るのですが、
その当時の『風』というか、『温度』というか、そういうものって、実感できないんですよね。
だから、私はいろんな人にユダヤ人虐殺の話を聞いても、いつもどこかで理解できないで居ます。
きっとドイツにはあるだろうなと思っていました。次にドイツに行く時は、もう少しこちらに焦点を合わせてみたいと思っています。
ブログ、楽しみにしています!
紅子さん
貴重な意見、ありがとう!
こういうことって、普段はあまり話題に上らないので、非常に勉強になります。特に紅子さんのような若い人が、こうしてちゃんと歴史を見つめていて、自分の意見をはっきり言えるのはうれしいことです。
今のエジプトの様子を見ていてもそうですが、結局「英雄」を求めてしまう「時代」というか、「狂気」が悲劇を生んでしまうんですよね。映画の中で、主人公の祖父が「お父さんは歴史を作っているんだよ」と言っていたのが非常に印象的でした。それが「正」か「悪」か判断するのはその後に時代です。その時はそれぞれが自分の信じることが正しいことと思って突き進んでいるんですからねぇ・・・どちらが正しいかという「結果」ではなく、なぜこういうことになったのか、という「過程」を学ばないと何も理解は出来ませんよね。罪のないユダヤ人を虐殺したことは確かに認めることは出来ませんが、なぜこういう悲劇がおきたのか、を理解することが重要なんですよね。
私は、「美術館」に問題があると思っています。作品は美術館に収めるために作られたわけではないですからね。私も美術館で見る作品、特にMostraの時など「温度」を感じませんね。でも先日のPeruginoのフレスコなど、本来あった場所に今でもあるものを見ると、この作品が見てきた「時間」を感じることが出来ます。本来の場所にある作品は今でも生きていて、美術館に収められたものは死んでいる、とまでは言いませんが・・・なんてちょっと格好良すぎかな?
実際、私もアウシュビッツに行くまでは、「遠い世界のお話」でしたが、実際あの「空気」に触れてしまうと、もちろんすべてを理解することは出来ないけど、少しでも「理解したい」と思うようになりました。どれだけ本を読んでも、話を聞いても、実際理解できることなんてほんの少しだと思います。でも「知りたい」「知らなくては」という気持ちが重要なのではないでしょうか?間違いを繰り返さない為にも・・・
やっぱり重い映画だったのね。
前にドイツ人の監督の映画観ました。この映画の宣伝が確かドイツ人のタブーがドイツ人によってついに解禁的な感じだったような。タイトルのまんまオリヴァーヒルシュビーゲル監督の『ヒトラー最期の12日間』。ヒトラーが最後愛人と自殺するまでの話をそこで働いていたヒトラーの秘書(実在した人)の目からみた話になってましたが、史実では、彼女は後から大量虐殺の事実を知ったとか。
他にスイス人の監督だけど『わが教え子、ヒトラー』も観終わった後なんとも言えない気持ちになりましたが、こちらは半分コメディなんですが、コメディがある分フィクションでも辛~い気分になりました。
日本モノの映画ではこれもフィクションですが、日中合作の『鬼が来た!』が記憶に新しいです。
内容は、日本軍が統治していた中国のとある田舎の村に、一人の日本人兵士が麻袋に入れられて村の人に助けられて…という話。
映画ではどの立場の人もその時の正義を全うし、社会の中での責任も果たしています。もし自分だったら…と思うと、やはりどの立場(日本人大佐、一人の日本兵、中国人の村人)にいても彼らと同じことをすると思うのです。
誰も悪くない、戦争というモノが彼らをこう動かしてしまった…
ここでは戦争とは何か…を問われます。
遠い世界の話ではなく隣国との話。最後のカメラワークの斬新さもある映画でしたがこんなに後味が悪い映画は観たことがなかったです。
それは日本人だったか…いえ、一人の人間だからだと思うのです。
近年、ヒトラーはベジタリアンだったとかアーティストの才能など、一人の人間として描かれるものをよく目にします。
社会が、時代が、彼を狂気にさせてしまったのか。
歴史を知り、今を知り自分を考えることは必要だと思いますね。
映画ネタだったので食いついてしまいました。
長文で失礼しました。
また、ドイツとポーランドの国境でドイツ人がポーランド人の軍服を着てドイツ人を襲わせた、とか、ベルリンの国会議事堂はヒトラーが自分で攻撃をし、ソ連軍がやったように見せたとか、彼は汚いことばかりしているのです。
オーストリア出身のはずが、「ドイツ人以外は皆殺し」をしようとしたり、実はホモではなかったかと言われた彼がホモも取り締まったり。
ドイツ人はあるエイズ予防のPRビデオで、「ヒトラーの母親がコンドームを使っていたら、、、。」という皮肉な冗談を描いていました。今のドイツ人にとっても彼は目の上のたんこぶなのです。戦争当時に英雄に見えていたのは、彼の演技力と戦略のせいなのです。
よん太郎さん
機会があったら是非見てください。戦争を考えるというより、無知であることがどれだけ罪か、その代償の大きさを考えさせられる映画です。残念ながら、本当に最後は「衝撃の結末」ですが・・・
Shokoさん
そんなことまでヒトラーはしていたんですね。ヒトラーほどではないにせよ、ベルルスコーニを見ていると思います。演技力は政治家の最大の武器ですが、それに騙されてはいけないと思うんですがねぇ・・・なんでイタリア国民が騙されているのか、全く理解できません。
今読み直して思ったんだけど、恵比寿ガーデンシネマって今ないの?私も昔よく行ってたよ。あそことBunkamuraの映画館は、大衆映画(つまりハリウッド系)ではない、いいものを上演していたのに、残念です。悲しいことに、イタリアもそうですが、本当にシネコンに食われちゃってますね。
そして今月また渋谷から一つ映画館が消えます。。。
う~ん本当に残念です。
思います ヒトラー暗殺を敢行しようとしていた男が本当にいたんだなとトムクルーズ主演の
”ワルキューレ”という映画で知りました
コメントありがとうございます!