今回は「花蔵の乱」でしたね。
今川家の内訌ですが,ここで駿河守護とも言うべき今川家について述べてみたいと思います。
武田氏同様に清和源氏の名門です。
武田が八幡太郎義家三弟の義光を祖とするのに対し,今川は義家の次弟義国を祖とする足利源氏です。
足利将軍家に継嗣が無い場合は同族の吉良家から将軍が出で,吉良家にも継嗣が居ない場合は今川家から出ることになっていたと言われ,南北朝時代に九州探題として南朝方と戦った今川了俊が有名です。
出自は吉良家や一色家同様三河湾沿岸と思われ(細川氏は豊川沿い),これは鎌倉時代に足利家が同国の守護であったからでしょう。
その今川家の内訌が1536(天文5)年の「花蔵の乱」です。
8代目の若い当主今川氏輝(享年24)と次弟彦五郎が何と同日に死亡。
五男で僧籍にあった・栴岳承芳(せんがくしょうほう)が家督継承に動き出し,太原崇孚雪斎や庵原氏の協力で,四男で庶子の玄広恵探(げんこうえたん)と味方する福島(くしま)一族を討って駿河の実権を手中にした,というのがその内容です。
この栴岳承芳が後の三国の太守といわれた今川義元になります。
7代目氏親の室にして義元の母が寿桂尼で,京の名門土御門家の出身ですから,義元時代駿府に花開いた京風の文化の基礎はこの母が築いたと言っても良いのかも知れません(この辺は永井路子著「姫の戦国」参照)。
尤も,義元と雪斎は共に京五山の一つで曹洞宗の総本山である建仁寺で学んでいるので,その影響も大きかったことでしょう。
今川家の全盛期は,はっきり言ってこの雪斎の力に寄ることが大きく,雪斎没後5年後の桶狭間の戦いは彼が生きていたら有り得なかったかもしれません。
また,岡部則綱や朝比奈泰能といった戦闘力に優れた武将と関口親永(家康岳父)のような官僚をうまく使ったのも,雪斎の裁量だったのかもしれません。
また,山岡荘八著「徳川家康」では幼い日の家康が雪斎に師事したことが語られていました(尤も横山光輝のコミック版しか読んでいないのが悲しい・・・)
・・・ということで,太原雪斎役の伊武雅刀に感心しました。
「陰陽師2」にしても「のだめ」の峰の父ちゃん役(「裏軒」の親父)にしても,はたまた「宇宙戦艦ヤマト」のデスラー総統にしても,この人は何て器用で役作りが上手いのだろう,と毎度毎度感服させられます。
しばらく続く勘助の今川家編では毎度のように出てきてもらいたいものです。
福島越前,誰かと思いきやテリー伊藤でした。
勘助兄の光石研ともども上手かったですね。
それから,小山田信有役の田辺誠一も◎。
とにかく武田も今川もヴェテランが実に良い味出しまくりです。
来週は,武田・今川の同盟締結と共に北条軍が富士川以東に侵入する泥沼状態の「河東一乱」でしょうか。
勘助が庵原直胤の親戚とは無理が有りすぎ,と突っ込みつつも楽しんでいます・・・。










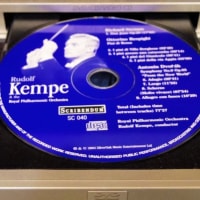
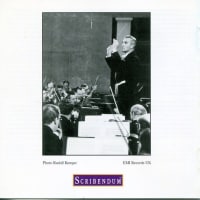
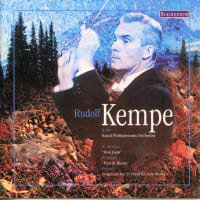







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます