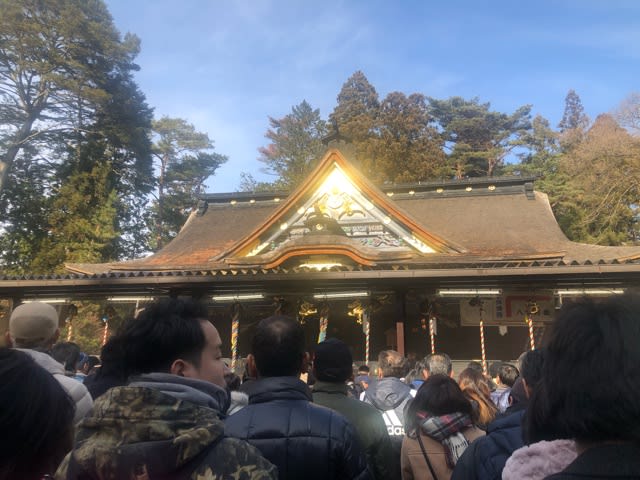水道法改正で何が起きようとしているのか 日本の水道水のありがたみを思い知らされる日
12月6日、改正水道法が成立した。
改正水道法は、自治体の水道事業へのコンセッション方式(国や自治体が公共施設などの所有権をもったまま、運営権を民間企業に売却する方式)の導入を促進し、水道事業の民営化を容易にするものだが、多くの問題をはらんでいると指摘されていた。
しかし、水道施設の老朽化や人口減少により経営困難となった水道事業の基盤を強化するためには、コンセッション方式の導入しかない、といった論調の報道もあった。
はたして、何が起きようとしているのか。
水道を民間に委ねる口実となった「ショックドクトリン」とは
そもそも、水道の老朽化問題が注目されるようになったのは、2018年6月18日の大阪北部地震だった。このとき、およそ21万人が一時断水や減圧給水などの影響を受けたのだ。
すぐさま同月27日には水道法改正が審議入りし、8時間の審議の後に7月5日には衆院本会議で可決されている。このスピード感は、まさに「ショックドクトリン」を利用したとしか思えない。ショックドクトリンとは、カナダのジャーナリストであるナオミ・クラインが2007年に著した書籍のタイトルだが、その意味するところは、市場原理主義者が社会の危機的状況に付け入り、自らの利益を誘導するために改革を進めてしまうことだ。
したがって、大阪北部地震は単なるきっかけにすぎない。実際、浄水設備の多くは高度成長期の1960年代から70年代に建設されたため、老朽施設の更新需要が毎年のように増えていた。このための費用と人材が足りない、というのが政府の見解だ。
というのも、水道運営は原則として水道料金の収入と地方自治体が発行する企業債(地方債の一種)で賄われてきたためだ。
ところが地方自治体によっては、人口の減少により水道料金の収入が減少している。しかし、水道運営のコストは大部分が固定費であるため、利用者が減少したからといって運営費が下がるわけではないのだ。
そのため、減少している利用者に負担がのしかかり、水道料金はこの4年間ほど値上げが続いている。さらに全国で3割の水道事業者が赤字になっているという。また、人材も不足している。
これらのことから、「もはや老朽化した水道事業を継続するためには、民間企業が参入できるようにしなければならない」というのが政府の主張だ。これはとても奇妙な論法である。なぜなら、民間企業こそ、儲かることにしか手を出さないはずではないか。