
頼りになる兄貴と姉御の対談を見つけた。どちらもどん!とされているね。石原慎太郎氏に感心するのは政治をやりながら、文学やったり、随筆書いたり、いまだに芥川賞選考委員を続けて選評まで書いていることだ。その為には主に若者の世界の候補作品を読み通さなければならないだろう。よく時間と根気があるなと思う。
この対談前には
 随分緊張があったみたいだ。いやはや、慎太郎氏氏の繊細な神経も下手をすると癇癪を起こすと思う。テレビ出演で他人が話している時の激しい“まばたき”にそれを感じる。小父さんは、お二人のファンなのだが。
随分緊張があったみたいだ。いやはや、慎太郎氏氏の繊細な神経も下手をすると癇癪を起こすと思う。テレビ出演で他人が話している時の激しい“まばたき”にそれを感じる。小父さんは、お二人のファンなのだが。
シンガー・ソングライターの松任谷由実さんの対談企画「yumiyoriな話」。今月のゲストは、東京都知事で作家の石原慎太郎さんです。音楽と文学。分野は違うものの、表現者同士。創作を巡る会話は大いに盛り上がり、「メロディーはどのように生まれるの」など、石原さんがユーミンさんを質問攻めにする場面もありました。(構成・祐成秀樹、田中誠)
作曲が先、頭に映像
石原慎太郎(以下I) この頃(ごろ)の若い人のラップとかポップスとかの曲は面白くないね。言葉をよく知らない奴(やつ)が書いた日記を読んでいるようで。
松任谷由実(以下M) そういう傾向はありますね。私が言うと小姑(こじゅうと)っぽくなるんですけど、活を入れなければ、と少しは思っています。ポップスでも、もっと文学性が必要なんじゃないかと。
I 昔の流行歌は歌詞も良かった。佐藤惣之助さんの「人生の並木路」は、一番の詞はたった3行なんだけど、それがすばらしい。
M 浜口庫之助さんの「夜霧よ今夜もありがとう」もすごいと思います。
I 「港町涙町別れ町」もいいんだけど、弟(石原裕次郎)の歌い方がだめなんだよね。本当は僕の方が歌はうまいんです。
M 裕次郎さんは、すごくスイートな歌声でしたよね。
I あなたは、作詞が先ですか? 作曲が先?
M 曲が先です。曲を書く段階で映像は見えているんですが、みんなが分かる言葉に翻訳しなければならないので、そこで苦しみます。正しくて美しい表現にしようと思うと……。
I 曲のヒントはどうやって得るんだろうね。
松任谷由実さん
M たくさんの音楽を聞きます。外国のものでも、クラシックでも民族音楽でも。文章でもそうですか? ほかの人の作品とか、若い頃から蓄積してきた表現とかが、ふっと出てくるようなことはありますか。
I あまり人のものに影響されないけれどね。どうやってメロディーが出てくるのかな……。言葉のように出てくるんだろうね。自分で書いて捨てる曲もあります?
M ありますね。頭の中で鳴っていた曲でも、消えちゃったものはそういう運命なのかなって。逆に、繰り返し頭の中に出てくる曲は、世の中に出たがっているんだなって思います。ただ、年を取ってくると、整理をしないと、自分で何をやっているのか分からなくなることがあって……。
I まだ50代でしょう?
M 若くないですよ。結局、ポップスは若い子のカルチャーですし、消えていく宿命です。「生き残っちゃってどうしよう」という世代になってます。
I そうすると、「サーフ天国、スキー天国」のような曲は、どういう風に出てくるんだろう。
M 湘南サウンド的な、リゾートソング的な引き出しというのは、元をたどると太陽族では。そういう人たちがいて、風俗があることを切り取ったのは、石原さんの「太陽の季節」じゃないでしょうか。
I 湘南はいいところでした。5年生の時に小樽から逗子に引っ越して、何て優しい自然なんだろうと。当時、一番風俗も進んでいて、洗練されていたね。
M もう一度、短編集を拝見して、いろいろ気付くことがありました。いい意味、青い部分があるんだな、と。手が届かないものに「トライ・アンド・エラー」のように、挑んでいる姿勢を感じました。
I そんな大げさなものじゃないですが。ただ、今でも好奇心があるから好きなことをやっている。僕と同世代の作家は、ほとんど死んでしまいましたが、生きてても、もう書けないんですよね。
M 1970年に三島由紀夫さんが自決した時に、弱さを残念がっていた記憶があります。
I 頭のいい人で大好きだったけど、どんどん衰弱しちゃったね。最後の「豊饒(ほうじょう)の海」は、無理して読んだけど、気の毒で泣いた。自分の若い頃の作品をまねするなんてだめだね。あなたも自分の作品をまねしたらしょうがない。
M 一度手を染めたかに見えても、自分で新しいと感じられたらOKだと思う。「新しい過去を手に入れる」と表現しているんです。
政治、小説に刺激
いしはら・しんたろう 1932年、神戸市生まれ。東京都知事、作家。55年の作家デビュー作「太陽の季節」で芥川賞受賞。68年に政界入りし、国会議員を25年務めた。「東京オリンピック・パラリンピック招致委員会」会長。
I 僕は今思えば、政治家になって良かったと思いますね。小説を書く上でいい刺激になっている。文学と政治は両方とも口舌の徒なので、対極のようで実は背中合わせ。音楽家とか絵描きは政治家にならない。官能的だから。音楽はスポーツに似ていると思いますね。
M そうですね、時間をデザインするという点で似ています。2016年のオリンピックですけど、もう東京に来るような気になっているんですよ。
I いやあ、これは大変ですね。胃が痛くてしょうがない。WBCのイチローの気持ちが分かってきた(笑)。まだ胃潰瘍(かいよう)にはならないけど。言い出した責任もあるしね。あなたは1964年の東京五輪にどんな記憶があります?
M 一番鮮烈なのは丹下健三さんの建築かな。代々木にエスカルゴみたいな競技場ができていくところを見て、未来な感じがしましたね。女子バレーボールの「東洋の魔女」には感動しました。
I 優勝した瞬間、彼女たちが胴上げしようと探したら、監督の“鬼の大松”(博文)さんは、離れた所で、にこにこ笑って拍手している。男は美しいなと思った。あとは男子マラソンの円谷(幸吉)さん。かろうじて3位に入ってね。で、その後、彼は自殺をする。
M (国立競技場に)2位で入ってきて、抜かれた。結果論かもしれませんけど、そこから死への助走が始まっている感じがします。
I 彼の遺書は本当に美しかった。長距離ランナーはいろいろなことを考えながら走り、ドラマがある。僕は今も、マラソンを見るのが大好きですよ。
M オリンピック、東京であったらいいですね。
I この頃、ジーンとくることってないじゃないですか。音楽はジーンとくるけど、世の中のことではね。
M 石原さんってすごい照れ屋さんですよね。お書きになるものにも、何かシャイなところが。
I 照れ屋かなあ。
M でも、照れがないとダサイです。人としても。
I 松任谷さんって面白いねえ。
M よく言われます。
〈太陽の季節〉 石原さんが一橋大学在学中の1955年に発表した短編小説。湘南を舞台に、戦後育ちの若者の奔放な生態を描き、若い世代の共感を呼び、旧世代のひんしゅくを買った。翌年映画化され、享楽的な若者を指す「太陽族」は流行語になった。
松任谷由実 (まつとうや・ゆみ)
シンガー・ソングライター。1972年デビュー。
「卒業写真」など、長年愛され続ける曲を世に送り出す。90年のアルバム「天国のドア」は、日本人初の200万枚超えの売り上げを記録した。
(2009年5月8日 YOMIURI ONLINE )






















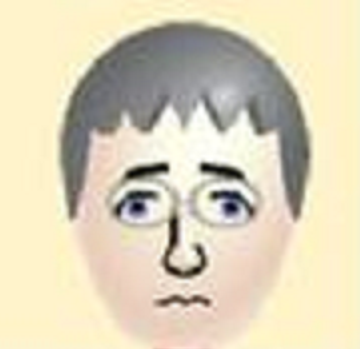





さすがpinkyさん良いことをいいますね~、こんなお二人に、我が日本国を託したいですね。
政治家・石原慎太郎氏の話は歯切れがいいですね。
いつも聞いていて気持ちがいいです。
ただ難点だと思うのはやたらカタカナ英語が
出てきてしばし意味が分からないことです。
>こっそりファミレスで聞き耳を立てていたりしているそうです
なるほどですね。
若者の世界はじっとしていても向こうからはやって来ませんね!
お二人の対談~!
楽しく読ませて頂きました。
小説家としての石原さんは、ほんの少ししか存じ上げませんが
政治家としての発言には、拍手を送りたい事も度々です。
ユーミン好きは、既にご存知でしょうが
憧れのお姉様であり続けて頂きたいものです。
常に新しい感性を求められる音楽業界にあって
その感性を磨く為のブレーンを持っていたり
こっそりファミレスで聞き耳を立てていたりしているそうです。
どちらも千両役者ですね。
>私が言うと小姑(こじゅうと)っぽくなるんですけど、活を入れなければ、と少しは思っています
はっはっは
面白いですね。
石原慎太郎氏78才!松任谷由実57才!!
二人ともよく若者の世界なりフィーリングをご存知ですね。
見習いたいものです。
>良い曲もあるとは思いますが、大抵何を歌ってるのか言葉が心に入って来ないんです
あまり聴いたことはないないですが、これこそ感性の世界な気がします。
お!ユーミン!奇遇ですね。嬉しいです。
肝の座ったお二人って感じですね。
ユーミンの朱の服は気合の現れでしたか(笑)
>ポップスでも、もっと文学性が必要なんじゃないかと。
その通り!
良い曲もあるとは思いますが、大抵何を歌ってるのか言葉が心に入って来ないんです。