さて、金峯山寺蔵王堂を後に仁王門を潜り抜け散策路に出た。
土産物屋、飲食店などが立ち並ぶ。
土産物屋、飲食店などが立ち並ぶ。
あっちをのぞき、こっちをのぞき。
祝祭日ではないので人影はまばら。
祝祭日ではないので人影はまばら。

蔵王権現仁王門すぐ前に食堂「はるかぜ」。
柿の葉寿司、葛うどんと看板に大書。
目に入るだけで腹がグーッと鳴る。
そこそこの客入り。
そこそこの客入り。
詰め込むと後は何も食べられない。
グルメ番組では、あれほど食べて凄い。
まあ、後はスタッフが食べるのだろうが。
丁度いいミニ定食があった。
まあ、後はスタッフが食べるのだろうが。
丁度いいミニ定食があった。
それも名物の柿の葉寿司(鯖)と葛きりセット。
吸い物、ゴボウ、ふきなどの和え物・・・800円也。

生ビールも、と思ったがここは節制の男。
あとのブラリを考えた(大人になったもんだ)。
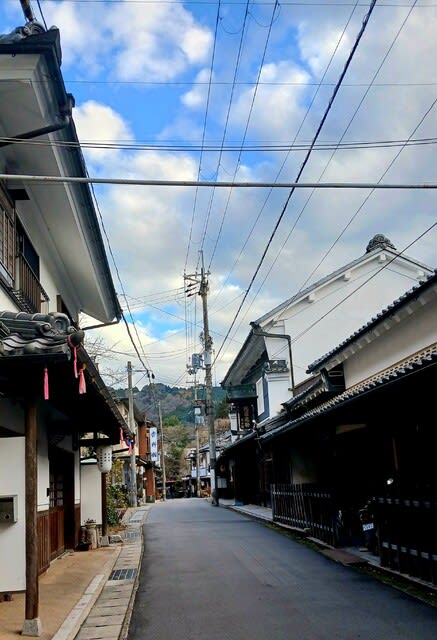
京都のように異人さんでごった返すこともない。
これがいい。
これがいい。
だが、マイナス点もある。
休業の店が多いことだ。
休業の店が多いことだ。
ロープウエー休止のことは書いた。

古い町並みは流石の世界文化遺産20年。
きっちり整備され、残っている。
きっちり整備され、残っている。
風情のある薬屋にふと目がいった。
ガマ蛙のデカい置物が惹きつける。
腹痛に効くという1300年の歴史ある「陀羅尼助」。
行者がキハダという高木の葉を煎じた。
密教の経文が陀羅尼経(だらにきょう)。
腹痛に効くという1300年の歴史ある「陀羅尼助」。
行者がキハダという高木の葉を煎じた。
密教の経文が陀羅尼経(だらにきょう)。
梵語(サンスクリット語)のダーラニーの音を当てた漢字。
それに「助けてくれ」の助をつけた、とある。
それに「助けてくれ」の助をつけた、とある。

土産物屋をのぞいた。
ここも蛙がズラ~リお出迎え。
婆さんがいつの間にかそばにいた。
婆さんがいつの間にかそばにいた。
「タモリも来たんだよ」
問わぬうちに話しかけてきた。
問わぬうちに話しかけてきた。
奥から、当時の写真・・・説明・・・。
話すのは嫌いではないが、この先制攻撃には脱帽。
聴けば去年の春ごろ「ブラタモリ」ロケ(放送は6月)。
話すのは嫌いではないが、この先制攻撃には脱帽。
聴けば去年の春ごろ「ブラタモリ」ロケ(放送は6月)。
お題も「なぜ桜といえば吉野なのか」。
なーーんだ、先に聞いとけば良かった。
なーーんだ、先に聞いとけば良かった。

話していると、おお!ヤマガラ君。
店先のヤカンの上にチョコン。
ここまで追ってきたか?と・・冗談です。
店の外から飛び交う。
「麻の実を皿に入れてあるんだわ」
「ヒマワリの種じゃないの?」
「そんなもん、ここらにあるかいな」
「そんなもん、ここらにあるかいな」

桜の季節じゃないけれど。
わざわざ秀吉が花見にやってきた吉水神社へいざ。
わざわざ秀吉が花見にやってきた吉水神社へいざ。
立派な書院造り。

南朝の後醍醐天皇、義経、秀吉がここを訪れた。
歴史上の人物がこの門をくぐったか?と思うと感慨深い。
入り口手前に「一目千本」の看板。

まさに一望。
花見時はさぞや壮観だろう。
だが、ここまで歩いた道のり。
花見時はさぞや壮観だろう。
だが、ここまで歩いた道のり。
それを考えると、春は凄い混雑ぶりが想像出来る。
落語ではないが「花見したつもり」でいい。
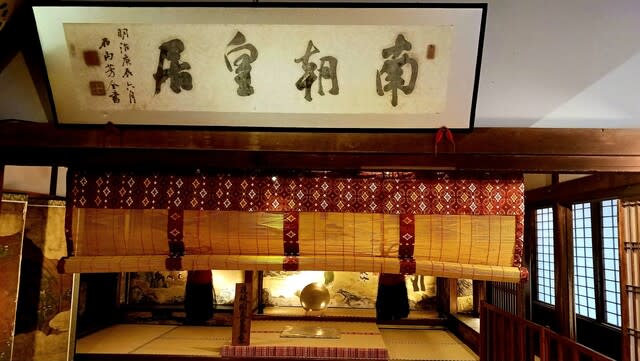
▲後醍醐天皇の玉座。都を追われ吉野入り。足利尊氏の室町幕府(北朝)に対抗して南朝政権を樹立した。

▲源義経の潜居の間。源頼朝に追われた義経が弁慶や静御前らと5日間、身を潜めた場所。

▲豊臣秀吉の花見本陣。愛用の金屏風と庭園。
秀吉自らガーデニングした名勝。
庭園の向こうに金峯山寺権現蔵王が臨める。

庭園の向こうに金峯山寺権現蔵王が臨める。

3偉人3英傑と1000年の時を経て同じ空間。
何とも贅沢この上ない。
何とも贅沢この上ない。
観覧料600円也。
往復900段の脳天破裂”大神”階段で脚はパンパン。
ちと一服。
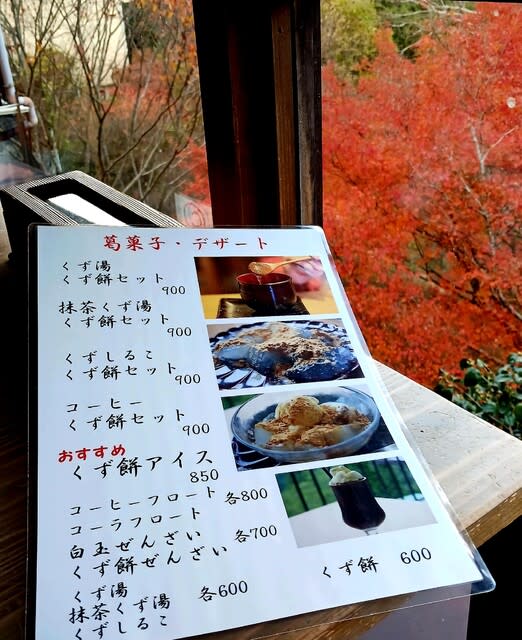
ちと一服。
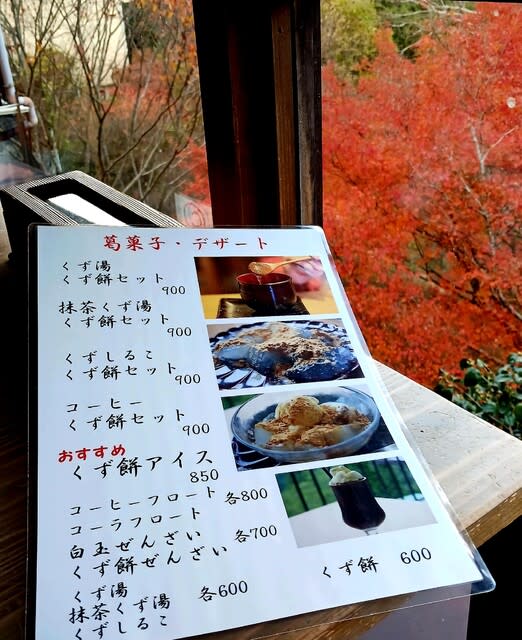
折角なので葛きり餅を頂こう。
洒落たカフェ風「静亭」があった。
眼下には真っ赤に染まった紅葉。
コーヒーも飲みたかったので「くず餅セット」にした。
洒落たカフェ風「静亭」があった。
眼下には真っ赤に染まった紅葉。
コーヒーも飲みたかったので「くず餅セット」にした。
きな粉と黒蜜にコーヒー。

食べ終わってから、コーヒーは合わないな。
抹茶にすればよかった、と後悔した。
抹茶にすればよかった、と後悔した。
見るものも見たし、食べるものも食べた。
時間があれば、まだまだあるのだろうが充分。
時間があれば、まだまだあるのだろうが充分。
陽が陰っりつつあるので来た道を戻った。

見上げるような大きな鳥居(高さ7・6m)を再びくぐった。
すべて銅製、再建後700年という重文。
すべて銅製、再建後700年という重文。
代行バスに乗らず急坂の道をゆっくり、のんびり降りた。

またも延々と続く山道。
脳天大神の地獄の階段を思えば、どうということはない。
脳天大神の地獄の階段を思えば、どうということはない。

人生も坂道、帰りも坂道。
ちょっぴり山伏気分を味わう。
静かな吉野路を堪能した。
静かな吉野路を堪能した。
≪終わり≫
【吉野紅葉狩り≪パート1≫】
【吉野紅葉狩り≪パート2≫】










