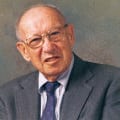上手な「子育て本」活用法
やってみて自分なりにアレンジを
「AERA with Kids」元編集長 江口祐子さん
二つの視点
子育てに関する本は大きく分けると2種類あります。一つは、どんな時代になっても変わらない普遍的な知識を紹介しているもの。もう一つは、時代の変化に伴って出てきた新しい教育観を取り上げているものです。
数多くの子育て本を読んでいると、本は違っても同じメッセージに出合うことがあります。「子育てに完璧を求めないで」「子ども自身に選ばせよう」「きょうだいを比較しない」といった趣旨は、何度も出合った子育ての「変わらない」教訓と言えます。
その一方で、これまでは常識だった教育観に変化を感じることもあります。例えば、これまでは「甘やかさないことが自立につながる」と考えられがちでしたが、精神科医の明橋大二氏は「甘えない人が自立するのでなく、甘えていいときに、じゅうぶん甘えた人が自立するのです」と著書で言い切っています。
また、子育てにおいて「褒めて伸ばす」は基本のように思われてきましたが、最近では、「褒める」こと自体を巡って議論が出てきています。「プロセスを見て、できるだけ具体的に褒める」など、褒め方には工夫が必要だと主張している本もあれば、中には褒めること自体を否定している本もあります。いろいろな本で「褒め方」を比べ読みしてみると、自分の褒め方を考える参考になるかもしれません。
このような「変わらないもの」と「変えていきたいもの」の二つの視点を持つと、自分がどんな本を探しているのかがより鮮明になります。
共感を大切に
生き方が多様化する時代にあって、親御さんたちの悩みも千差万別です。それに呼応して、子育て本の多様化もすごいスピードで進んでいます。
子育て全般の悩みを扱っているものから、国際感覚を育むことに特化したもの。自己肯定感を高めることに重きを置いたものや、日常的な声かけに絞ったものなど。親のいろいろな悩みに合わせて子育て本も多様化してきているとも言えます。もし、漠然と悩んでいるのであれば、どの本を読んだらいいのか迷ってしまうのかもしれません。
では、実際にどう選べばいいか。私は「共感できるかどうか」を大切にすることを勧めています。本のタイトルを見て気になったら、まず目次をじっくり読んでほしい。その中で、一つでも“私もそうなりたい”“これは大事だ”と共感できるものがあれば、参考にする価値があると思います。余裕があれば「はじめに」も読むと、著者が言いたいことや、本の趣旨がより明確につかめるでしょう。
親御さんの中には、本を選ぶ際、「口コミや評判が気になる」という方もいます。気持ちは分かりますが、口コミや評判はあくまでも他人の評価です。子育てはそれぞれの家庭で考え方が違うもの。参考にはしても、「共感できるかどうか」という主観を大切にして購入を判断したいものです。
三つのステップ
子育て本を上手に自身の子育てに取り入れるためには、次の三つのステップを意識するとよいでしょう。
①知識は積極的に収集を
②とにかく実践してみる
③自分なりのアレンジも
最初のステップは「知識は積極的に収集を」です。“子育て本なんて必要ない”と考えている人もいるかもしれませんが、子育ての知識は子育てだけにとどまらず、生活全般にも役立ちます。生きていく上でのスキルとして、知っておいて損はないことばかりです。気になる文章やキーワードが見つかったら、積極的に読んでみてください。
次のステップは「とにかく実践してみる」。講演会やセミナーに参加した人を見ていると、その時は一生懸命メモしていても、家に帰ってから見返したり、実践したりする人はごく少数です。
知識は実践しないとすぐに忘れてしまいますし、合うかどうかも判断できません。気になったことを一つでも、1週間だけでもいいので、ぜひ実際にやってみてほしいと思います。
そして、最後のステップは「自分なりのアレンジも」です。もしうまくいかなかったとしても、「うちの子には合わなかった」と諦める前にいろいろ試してほしいのです。
わが子の成長度合いや得意不得意に合わせて、「順番通りやる」を「興味があるものからやる」に変えてみたり、「毎日やる」を「3日に1回」にしてみたりするなど、アレンジを加えてみましょう。親子で対話をしながら、より子どもに合った形にしていけるといいですね。
数多くある子育て本の中から自分に合った1冊を見つけ出すのは至難の業です。“取り入れられそうなものがあったら、取り入れてみよう”くらいの軽い気持ちで、いろいろ試してほしいと思います。