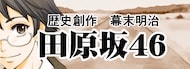創業セミナーで「自己アピール」…
いや、夏の書店委託の時もだ、メロンブックスやとらのあなに
「作品の良いところ」をアピールしなきゃいけない
つまり自分で自分を売り込むには、セルフプロデュースしなくちゃ
できなくちゃいけないんだけど…
苦手なんですよね…昔から。
「美神のカルテ」の作者紹介、自分で書けなくて担当のSさんに頼んだら
「人気がある」とか書かれてしまい
「ぎゃああああああやめろおおおおおお!!(爆死)」
逆に「ふ〜んだクソ虫がw」って思われちゃわない?て思ったり
そ、そういえばこんなことは1度2度じゃないぞ
「拙者」という言葉を抱えてるでござる。
あと、とにかく自分の過去作、前の作品を見るのが苦手で
「うわ〜〜〜やめれ〜下手くそで死にたい」
てなったり…
なぜなんだ><;
そういや美術関係で知り合った人に
内心「わーこの程度でよく出せるな〜どんだけ自信あんだよ」
と思ったことある(ゴメン;)
そうやって何かと比較するの、よくないなあとも思いながら。
逆に
「こんなにすごいんですよ」というドヤ顏の輩には
痛恨の一撃を食らわせたい…
と、どっかで思ったりしたかもしれない。
なんなんだ…
でも最近分かりましたよ(おせえよ…)
アメリカ現代美術はあれはスキル云々でなく
「いかに自分とその創造神の自分が作ったものはすごいか」に付加価値をつけ
つまりカサ増しした人が勝利するゲームだと。
(まあそういうアメリカ式はおかしいのではという声もあるけども)
セルフプロデュース、自己アピールを上手くやってこそ、の21世紀。
きっともう「謙虚」「謙遜」の美徳では通用しない。
いや特に美徳と意識してるわけでもなかったが…。
ふと「拙者」という言葉から読み解く。
「拙」とは
《名・造》
つたない。まずい。へた。
《代・造》
自分のことを謙遜(けんそん)して言う語。
でして、反対の「巧」で自分を「巧者」とは言わないよね。
謙遜、どっから来たんだというと「論語」か…
じゃあ21世紀の自由経済に相性のいい自己啓発みたいなのは
どこじゃ…聖書すか
「論語」と「聖書」は相容れない。
(東洋と西洋は美術史学会でも棲みわけてるのよ。
第一文科と第二文科に分かれてるので隣に行く時はダッシュなのよ)
おかしい、どっちも人の教訓となる良い要素あるのに!?
多分、聖書自体は似たような教えがあっても
勝手な解釈をし続けた人らがいるということなのでしょう…かね。
武士と純和風の精神を支えてきた儒教、論語の精神を紐解くと
今聞いたことをすぐひけらかしてはいけないだの
うぬぼれてはいけないだの
意見をごり押しするなだの
我が身優先の身勝手さはやめろ、だのありまして
昔、士族は小さい時からこう言う論語を教わって育ってた。
そしてこれらは、純和風的なものとして戦後も残った。
でも、世界がグローバル化するにおいて
「聖書」「啓蒙」的なものが勝っていってしまった。
実はこの問題、もう明治初年に気づいていた人らがおりました。
福沢諭吉です。
いち早くオランダ語から英語取得に転じた勢は、
武士が学んできた「論語」の世界は、英米の考えとどうもギクシャクすることを知ってた。
でも強気で海外を受け入れ
「論語にはそうあっても、必ず従うべきものではないはず」
って語っていたりします。
日本的なものを順守というのは美しいんだけど
一部「出る杭を打つ」になる側面もなきにしもあらず。
でもそろそろほんの少し
自分を認めてあげよう、
そのままの自分を出して認めてみようかなと思いました。
強すぎる自戒が、「自壊」になってしまわないようにです。
もしもまだ何かできる事があるなら。
で、この夏からは「サイッテーです><お目汚しです」
と思うのやめにしました。
一生懸命やってきたことも、やっていることも嘘ではありません。
堂々と自分で「面白いと思います」
または「これでいいや」とか
ちょっと恥ずかしいけれど
「こんなことをやっています」で
わかっていただければ…
あんまり営業て上手くないのですが
普通にそれだけでいいかなと思います。
それにしても日本人やっていくのって大変だよねえ…。