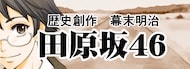熊本〜鹿児島の豪雨ニュース見てます。
自然災害に新型コロナに。
被災された方、なんと言ったらいいかわからない。
これ以上ひどくならない事を祈ります。
ーーーーーーー
西南戦争で薩摩軍の援軍をしたのは
…って、当初は私も、西南戦争は官軍と薩摩、西郷軍の戦いであって
そんなに九州各地からいろんな部隊が参加していたとは知りませんでした。
しかも、最初のイメージとしては薩摩は「賊軍」でちょっと暴力的、粗野で…というのはありました。
でも、調べていくうちに
「賊軍」とされた側には、政府を批判していたジャーナリストがやたら多いことに気がつきました。
そしてもう1つ
西郷とその側近らのように
「武士として志に対し、命掛けで戦って、志のため、国のために死んだ人」
はやたら絶賛されて、敵ながら天晴とされて残っているのに
「平和的解決」を望んだ者、死ぬことより生きることを選んだ者らはあまり記録が無いのに
気付きました。
戦前などは特に、国のため戦のために命をかけるのは素晴らしいが
逃げ出すのはみっともない、ダメとされたのでしょう。
中央主権も近代合理システムも「完璧」では無いし。
21世紀にEUやアメリカが傾きかけてる今だからこそ
幕末〜明治に「武力で抑圧した」側を再考するのは重要だと思います。
ーー龍口隊とはーー
熊本から西郷軍の味方に加わった部隊は
ここでも、ウチの本にもすでに登場していますが
「熊本隊」と「熊本協同隊」があります。
熊本隊が1500人、協同隊は最多 500位ですかね。
それとは別に、
九品寺から旗揚げしたという200人位(人数は資料によってまちまちです)の、
龍口隊
というのがあります。
これがあんまり、入手しやすい本にはあんまり出てこないです;
熊本隊が国学、協同隊がルソーという思想的バックボーンで動いていたのに比べると
龍口隊、今の所あんまりそういう強い思想は見えて来ません。
調査中です。
が、西郷に加勢するんだからそれなりに維新政府に不服はあったとは思います。
熊本城が炎上したのにショックを受けた、とはありました。
(そうするとまたまた濃くなるのが官軍による放火説だったりするのですが)
決起の時
「諸人の 嘆きの声を聞きかねて」と歌を詠んでいるので
やっぱり、武士として人々を救いたい、守りたい、そういう部分あったかと。
維新政府、人々にとってどうであったかは
「生きづらい明治社会 不安と競争の時代」松沢裕作著 (岩波ジュニア新書)
あたりを読まれたし。
まあいつの時代もそんなユートピアなんて無いんだろうけどね。
ーー中津大四郎ーー
龍口隊のリーダーは中津大四郎。
熊本城下生まれの士族で、馬医で画家の福田太華の弟らしい。
(ヤフオクで出されてた…;)
ちょっと画像借りて来た。

鑑定団in熊本で出そうですね…オークションてことはだいぶ個人所有なのか。
その龍口隊が主にやっていたのは
主に「後方支援」で
食料調達、ご飯の炊き出しなど。
大事ですよ。腹が減ってはなんとやら〜。
中津らは、官軍の食料庫に凸して米などをかっぱらって来たのだそうです。
そんな中津大四郎、いよいよ負けが濃厚になると
みんなを集めて「生きる意義」を聞いたのだそう。
何のために死ぬべきかではなく何のために生きるのか、なのですね。
そして、自分一人が残って責任をとると言い
隊を解散させて、逃げるよう勧めた。
「生きろ」
そして投降して捕まり、裁判になるようなことがあったら、堂々と挙兵の理由を言えと。
こういう所は、後の自由民権運動のジャーナリストに通じるなと思います。
この時代に部下を死なせて隊長までニコニコ帰って来てたらどうなるか…
というわけで、宮崎県山中で自刃しましたが
辞世の句が
「義を立てし 身はこの山に捨てて名を 末の世にまで遺す嬉しさ」
てあるんですけど
このままでは遺せるのか不安なのでキャラ起こしました。
誰か見てやって下さい。
義も勇もある撤退もアリだと言ってくれると
新型コロナで申し込んだイベント、行かぬは恥では無いわ。
もし状況があまりにも懸念されるならその時は
堂々と不参加もありで。
大事なことは何かをよく考えようと思います。