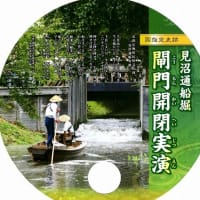いわゆる地図帳である。学校時代、いや卒業後も何かと
お世話になっている帝国書院の地図帳。もう三十年ほど前に
子供が使っていたものがボロボロになったので買い替えた。
道を調べるだけでなく、地名、国名や都市、そして面積、
人口、特産物などなど、立派に「地理百科事典」といえる。
出不精な我が奥方の愛読書でもある。
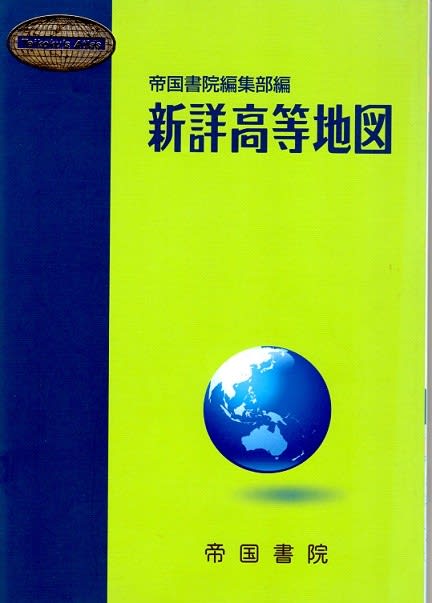
大正6年に四十歳で帝国書院を創業しこの地図帳を執筆、
発行したのは守屋荒美雄(スサビオ、幼名・荒雄)である。
カトリックの洗礼を受け、最高の賢者を意味するスサビオ
と改名した。
苦学して高等小学校を卒業し、高等小学校の正教員試験、
最後は難関の「文検」に合格した。文検とは、文部省師範
学校中学校高等女子学校教員検定試験。
今で言えば中学卒業で高校の教員試験に受かったという
ことになる。そういう時代であった。
教員時代に執筆した地理の教科書には、それまでのお偉い
先生方の文章主体のものと違い、多くの挿絵や図が使われ、
ビジュアル重視の新しい教科書としてヒットした。
創業三年目に発行された「帝国地図」は全ページカラー
印刷だった。欧米の分厚いアトラスと違い、「一人一冊」の
日本の子供たちの地図帳、世界に誇るべきものである。
しかし、この大ヒット地図帳を作った守屋荒美雄だが、
何故か、故郷の岡山県倉敷市(現)でも知名度は低い。
母校の西阿知小学校に胸像が立つのに最近赴任した副校長
も「知らなかった」という。郷里の橋や母校の講堂など多くの
寄付をしたにも拘わらずである。
とにかく「捨てられない教科書No.1」という帝国書院の
地図帳、これからもお世話になることだろう。
(参考:12/18朝日新聞土曜版「はじまりを歩く」)
正月も3日目、青山学院がトップを守って始まった箱根駅伝
の復路を観ながらチビチビとやるのは、富山の満寿泉(マスイズミ)
の干支ボトル。今は亡き会社の先輩の実家の酒である。