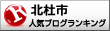この写真は金生遺跡の配石遺構を雪の後撮影した写真です。
配石が地面の土色の背景よりも、雪の白さにより際立っています。
横にある建物はどうでしょうか。
この建物には日本全国各地から調査に来ている人が少なからず居られるようです。
壁の白さは雪により映えている様子ですが、材質や色では無く、形式が壁を持つ建物と言うことが中心の対象となっています。
このような建物が縄文時代にあったのか、嘘だろうと疑うことです。
いずれにしても各種資料を検討されて否定すること無く帰られています。
引用----
先ほどもご質問が出ましたが、住居の形が普通の縄文の復元村で見るような屋根を葺きおろした家とは違うのです。つまり竪穴住居ではない。竪穴住居ではないということでしたら壁が無ければまずいのではないかということで、壁立ちになっているのです。
例えば岩手県の「八天遺跡」、これは中期の遺跡なのですが、また東京町田の「なすな原遺跡」でも一部そうだったのですが、竪穴住居ですが、火災に遭った住居の壁の内側に土手状に焼けた土が残っていた例があったのです。あれいったい何かなと考えたのですがどうも壁の痕跡ということでも良いのではないか、と思ったのです。竪穴住居でもある程度壁立ちもある。そうすると金生遺跡のような深く掘られていない「周石住居」などは壁立ちでもよいのかな、ということなのです。でも壁が土壁なのか植物などの材料なのかといった判断はつきません。この辺は推測の域は出ないのです。入口が隅っこにあるということについてもいくつかのご批判はあります。
『八ヶ岳南麓・金生遺跡(縄文後・晩期)の意義・4』 新津健
--------
最近、北海道八雲町の栄浜1遺跡から縄文中期の軽石製の「住居模型」が出土した(1998年7月25日付、読売新聞ほか)。それは縦14.9センチの小さな製品で四角い家で形どっている。壁立ちの四隅に柱を立て、丸みのある屋根には棟がしつらえてある。
その姿は四千有余年も前の建物というよりは、ついこの前まで近所で見かけた佇(たたず)まいそのものである。
縄文時代は決して「原始」ではなかった。縄文遺跡の内容が鮮明になればなるほど当時の技術や文化の素晴らしさが浮かびあがってくる。縄文時代以来の伝統の上に私たちの暮らしや住まいが成りたっていることを再確認させられるこの頃である。
(ふじた ふじお・富山市教育委員会事務局主幹) -平成11年1月16日放送-
ーーーーーーーー
宝?古城遺跡の2020年度発掘調査で撮影した稲田跡と思われるエリア(資料写真)。(c)Xinhua News
宝?古城遺跡の低地を利用して作られた灰坑と墓葬(資料写真)。(c)Xinhua News
Next
【6月9日 Xinhua News】中国四川省(Sichuan)の成都文物考古研究院は7日、成都市(Chengdu)新津(しんしん)区にある宝?(ほうとん)古城遺跡で、4500年前の竹製家屋部材を初めて発見したと発表した。
成都平原でこれまでに見つかった最古の「竹の家」であり、このような竹の骨組みと土壁を持つ建物は、三星堆(Sanxingdui)文化の時代まで受け継がれたとされる。
ーーーーーーーー
従来から、縄文後期から晩期に人口が激減したとされる山梨県を含む高地中部地方では、縄文中期に文化的隆盛期を迎え、以降次第に衰退し、その後独自の文化は無かったとされていた。この考古学の定説が、金生遺跡の発掘によって覆されたのである。昭和55年(1980)、圃場整備に伴って調査された発掘で、東西80m、南北15mにおよぶ配石遺構が多数の住居跡と共に発見された。
ここでは、住居跡38軒、配石遺構5基、集石遺構3基、石組み遺構16基など豊富な遺物が発見されている。焼けた猪の顎の骨が138 頭分同一箇所から出土したので、通常の集落ではなくて祭祀場所だったのだろうという説が有力だ。水田の下にあった遺跡は保存状態が良好で、夥しい石組の間からは土器・石器・石棒・石剣・独鈷石・土偶・耳飾り・ヒスイ製垂飾などの祭祀用具・装身具が検出された。
遺跡の奧に見えている現代アフリカの住居のような、或いはモンゴルのゲルのような住居が、問題の「壁建住居」である。八ケ岳南麓の斜面には縄文時代の遺跡・遺構が多く、祭祀遺構と考えられる石組み遺構も沢山発見されているが、このような「壁」を持った住居はここだけである。北海道八雲町の「栄浜1遺跡」からは屋根を持ち、壁を持った家型の石製品が見つかっているが、これは住居跡が見つかったわけでは無いので、物証としては弱い。
ここの建物は、全国唯一の縄文時代「壁立ち構造」での住居復元である。発掘の際に、通常竪穴式住居にある「掘り込み」や「周堤」が見られなかったこと、又、主柱穴のほかに壁柱穴と思われる穴が見つかったことから「壁立ち構造」と判断したと旧大泉村教育委員会の資料にはあるが、どうもしっくりこない。
中を覗いてみると、屋根を支える主柱とは別に、いくつもの壁柱を組んでその間に茅をびっしり編み込んである。外側を粘土質の土で固めて壁を作っている。解説書によると、石灰を混ぜた漆喰だそうだ。土壁だと冬季にひび割れてボロボロになったので、耐久性を持たせるため石灰を混ぜて上塗りをしたとある。それで白い壁になっているのだ。
日本の古代において、住居の形態はどのような変遷をたどってきたのであろうか。一般に旧石器時代の人々は、洞窟や岩陰に住んでいたと思われているが、それは特殊な場合であり、開けた台地上に住むことのほうがむしろ多かったのである。岩陰遺跡の例としては愛媛県
美川村の 上黒岩遺跡 を、「遺跡めぐり」のHPでとりあげている。
岩陰や洞窟遺跡に対して、開けた場所での遺跡を「開地遺跡」と読んでいるが、日本の古代においては、住居はこの「開地遺跡」にあることが一般的だった。では、台地上にどのようにして住居を確保していたのだろう。それは周知の如く「竪穴式住居」である。つまり地面を掘り下げ、その上を木と植物の葉や枝で覆い、雨露をしのぐというものである。地面を円形や方形に掘り窪め、その中に複数の柱を建て、梁や垂木をつなぎあわせて家の骨組みを作り、その上から土、葦などの植物で屋根を葺く。「竪穴住居」(たてあなじゅうきょ)、「縦穴住居(たてあなじゅうきょ)と表記することもある。
「縦穴・竪穴」という用語は、横穴という表現の対照として生まれ、ほぼ世界の考古学界で通用する。英語表記の一つ「pit-house」は、厳密には、竪穴式住居のうちで、屋根以外は、竪穴自体で構成されている、つまり竪穴に屋根を被せた形の家屋ないしは住居のことをいうが、竪穴自体が浅く、地上部分のある竪穴式住居についてもこのように呼ぶ研究者がいるので、日本語の「竪穴式住居」とほぼ同じと見てよい。
ヨーロッパでは、旧石器時代からこの住居の形態が出現している。やがて、世界各地で、新石器時代に盛行するようになる。中国では、仰韶文化(やんしゃおぶんか)の代表的遺跡である西安の 半坡遺跡(はんばいせき) で発掘されたものがよく知られている。これは、南側に階段のある出入り口を持つ約5m×4m、深さ80cmの隅丸方形のもので内部に炉が見られるものである。
また、アメリカ南西部のモゴヨン(Mogollon)文化やホホカム(Hohokam)文化の人々は、9世紀頃まで、入り口部分を張り出し状にした竪穴住居に住んでいたことが知られている。金生遺跡に復元してある3軒の住居の内、一軒がこれである(下)。
日本では竪穴式住居は、後期旧石器時代ごろから造られたと考えられており、北海道から九州にかけて10数カ所の遺跡で確認されている。北海道標津(しべつ)町に一辺長さが4m~10mもある汁鉢状の大きな窪みが数え切れないくらい密集している。この窪みが大昔の「穴居」(けっきょ)の跡である。深さが2.5mもあり、掘った土に周りに盛り上げてある。また縄文時代の、北海道南茅部町の「大船C遺跡」では、穴の深さが4~7mに及ぶものがあり、これは西日本各地で見られる竪穴式住居とは大きく異なっている。普通の竪穴住居の深さはせいぜい70~80cmなので如何に深いかが理解できるが、範疇としては「竪穴式住居」に含まれる。
日本の竪穴住居は伏屋式と壁立式とに区分され、後期旧石器時代頃から造られ始めたと考えられており、縄文時代には盛んに造られ、弥生時代に伝わり、伏屋式が主流で「壁立式」は拠点集落の大形住居に限られ、首長居館として権威を示す形式として弥生・古墳の両時代に築造されたと考えられている。そして日本の農家や民家のもととなっていった。
「後期旧石器時代頃から造られ始めた」という論拠の一つがこの「金生遺跡」の存在なのである。
竪穴住居自体は平安時代ごろまで造られ、さらに時代が下がった例で東北地方では室町時代まで造られていた。特に近畿地方では平安時代にはほとんどが平地住居へ移行したとされる。
前述したように、日本においては地面を掘り窪めた穴の平面形状は、時代と地域によって大きく異なっている。縄文時代前期では、概ね方形、台形、楕円形で、6本の主柱をもち、壁面周辺に支柱穴とも推察されるピットが並んでいる状況が見られる。また、前期には東北・北陸地方を中心に超大型住居が現れる。
炉は、地床炉(ぢしょうろ)が多いが石組炉もあり、保有率は時代が下るに従って増加する傾向にある。中期では円形および楕円形が多く、4本から5本の柱をもつものが主流であり、地床炉や石囲炉、また炉体土器を伴う炉が見られ、中期後葉の東北地方南部では複式炉をともなう住居が現れ、中部地方とくに長野県などではこの金生遺跡のように、石敷の住居も現れる。後期になると、地域によっては「柄鏡型」とよばれる、入り口部分を外側に張り出した住居が出現し、この金生遺跡でも見受けられる。円形のものも続き、方形に近い住居跡も復活する。晩期になると、柄鏡部分がつぶれて短くなる構造に変化する。
確かにこれらの配石は、単なる伏屋式の竪穴住居には不要である。壁を支えていたとしか思いつかない。
炉は古墳時代前期まで続くが、古墳時代中期になると北側や東側の壁にカマドを設ける住居が出現する。カマドは時代が下るごとに発達し、「壁」の外へ向かって張り出していくようになるが、実際には竪穴住居の堀りくぼめた部分が狭まって、そのぶんカマドが発達していると考えられる。このような住居は関東・中部地方以北では平安時代まで続くが、東海地方では一部残しつつも、近畿においては飛鳥時代から掘立柱建物に移行していき、鎌倉時代以降は、関東で竪穴状遺構として一部名残をのこすものの、ほぼ全面的に消失する。
地面を掘り下げた底の深さも、地域や時期で異なる。前述、知床半島に近い標津町の伊茶仁(いちゃに)カリカリウスの住居は、竪穴の
周りに掘りあげた土から底まで、2mから2.5mもの深さがあり、天井から出入りしたものと推測される。床の中央か一方に片寄って
炉がある場合が普通であり、古墳時代以降は壁際にカマドを設ける事例が一般化する。
排水のため床の周りに溝を巡らしていることも多い。竪穴(縦穴)建物の屋根の軒先は地面付近まで下がることが多かったと推測され、
外からは屋根しか見えなかったものと考えられる。屋根はアシやカヤなどの茎、土葺、草葺の屋根も多かった。
遺跡発掘当時の様子
ここからの出土品は祭祀に関するものが多い。石棒、石剣、耳飾り、垂飾り、石冠、独鈷石、酒器或いは神々に供えるためのものと思われる土器類等。
そして他に類を見ないおびただしい数の石で作られた祭壇状の配石遺構と敷石遺構。配石遺構は本来石を用いた墓であり、その後祭祀施設として用いられ、縄文後・晩期の祭りを象徴する遺構として、八ヶ岳南麓に最後まで残った縄文集落跡となる。
金生遺跡は縄文時代後・晩期を中心とした遺跡で、38軒の住居跡の他大規模な配石遺構が発見されたが、これら配石遺構は縄文後期から晩期にかけて延々と石が運ばれ続けて築かれたと見られる。
敷石遺構の中には小さなスト-ンサ-クルも見られる。配石に使われた石の中には、八ケ岳では産出しない花崗岩の巨石(これは1トンの重さがあり、10キロ離れた釜無川から運ばれた事は確認されているという。)もあり、又、垂飾り(ペンダント)には、新潟の糸魚川地方にしか産出しないヒスイ製のものも出土したという。広く東北から関東に掛けて見られる「縄文時代の交流」が、ここにも及んでいたことになる。
配石(はいせき)遺構とは、表面のなめらかな河原石などの自然石を目的をもって配置したり、組合せたりした遺構である。ピラミッドのような石組みの建造物は通常は含まれない。配石の全体の形はさまざまあり、その性格も集落内の土地区画など日常生活に関わる標識から、埋葬や祭祀など信仰に関わるものまで多岐にわたると考えられる。
単独のものは組石(くみいし)とも呼ぶ。配石のうち、石を円形に(ドーナツ状)に配置させるものは環状配石や環状列石と呼ぶ。
立石をともなう場合もある。礫を土坑の中や外に配置した埋葬施設を特に配石墓と呼び、配石によって作られた住居を敷石住居と呼ぶ。
ヨーロッパには巨石を並べた配石遺跡があり、ストーンヘンジはその代表例である。類似のものは、原始・古代に渡ってほぼ全世界的に分布しており、西欧、北欧、北方アジア、シベリア、アフリカ、インド、東南アジア、中国、日本に至る。アラスカのエスキモー遺跡にも配石遺構は存在しており、その原初の形はいずれも墳墓と考えられているようだ。モンゴルから北朝鮮、南朝鮮を経て日本に至る東北地方の配石遺構は、その形態に類似のものが多数見受けられ、古代人の葬送思考の類似性、或いは民族の大移動といった研究テーマを提供している。
日本では縄文時代前期に顕著となり、中期には急増する。環状列石をともなう著名な遺跡には、秋田県鹿角市の大湯環状列石や青森県青森市の小牧野遺跡、秋田県北秋田市の伊勢堂岱遺跡があり、これらはいずれも縄文時代後期の遺跡である。また、石材資源の豊富な中部地方の山麓地域においても盛んに作られる
規模は小さいが立派なスト-ンサ-クルである。
ストーンサークルは、石を環状に配置した古代の遺跡である。環状列石(かんじょうれっせき)、環状石籬(かんじょうせきり)ともいう。イギリスには巨石を使ったストーンサークルが多数あり、ストーンヘンジもストーンサークルである。世界遺産に登録されたアフリカのセネガンビアの環状列石では一部で発掘調査が行われており、その結果、8世紀から12世紀にかけての配石墓であることが判明している。
日本における環状列石は、現在までに主に東北の青森県と秋田県北部、北海道渡島半島を中心に道北を除いて道の各地に検出されている。血縁・地縁をもった氏族の連合が40~50キロほどの距離をおいた領域を占有し、その中心に祭の場を築造したのではないか、と考えられている。
この遺跡が日本ではじめて公表されたのは1886(明治19)年小樽市の忍路環状列石である。
東北地方から北海道にかけてのストーンサークルは縄文時代中期後半から後期にかけて作られている。大きさは直径30m以上のものと直径10m以下のものがあり、大きいものは祭祀の場として作られ、小さいものは竪穴住居の周囲に石を置いたものが多い。直径が30m以上のものは、まず縄文時代中期の終わりごろに静岡県、山梨県、群馬県付近で作られる。続いて縄文時代の後期前半に秋田県北部や青森県、北海道西南部で作られる。同じころ、岩手では石を直線状や弧状に並べるものが作られている。
配石遺構は、日本においては縄文中期後半から後期に掛けて盛行するが、晩期末から弥生時代に掛けて作られなくなり、弥生時代になると殆ど姿を消す。これは他の国々においても同様の傾向を示し、当初墓だったものが、次第に祭祀的な性格を帯び、やがて集落のモニュメント的な遺構へと変貌する様も世界的に共通している。
上は「石棺」と資料館の模型に記されていた。
「壁建住居」の正当性に疑義を挟み、わざわざ現地まで見に来た遺跡ツアーだったが、どうやら「壁建て住居」というのはかなり確率が高そうである。住居内で壁の根元にめぐらされた礫群と、その後ろにある壁の「壁柱跡」がほんとにあったのだとしたら、竪穴式住居にある「掘り込み」や「周堤」が見られなかったことと符合して、今のところ「壁」以外にはその形態を説明する方法がなさそうである。縄文時代の「壁建て住居」、ひとつ認識をあらたにせずばなるまい。
八っが岳が、雄大に眼前に聳えている。一番右端が富士山の次ぎに高いという北岳である。見事に晴れた暖冬の一日。 -中略--
これが南アルプス。右の方(写真には写っていない)の奧に北岳があります。
国内最古の「大壁建物」跡出土 滋賀・天神畑遺跡 2011.5.12 20:10 sankei-web
天神畑遺跡で見つかった、国内最古とみられる大壁建物跡=滋賀県高島市(藤原直樹撮影)
滋賀県高島市鴨の天神畑遺跡で、朝鮮半島からの渡来人が建築に深くかかわった「大壁建物」の古墳時代前期(4世紀後半~5世紀初め)の建築とみられる2遺構が見つかり、県文化財保護協会が12日発表した。大壁建物は渡来人がもたらしたとみられ、国内で約100カ所見つかっているが、ほとんどが古墳時代後期(6~7世紀)のもので、国内最古とみられる。同協会は「早い時期から渡来人が広範囲に活動していたことを示す貴重な資料」としている。
和風建築は柱と柱の間に壁を造るが、大壁建物は細い柱を骨材とし、壁の中に土で塗り固める。これまでは、5世紀前半のも
のとみられる南郷柳原遺跡(奈良県御所市)の遺構が最古とされていた。
今回見つかった2カ所の大壁建物跡は、それぞれ縦約10メートル、横約12メートル。四方の外壁部に溝(幅約60センチ)
が残り、深さ約30センチの多数の穴があったことから細い柱を立てたとみられる。
溝から4世紀後半~5世紀初めのものとみられる土器が見つかり、古墳時代前期の可能性が高いと判断した。神聖な場所とされた川の合流地点で、渡来人が祭祀(さいし)を行ったと推測される。
日韓交流史に詳しい林博通・滋賀県立大名誉教授(考古学)は「朝鮮半島でもここまで古い大壁建物跡はほとんど見つかっていない。渡来人が早い時期から日本で、首長らの信頼を得て祭祀を行っていたことがうかがえる」と話している。
現地説明会は15日午後1時から。問い合わせは滋賀県文化財保護協会((電)077・548・9780)。 邪馬台国大研究・ホームページ /遺跡の旅/ 金生遺跡
ーーーーーーーーーーーーーー
金生遺跡の焼けた人骨幻視
金生遺跡の焼けた人骨と配石の幻視
金生遺跡の配石遺構の中にある、石棺状石組みから発見された人骨は、
焼けた人骨というのは焼かれたものなのか、それとも火事などで焼けてしまったものなのか。配石先端の住居の住人が不慮の火事で死んでしまったのでは無いのだろうか。
死体を焼いて骨にするということは当時行われていたのだろうか。
もしかして不慮死を原因として、このシャーマンを記念するため配石が作られたのか、またはシャーマンの仕事を、継承するために配石が作られたものなのか。
遺跡の発掘報告などからは、金生遺跡の始まりは、それ以前にはこの遺跡周辺には何件かの住居が散在していただけであったようだ。
そして最初、後に配石遺構が形成されたときに、東の先端になる当にそのポイントに一軒の住居が出来たことに始まるようだ。この位置から配石の形成が始まっている。
この位置は太陽観測の天文台としての決定的ポイントであるように見えるので、シャーマンの住居がこの天文台の起点となって始まった遺跡のように感じる。
もしそうならそこに住居を置いたシャーマンが関係する配石遺構だろうと考える。
そして配石の形成はそのシャーマンにより始められたものなのか、または何かの事故なり事件が起こり、それを契機としたものなのだろうか。
金生遺跡の配石内での人骨の発見状況は特異なものなのではと考えた。
引用----
金生遺跡 ところでこの1号配石の全体像ですが、もう一度図7をごらんになってください。これによって1号配石の構造がだいたいわかります。まず尾根に対して横長になっているのですが、その横の長さは六〇mくらいあります。図の下が南で斜面の下の方に当たります。そして上に向っての幅は一〇mくらいあります。つまり一〇mの幅で六〇mの長さに尾根を横切って構築されているのです。南北の中央辺りに大きな石を背骨のように連続しながら置いてありまして、その手前の斜面の下の方が丸い石組み、上の方が四角っぽい石の配置というようになっています。図7にてペンで丸とか四角とかで囲んであるのがそれです。方形の配石など周石住居と同じような形で、四角に石が並んでいるのです。
さらに12のような面白い石組も発見されました。位置としては図7にある②ブロックのペンで囲った左側の箇所がこれなのですが、まるで古墳の石室とか弥生時代の石棺みたいな感じで長方形に石が並んでいるのです。実はこの中から人骨が出土しています。但し人骨とは言っても、頭蓋骨の一部、骨盤の一部、手の一部、足の一部ということで体のそれぞれの部分が少しずつここに入っていたのです。しかもこれらは全部火を受けていた、つまり焼かれていたのです。ですからこの石棺状遺構には、焼いた身体のうちのそれぞれのパーツをここへ納めたのかなという感じですね。
---------
もともと石棺状遺構といいますのは、山梨では後期から広くみられるようになります。それは長さ一m五㎝から二mくらい、幅五〇㎝から八〇㎝くらいまで石をきれいに並べて造られていまして、船形の石棺みたいにきれいに整っています。石の蓋については、残されているものも少しはあるのですが、大方には見られません。青森を始めとして東北地方から関東・中部にはたくさんあります。後期の中頃以降、こういう石棺が非常に増えています。この石棺状の配石遺構とはいったい何なのでしょうか。生身の人間を本当に埋めた一次埋葬なのかなという感じもしますが、人骨が残っている例は非常に少ないようなのです。従っていったん埋葬したのを骨だけになったのを取り出して、別の場所に埋めなおすといった埋葬方法もあったのかとも考えられます。そうした場合、一旦埋葬を行う場所がこの石棺状の施設ということになるのかもしれません。金生遺跡の先ほどの例では焼けた人骨の破片が出土しておりますので、二次的な埋葬施設とも考えております。でも1号配石遺構の下面にも石棺状のものがいくつもあるようなのですが、これらが全て二次埋葬施設であるとは言い切れません。なぜならばこの1号配石遺構は後期の中頃からつくられ始め、晩期前半期まで機能していたことがわかっているからです。つまり長い期間この場所が石棺状遺構やそれに伴ういろいろな石組施設をつくる場所であったわけであり、少なくとも晩期には焼かれた骨が納められるようになったということでしょう。
ーーーーーーーー
では、この配石遺構全体の用途は一体何であったのでしょうか。確かにひとつにはお墓だと、ただお墓だけども普通のお墓じゃなくて、やっぱり特定の人を埋葬してそこでお祈りするような場ではなかったかなと思うのです。大小の石棒もあるし丸石もあるし、土偶も非常に多いということから、墓を中心としてその祭りに使ったような施設がここにあったのかなというような感じがするわけであります。だからこそこういう石をいっぱい集めたのでしょう。で、ここで問題となるのはじゃ誰がこんなに石を集めたのかな、ということになります。図11からもわかるように、膨大な量ですよね。これだけ多くの石を金生の集落の人数だけで運ぶことができたのかな、という問題が生じます。例えば一番大きく発達した晩期前半のムラは七軒か八軒の住居から構成されていますが、それだけの人間だけで運ぶことができたのか。かなりこれは疑問に思います。
ーーーーーーーー
金生遺跡は八ヶ岳南麓の南北にのびる標高760~780㍍の尾根上に立地し,縄文時代の遺構としては前期から晩期までの住居址38軒と後期から晩期の配石遺構,集中遺構,石棺状の遺構から構成されている。前期と中期の住居址は3軒ほどで,他は後期ないし晩期の祖所産で,配石・集石遺構群とあわせて金生遺跡は主として、後期前半から晩期終末に至るまでの遺跡群と理解されている。とくに1号配石と名づけられた遺構群は,幅10m長さ60m以上に及んで大小さまざまな石が組み合いされてできあがり,最も特徴的な遺構となっている。
子細にこの配石をながめると,石垣状の列石や立石を中央に,北側に石棺状の石組み,南側に円形の石が配され,それらが構成要素となったブロックが4-5ほど集合して全体の配石ができあがっている。そしてこれらの円形石組みや配石などには石棒や丸石が組みこまれたり,土器や土偶,耳飾などが伴出している。
1号配石は出土土器から晩期前半に位置づけられているが,この遺構の北側に接して同時期の住居址が発見されており,両者は一体化したものと考えられる。そのほか,石棒・丸石・独鈷石・土偶・壷形土器などを出土した集石遺構や底に扁平な石を敷きつめた石棺状の石組み遺構,火を受けたイノシシの下顎骨が100個体ほど埋蔵されたどこう土壌などが発見され,全体として祭祀的な性格が濃厚な遺跡と理解されている。
ーーーーーーーーー
1980年(昭和55年)、圃場整備に伴い山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、38棟の住居址、5基の配石遺構が確認されました。
石組は方形や円形で、立石、石棒、丸石などが配置されており、石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具も出土しています。そのため墓前祭祀行為が行われていたとも考えられているようです。
北杜市の学芸員佐野隆さんによると、この遺跡は主に祭祀の場所として存在していたという。家も特徴的で、床に平たく割った石を敷き詰めた敷石住居や、家の周りにぐるっと石を置いた石組住居などが作られた。石を組んで作った棺のような場所からは、焼けた人骨片や耳飾などの装飾品も見つかっている。
こう聞くと、金生遺跡の人々は、かくも石が好きだったのかと思ってしまう。
縄文遺跡では、住居址群・配石遺構や、石組などの埋葬施設、石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具も出土しており、祭祀施設などが「複合」した複合遺跡になっています。
縄文時代の晩期であることから、寒冷化が進み、弥生時代には使われなかったようです。
ーーーーーーーー
<発掘調査と検出遺構・出土遺物>
1980年(昭和55年)、圃場整備に伴い山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、38棟の住居址、5基の配石遺構が確認されている。
住居址は縄文後晩期が中心で、竪穴式住居や敷石住居、石組住居など。石組は方形や円形で立石、石棒、丸石などが配置された形態で、石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具も出土しており、墓前祭祀行為が行われていたとも考えられている。
出土遺物は200点を越える土偶のほか石棒、石剣、独鈷石、祭祀用土器などの祭祀遺物のほか、日用品や土製耳飾などの装身具が出土。
動物遺体では縄文時代のツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカの大型動物化石が出土しており、特に大半が幼獣の焼けたイノシシの下顎骨が138個体分確認されており、これらは縄文時代にイノシシの飼養が行われていた可能性があるものとして注目されているほか、狩猟儀礼や農耕儀礼が行われていたとも考えられている。
ーーーーーーーー
従来から、縄文後期から晩期に人口が激減したとされる山梨県を含む高地中部地方では、縄文中期に文化的隆盛期を迎え、以降次第に衰退し、その後独自の文化は無かったとされていた。この考古学の定説が、金生遺跡の発掘によって覆されたのである。昭和55年(1980)、圃場整備に伴って調査された発掘で、東西80m、南北15mにおよぶ配石遺構が多数の住居跡と共に発見された。
ここでは、住居跡38軒、配石遺構5基、集石遺構3基、石組み遺構16基など豊富な遺物が発見されている。焼けた猪の顎の骨が138頭分同一箇所から出土したので、通常の集落ではなくて祭祀場所だったのだろうという説が有力だ。水田の下にあった遺跡は保存状態が良好で、夥しい石組の間からは土器・石器・石棒・石剣・独鈷石・土偶・耳飾り・ヒスイ製垂飾などの祭祀用具・装身具が検出された。
ーーーーーーーー
①【金生遺跡】
山梨県北杜市(旧北巨摩郡大泉村谷戸寺金生)にある遺跡。国指定の史跡。
1980年、圃場整備に伴い山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、38棟の住居址、5基の配石遺構が確認されています。住居址は縄文後晩期が中心で、竪穴式住居や敷石住居、石組住居など。石組は方形や円形で立石、石棒、丸石などが配置された形態で、石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具も出土しており、墓前祭祀行為が行われていたとも考えられています。
⑥【栃原岩陰遺跡】(とちばらいわかげいせき)
長野県南佐久郡北相木村で1965年に発見された縄文時代早期の岩陰遺跡である。所在地は北相木村字東栃原上ノ段。1987年に国の史跡に指定されました。栃原岩陰遺跡は、10体以上の縄文時代早期の人骨が出土したことで知られ、土器、石器、骨器、食料にしたと思われる多数の動物(絶滅したニホンオオカミを含む哺乳類、爬虫類、淡水性の魚介類など)の骨なども出土しており、縄文時代早期の衣食住の研究に非常に多くの資料を提供している。遺物中、骨製の釣り針、縫い針の精巧さは類を見ず、当時の人々の技術水準の高さを物語っている。これらの遺物の多くは出土人骨から復元された「相木人」の頭部復元模型などとともに北相木村考古博物館に展示されています。
(※参考:Wikipedia)
長野県南佐久郡北相木村の栃原岩陰遺跡(とちばらいわかげ)は、12体の縄文時代早期の人骨が出土した事で有名であるが、八ヶ岳から流れ出た相木川泥流が堆積した崖を、相木川が長年月に亘る流力で削りとった岩陰に縄文早期の小規模な遺跡を3つ残した。そこでシカなどの足の長管骨を裂いて作った釣針が出土した。しかもサケ・マス類の脊椎骨までも伴出した。日本海の信濃川から千曲川を遡り、さらに遡上を続け、群馬県の県境、長野県の相木村にまで達していた。