昨年の晩秋~年明けしばらくの間、
拙ブログでずっと、断トツのアクセス数で一位だった記事があります。
それは
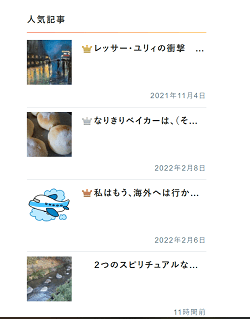
レッサー・ユリィ。
三菱一号館美術館で開催されていた
イスラエル博物館の所蔵展で、突如ブームとなった近代画家。
どうも哲学的で、色彩も暗めで重い印象のドイツ近代絵画の中で
格段にキャッチーで“あかぬけた”雰囲気を持つ彼の作品は
ポストカードが売り切れるほど話題を呼び。
私も…
 「ドイツ語学科の割には、ドイツ表現主義とかって
「ドイツ語学科の割には、ドイツ表現主義とかって好きじゃないんだよねー」
 「私も、私も! クレーとかは好きだけどね。
「私も、私も! クレーとかは好きだけどね。そういえばこの人、ドイツ語読みだと“ウリィ”だよね」
 「うん。この人はわかりやすくて、いいね」
「うん。この人はわかりやすくて、いいね」なーんて、元同級生とメッセンジャーで話したりしていて。
趣味の範疇ですが、高校時代から40年間も美術館巡りをしていて
海外の美術館もいくつか訪ねた経験上、
ここまでぱっと惹かれる画家はそうそう、いなかったなあと
ちょっと感激して、ブログに書いたところ
ほかに、タイトルまでつけて書いた人は少なかったのか
翌日からアクセスが急増。
着物中心のブログなのに、2か月以上も一番、読まれていました。
(私も、良く知らない画家だったので)浅い内容だったにも関わらず。
まあそれだけ、人気の割には情報が少なかったのでしょう。
そうしたら、
2月上旬に、山田五郎さんのYoutubeチャンネルで
この画家が取り上げられ、
何と、ドイツ語の文献を調べたとのことで、より詳しく勉強することができました。
【レッサー・ユリィ】なぜ日本で!?突如話題になった無名画家【人気の秘密】
こちらの番組によると
人気を博した彼の、都会の街角やカフェの情景を描いたシリーズは
どうも、彼自身が好きだったから、というよりは
ウケが良かったので(仕方なく?)量産していたよう。
ユダヤ人である彼は、実はドイツ印象主義における「シオニズム運動」の旗手で
(パレスチナにユダヤ人の民族国家を再建しようという思想や運動)
本当は、もっと宗教色の濃い、死生観をモチーフとした絵画で
有名になりたかったのだが、そちらではさして注目されなかった……と。

そして、20世紀初頭当時はそこそこ、欧州では知名度が高かったが
自分の意に反して注文の多かった、カフェシリーズを量産しすぎて
現代の、オークションでの市場価値は大して高くない……らしいです。
それで、ふっと思い出したのが、
意図せずアクセスが爆上がりした、ユリィについての記事に
何気なくリンクを貼った、
スイスの画家 フェルディナント・ホドラー。
彼も、「死生観」を大きなテーマの一つに掲げており、
全盛~晩年にかけて「生と死」を取り上げた大作を発表し、
こちらは高い評価を得ていました。

ホドラーがこのテーマを好んだのは
幼いころに身内を次々と病気などで亡くした経験からだそうですが
ユリィもホドラーも同じ流派(ベルリン分離派)にいたことがあり
ドイツ表現主義と縁があるため、
あくまで素人目で見て、ですが
ユリィが描いたシオニズム絵画と、ホドラーの絵画の画風が似ているのです。
どちらも、内から沸き起こるパッションの熱量は
背景は違うとはいえ、同じようなものだったのでは。
そして、画風も何となく似ているのに
ホドラーは評価を得て、ユリィは評価されなかった。
何とも、複雑な気持ちになりました。
作品を生み出すだけでなく、それを世に、メッセージとともに
広めていくことの難しさ。
「知られなければ、ないのと同じ」と言われてしまう、アートの切なさ。
(ユリィのシオニズムのことも、こうして山田五郎さんが取り上げて
くださらなければ知らないままだったし、多くの日本の人もそうだったのではと)
オシャレでエッジの効いた、ユリィの街角やカフェの絵を
今後、目にしたときには、以前とは別の感情が沸き起こってきそうです。


















