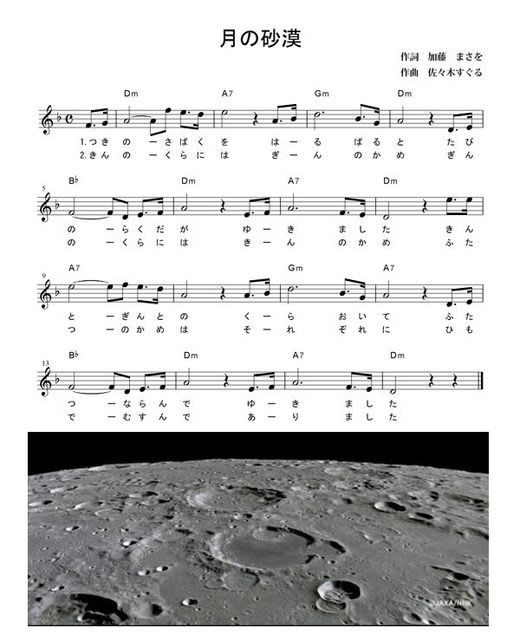好きなミュージシャンについて書こうと思う。第1回目は浅川マキ。とてもマニアックな話です。
浅川マキは1942年に石川県で生まれた。高校卒業後、町役場で国民年金窓口係の職に就くが、すぐに辞めて上京。ビリー・ホリデイのようなスタイルを指向し、米軍キャンプやキャバレーなどで歌手として活動を始めた。1967年にビクターから「東京挽歌」を発表するが、この作品は本人の意にそぐわなかったようで、その後彼女はこの曲を封印してしまう。
1968年、寺山修司に見出され新宿のアンダー・グラウンド・シアター「蠍座」で初のワンマン公演を 三日間にわたり催行、クチコミで徐々に知名度が上がる。やがてレコード会社を移籍し、1969年に「夜が明けたら/かもめ」で正式にレコード・デビュー。以後、数々の作品を発表しつつステージを主体に音楽活動を行う。
CDの音質に対して懐疑的であったため、1998年以降は新譜を発表せず、ライブ活動に専念している。2010年1月、ライブ公演で滞在していた名古屋市内のホテルで倒れ、そのまま死亡。享年67歳。死因は急性心不全とみられる。
以上は、インターネットで調べた浅川マキの略歴である。ここで僕が初めて知ったことが二つあった。ひとつは歌手になる前は役場の国民年金窓口係だったということ。これは意外だ。全然似合っていない。あの顔とあの声で受付をされたら、国民年金の申し込みに来た人も先行き暗い気持ちになるだろう。
もうひとつは「東京挽歌」の話。僕は「夜が明けたら」がデビュー曲だと思っていた。浅川マキ本人はこの「東京挽歌」を自らの汚点のように思っているらしく、これまでの発表曲を記録したディスコグラフィーからも抹消されている。浅川ファンとして知られる音楽ライターが「東京挽歌の音源を持っている」と自慢げに本人に話したところ、「棄ててください」と言われたそうだ。
浅川マキに関するエピソードをもう少し紹介しよう。
自らの作品において「作詞」と表記する際、「詞」ではなく「詩」を用いている。また、外国作品を自ら日本語で歌う場合、原作の持つ世界観を損なわぬよう、まず翻訳家に対訳を依頼し、メロディーから受けるイメージも採り入れたうえで練り直して新たに詩作を行う。そのため表記を「訳詩:浅川マキ」とせず「日本語詩:浅川マキ」としている。
1993年、東芝EMIが「音蔵シリーズ」と称するアルバム作品群のCD化企画を行い、その中に浅川マキのアルバムが4タイトル含まれていたが、発売後短期間で廃盤となった。「音質が気に入らなかった」とマキ本人が語っており、その強い意向で会社側としても廃盤にせざるを得なかったらしい。
このように「詩」について、また「音」について、徹底したこだわりを持ち続けた。数々の有名ミュージシャンと協演しているが、山下洋輔のような大御所に対しても、演奏が気に入らなければ容赦なくやり直しを命じたと言われている。
僕が浅川マキを知ったのは中学生の頃だった。ラジオの深夜放送で流れているのを耳にした程度で、不気味な音楽という印象だけが残っている。当時の僕はまだ清純で、その不気味さを心地よく感じるほど成長していなかったのだ。
高校に入学してクラブ紹介のとき、フォークソング部の発表で有吉さんという先輩が浅川マキの曲を歌った。「♪ あたしが着いたのはニューオリンズの 朝日楼という名の女郎屋だった」他の部員はかぐや姫だとかチューリップだったが、有吉さんはギター1本で「朝日楼」だ。この演奏には度肝を抜かれ、さすがに高校はすごいところだと実感した。ちなみにこの人は、高校卒業後アメリカへ渡り、今ではブルースの本場シカゴでピアニストとして活躍されている。高校1年生の時、その有吉先輩から「MAKI・Ⅱ」というアルバムを録音したテープを借りて聴いた。それが浅川マキとの最初の出会いと言ってよいだろう。
中島みゆきの歌は暗いだとか、いや山崎ハコはもっと暗いだとかいう議論があったが、暗さに関して言えば浅川マキの右に出る人はいないだろう。彼女の歌は陰鬱で、寂しく、たまらなく悲惨だ。
しかし、そこに登場する風景はアメリカの貧民街であったり、港町の酒場であったり、また刑務所であったりと、ほとんど自分には縁のない所だ。だから僕はその暗さや寂しさを客観的に見つめることができる。言うなれば他人事の暗さや寂しさなのだが、それでも浅川マキの歌は、その遠い世界の悲惨さを僕のすぐ近くまでひしひしと伝えてくる。僕は迫り来る悲惨さを体の表面ぎりぎりで受け止め、その歌の世界に聴き入る。体の中にまで侵入させてしまったら、あまりに痛々しくて、とても聴いていられないだろう。
高校生時代は友人の家で浅川マキのレコードをよく聴いた。ナイショでタバコを吸ったり酒を飲んだりして聴くものだから、部屋中に背徳の匂いが立ちこめる。そうして、しばし陰鬱かつ退廃的なムードに浸ったあとは、自転車に二人乗りして「天下一品」のラーメンを食べに出掛けたりしたものだった。
浅川マキの初期作品は寺山修司の演劇世界とつながっているが、彼女がほんとにやりたかったのはそういうものではなかったようだ。有名になってからはジャズ、ブルース、ゴスペルなど外国作品を多くカヴァーし、シンガー・ソングライターというよりもボーカリストといった色彩が強くなる。レコーディングやライブ公演には名だたるジャズ演奏家を招き入れるが、それはもはや浅川マキのバックバンドという存在ではなく、マキがボーカルを担当する全日本選抜セッションバンドといった感じになっている。
僕が信州の大学に入学した年、松本市内で行われるライブ公演のポスターを見つけた。まさかこんな所で浅川マキに出会えるとは思わなかったので、うれしくなってすぐに前売りチケットを買った。
ライブ会場は、なんとお寺の本堂だった。最初に住職の読経があり、それに続いてマキが登場。客は畳の上であぐらをかき、中には寝そべっている人や一升瓶の酒をまわし飲みしている人もいた。場内には「勧煙」の貼り紙があり、客席となった畳の上には灰皿がいっぱい置いてあって、マキも他のミュージシャンもタバコを吸いながら演奏した。タバコと線香の煙で空気はひどい状態となり、愛煙家の僕でさえ気持ち悪くなるくらいだった。ジャズ系の曲が中心で、演奏された曲目はよく覚えていないのだが、そのとき受けた感銘はまだ胸の奥に残っている。真っ黒のドレスを着てお寺の本堂に立つ浅川マキは、何とも言えず不気味だった。
そのあと、大学から帰省中の京都で浅川マキのライブを見た。冬の寒い日、四条大宮の映画館で夜の10時頃から開演し、なんと朝までやるという。この公演には「始発まで」というタイトルがついていた。長いライブが終わったあと、僕は本当に阪急電車の始発と京阪京津線に乗り継いで家へ帰った。
1曲目、舞台中央に立ったマキ一人に薄暗いスポットライトが当たり、無伴奏で淡々と歌い始める。ワンコーラスが終わり、ツーコーラス目の途中からいきなり伴奏が入るのだが、その音程がぴったり合っていて驚いた。浅川マキは、その独特の雰囲気ばかりがクローズアップされがちだが、歌唱技術といった面でも素晴しいものを持っている。
そのときのミュージシャンはそうそうたるメンバーだったが、特にギターは内田勘太郎&渡辺香津美という滅多に見られない二大巨匠の共演で、まさに感動物だった。後半は浅川マキもかなりノリノリの感じで、この人は実は明るい性格なのではないだろうかと思ったくらいだ。
ほんとのところ、浅川マキのあの暗さは、意図的に作り出されたものではないかと僕は思っている。石川県からわざわざ上京して人前で歌おうなんて、陰鬱な性格の人ではまずできないことだ。また、全盛期でのレコーディングやライブ活動のスケジュールは非常に精力的で、エネルギッシュな人でなければとてもこなせない。CD化拒否に代表されるように「音」に対して徹底的なこだわりを見せ、さらにはレコードのジャケット、ライナーノート、ポスターのデザインなどにも一貫した美意識を持ち、終生その姿勢を崩すことがなかったという。こうしたこだわりを貫くためには強大なエネルギーを必要とするし、それは孤高の自意識と、プロとしての責任感みたいなところから生まれてくるのだと思う。
浅川マキは意外とポジティブな性格の持ち主で、ステージで見せる言動や表情などについても、綿密な計算に基づいて演出されたものではないかという気がしてくる。
日本人のジャズ・シンガーはたくさんいるが、概して言えば、みな上品すぎるような気がする。耳に心地よく入ってくるが、すぐにもう一方の耳から抜けていく。そこに残るものは何もなく、刺激もなければ毒もない。BGMとして聴くには丁度よいのだが、その歌によって創り出される世界に浸るという冒険はできそうにない。変な喩えだが標準語で演じられる吉本新喜劇みたいなもので、表現法の違い云々の問題でなく、そこに本来あるべき原点のようなものが完全に欠如してしまっているのだ。
浅川マキの歌は、これらとはまったく異質だ。その声質は決して耳に心地よいものではなく、ときには不快でさえあるが、何か心の内面に直接響いてくるようなものがある。彼女の創り出す世界は、一般によく用いられる「泥臭い」といった表現をはるかに通り越した「血なま臭い」印象すら与え、本場のジャズやブルースの根底に流れる魂の叫びみたいなものを感じさせる。
全身黒ずくめの衣装は、あたかも魔女を連想させるが、いやそんなに神秘的なものではない。彼女は現実に世界のどこかで起こっているであろう(あるいは過去に起こっていた)人間社会の悲哀を歌う。あの暗く陰鬱な独特の雰囲気は、たとえそれが一種の演出であったにしても、僕たちを遠い非日常の世界へと誘い込むための仕掛けとしては十分だ。
浅川マキのライブを見たのは先に述べた二度だけだ。いくら望んでも、もう決して見ることができない。浅川マキのようなシンガーは類稀で、誰も彼女の代わりを務めることは不可能だろう。
名古屋のライブ公演を前にしたホテルで亡くなったというのは、どう考えても無念だ。せめて、できることなら、あとしばらくがんばって、ステージの上で息をひきとって欲しかった。そのほうが本人にとっても幸せなことだったと思うのだ。