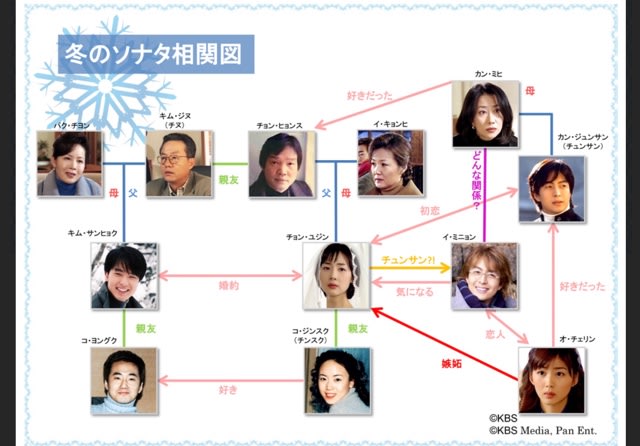
その夜、二人はミニョンの定泊していたホテルに戻ってきた。10年ぶりにチュンサンとユジンとして再会した二人を隔てるものは何もなかった。二人はソファに向かい合って座り、飽きる事なく見つめ合っていた。
特に10年間チュンサンが死んだと信じていたユジンの喜びは格別で、涙を浮かべて瞬きもせずにミニョンを見つめていた。その姿は昨日までサンヒョクとの間で揺れていたユジンとは別人のようだった。
「こうしてまた会えるなんて信じられない、、、チュンサン、、、チュンサン、、、チュンサン、、、。」

ユジンは何度も何度もチュンサンの名を呼んで、これが夢でないのだと確かめていた。
一方でミニョンは複雑な胸中でいた。空港でうっすらとユジンのことを思い出してはいたが、チュンサンとしての記憶は全くと言っていいほどないのだった。ただ、自分がかつてチュンサンだったと言う事実だけが重くのしかかる。特に熱を帯びた眼差しで自分を見ているユジンの期待に答えられない自分が、たまらなくもどかしかった。

「、、、ユジンさん、何でも話してください。僕は思い出せなくても、全ての話を聞くことは出来ますから」
ユジンは泣き腫らした目で語り出した。
「チュンサン、チュンサン、チュンサン、時々、たまらなく名前を呼びたくなることがありました。でも声に出せなかった。だって、返事がなかったら、チュンサンが死んだことをみとめなくちゃならないから、、、。でも、あなたが死んだなんて、どうしても信じられなかったんてす。だって、あなたはわたしと会う約束をしたんだもの。約束を破るはずがないってわかってたんです。」
ミニョンは困惑した眼差しで言った。
「僕が、、、あなたと会う約束を?」
ユジンは悲しげな表情で言った。
「ええ、全然覚えてないんですか?本当に記憶にない?」
ミニョンは静かに首を振った。ユジンの熱い想いに応えられない自分が不甲斐なくてたまらなかった。しかし、記憶のどこを探っても、何一つ思い出せそうもなかった。ミニョンの目からは次々と涙がこぼれだした。

ユジンは泣き腫らした顔のまま、独り言のように話を続けた。
「本当に、本当に何一つ覚えてないの?わたし、あなたにピンクのミトンを貸したのよ。それを大晦日に返してもらうつもりだったのに、、、。それから、ピアノを弾いてもらったり、、、二人で授業をサボって自転車にも乗ったの。手だって繋いだんだから。」
ユジンは一つ一つ確かめるようにミニョンを見ながらポツポツと話す。
「ユジンさん、すみません。本当にすみません。覚えていなくて、、、」
ミニョンは涙を流すしかなかった。
「ミニョンさんは悪くないんです。悪いのはチュンサンです。わたしは、わたしは何一つ忘れられずに全て覚えているのに、私のことを忘れて生きているなんて、チュンサンが悪いんです。」
そう言ってさめざめと泣くユジンを、ミニョンは抱きしめることしか出来なかった。前にミニョンとしてユジンを抱きしめたときには、彼女はおずおずと背中に腕を回してきた。しかし、ミニョンがチュンサンと分かった今、ユジンはしがみつくようにミニョンを抱きしめていた。まるで、二度と離すまい、という決意の現れのようだった。そこに彼女の想いの強さが感じられて、ミニョンの心はますます苦しくなった。やがて、ユジンはいつのまにか泣き疲れて、ミニョンの腕の中で眠りについた。

ミニョンはそんなユジンをそっとソファに寝かせると、ユジンの携帯からどこかに連絡をとった。相手はサンヒョクだった。
その頃サンヒョクは、ユジンが帰宅しないと心配するチンスクと一緒に、ユジンとチンスクのアパートで帰りを待っていた。そこにユジンの携帯からの電話がかかってきたのだった。しかし、電話の相手はミニョンだった。サンヒョクはミニョンの声を聞いて、すぐにユジンと一緒だとわかった。彼はユジンの携帯を持っているのだ、、、。
「ユジンは全てを知ったんですね?」
しかしミニョンはそれには応えなかった。
「僕はやはりアメリカに行きます。明日たちます。今晩はユジンさんは寝てしまっています。起こすのはかわいそうなので、明日の朝迎えに来てもらえませんか。」
そう言って電話は切れた。あとに残されたサンヒョクは絶望感でいっぱいだった。ユジンが真実を知った以上、もはやミニョンが何をしようと、彼女の心は戻らないだろう。まるでこの世の終わりのようだった。来るべきときが来たのだ。そんなサンヒョクを、チンスクと、チンスクからの電話でやはり駆けつけたヨングクが心配そうに見守っていた。
「どうして、ミニョンさんから電話があるの?なぜ二人は一緒なの?」
サンヒョクは静かに答えた。

「ミニョンさんがチュンサンなんだよ。ミニョンさんが、チュンサンなんだよ。」
それを聞いた瞬間、さすがの二人も黙ってしまった。混乱する頭の中でも、一瞬でサンヒョク、ユジン、ミニョンの立場を理解して、サンヒョクの気持ちを考えると何も言えなくなってしまったのだった。ユジンとチュンサンの絆がどれほど深いものか、10年前にチュンサンが消えたときのユジンの憔悴ぶりを静かに思い出していた。

ミニョンはユジンをベッドまで運ぶと、ユジンの髪にそっと触れた。ユジンは泣き腫らした顔のまま、疲れ果てた様子で眠っている。今晩のユジンの様子では、自分がチュンサンであると知ったことで、サンヒョクを捨てて自分の元に来るつもりだろう。いや、もはや彼女の頭からはサンヒョクはじめとしてチュンサン以外のことは入っている様子はなかった。ユジンは自分が唯一恋焦がれた女性であり、それは今も未来も変わらない。しかし、自分はユジンが望むチュンサンなのだろうか。記憶はこれからも戻りそうにないし、自分はあくまでもミニョンで、これからチュンサンとして生きることは出来ない。二人の未来に何があると言うのだろうか。ユジンにはサンヒョクという婚約者がいる。目前に迫っている結婚をぶち壊すことは出来ない。ユジンの幸せはここにはない。ミニョンはユジンをサンヒョクの元に帰すと決めた。そして、自分はアメリカに今度こそ黙ってたつ。そしてユジン含めてチュンサンだった過去とも決別しよう。
ミニョンはそう思いつつも、ユジンの寝顔を飽きることなく眺めていた。決心したものの、本当に自分がそんなことができるのか、どうにも自信がなかった。こうして、2日目の長い長い夜は、一睡もすることなく、夜の空が東から白々とあけてゆくのだった。

























