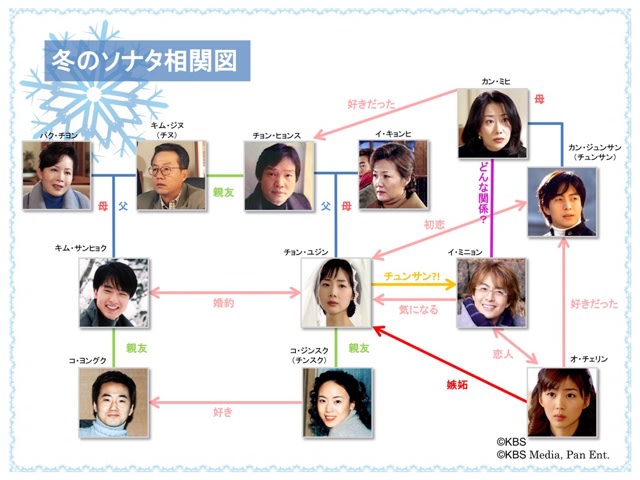
バーを出ると、サンヒョクはユジンの手を振り解いた。彼は猛烈に怒っていたのだ。そのままユジンを置き去りにして車に乗り込もうとするのを慌ててつかまえた。
「サンヒョク‼️待って。」
しかし、振り返ったサンヒョクの目は怒りに燃えていた。

「いつまで、、、いつまで僕を騙せば気が済むんだ?!いつまで苦しめるんだよ!」
「えっ?」
ユジンは戸惑い、瞳が揺れた。
「僕が来て悪かったな。ミニョンさんがいるならいるって言ってくれよ。邪魔しないから。」
ユジンは毅然として言った。
「彼がくるなんて知らなかったの。騙してなんていない。嘘をついたと思ったの?」
信じられないという目でサンヒョクを見つめる。しかし、サンヒョクは冷たい目で切り返した。
「じゃあ昨日は?なぜ彼と会ったんだ?」
ユジンはたじろいだ。なぜサンヒョクがそれを知っているんだろう?
「それは、、、返すものがあったから会ったの。」
サンヒョクは鼻白んで失笑した。
「へぇ、そうか。僕がいなかったら、今日も何か返すつもりだったんだろ」
ユジンの言うことをまるで信じていない、憎しみのこもった声だった。
「サンヒョク、何で?なんで、、、」
「おまえ、こんな言われ方、イヤだろ?信じて欲しいんだろ?僕だって信じたいよ。僕は死ぬほど苦しんだのに、お前に罪の意識はないのかよ?僕は君がいればそれでいいのに、君は僕だけじゃ満足できないのかよ?えっ?」
ユジンはもはや全てを諦めたくなった。思わずため息をついて真剣な眼差しでサンヒョクを見つめた。

「サンヒョク、サンヒョク、そうじゃないってば」
ユジンは誤解を解くために必死に訴えた。
しかし、サンヒョクは聞く耳を持たない。怒りに燃えたまま、ユジンをふりほどいて、さっさと車に乗り込んで発車させた。ユジンは車を見送るしかなかった。最近はやることなすこと空回りしている。やればやるほど深みにハマっててしまう。ため息をつきながら、タクシーを拾うために大通りをうろついた。

サンヒョクを追いかけて、誤解を解こうと思っていたのだ。しかし、週末のソウルはタクシーを待つ人でいっぱいだった。やっと捕まえたと思っても、横から人が来て取られてしまう。ユジンは途方にくれていた。
その時だった。後ろから誰かがユジンの腕を掴んだ。振り向くとそれはミニョンが立っていた。

ミニョンは気まずさだけが残るバーを出て、夜道をぶらぶらしていた。すると、大通りでユジンがタクシーを捕まえようとただずんでいるのが見えた。車道に出すぎていて、このままでは轢かれてしまいそうだ。ミニョンはすぐに状況を把握した。バーで自分の姿を見たサンヒョクが怒って、ユジンに八つ当たりして置き去りにしたのだろう。ミニョンはユジンのことがかわいそうでならなかった。そのとき、またユジンがタクシーを捕まえようと、車道にはみ出た。ミニョンは思わずユジンの手を掴んだ。その腕は折れてしまいそうなほど細くて儚くて、ミニョンはドキッとした。


そして振り向いたユジンはびっくりした顔をした。思いがけず近距離で見つめ合った二人の視線が、一瞬だけ交差した。
しかし、ミニョンはすぐに視線をはずすと、道路に出てタクシーを捕まえ始めた。

ユジンはミニョンの広くて頼もしい背中をじっと見つめていた。このままタクシーが捕まらなければ良いのに、、、と思いながら。さっき掴まれた腕が熱を帯びたように熱い。しかし、タクシーはすぐに捕まってしまい、ミニョンはそっとドアを開けた。ユジンは涙でいっぱいの目でするりとタクシーに乗り込んだ。何か一言でも発したら、お互いに気持ちが溢れてしまいそうだったのだ。だからユジンは目も合さずに車に乗り込んだ。
ユジンがミニョンの前を通り過ぎてタクシーに乗り込むとき、鼻先をユジンの香りが掠めた。ミニョンの心はチクリと痛み、思わずユジンの手をつかんでしまいそうになった。しかし、その気持ちをグッと抑えこんで静かにドアを閉めた。タクシーはユジンを乗せて音もなく走り始めた。バックミラーに映るミニョンがどんどん小さくなって、やがて見えなくなった。



























