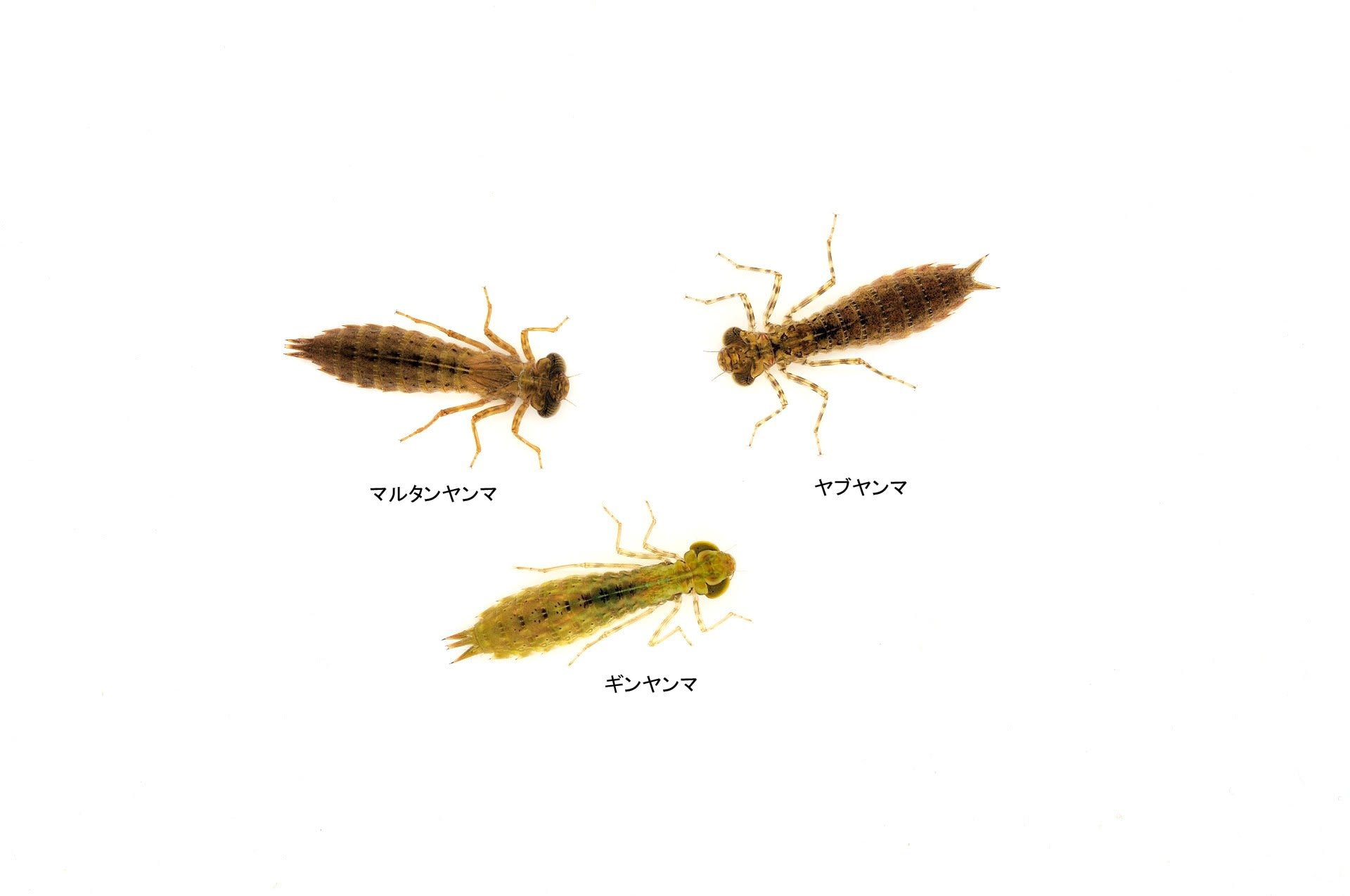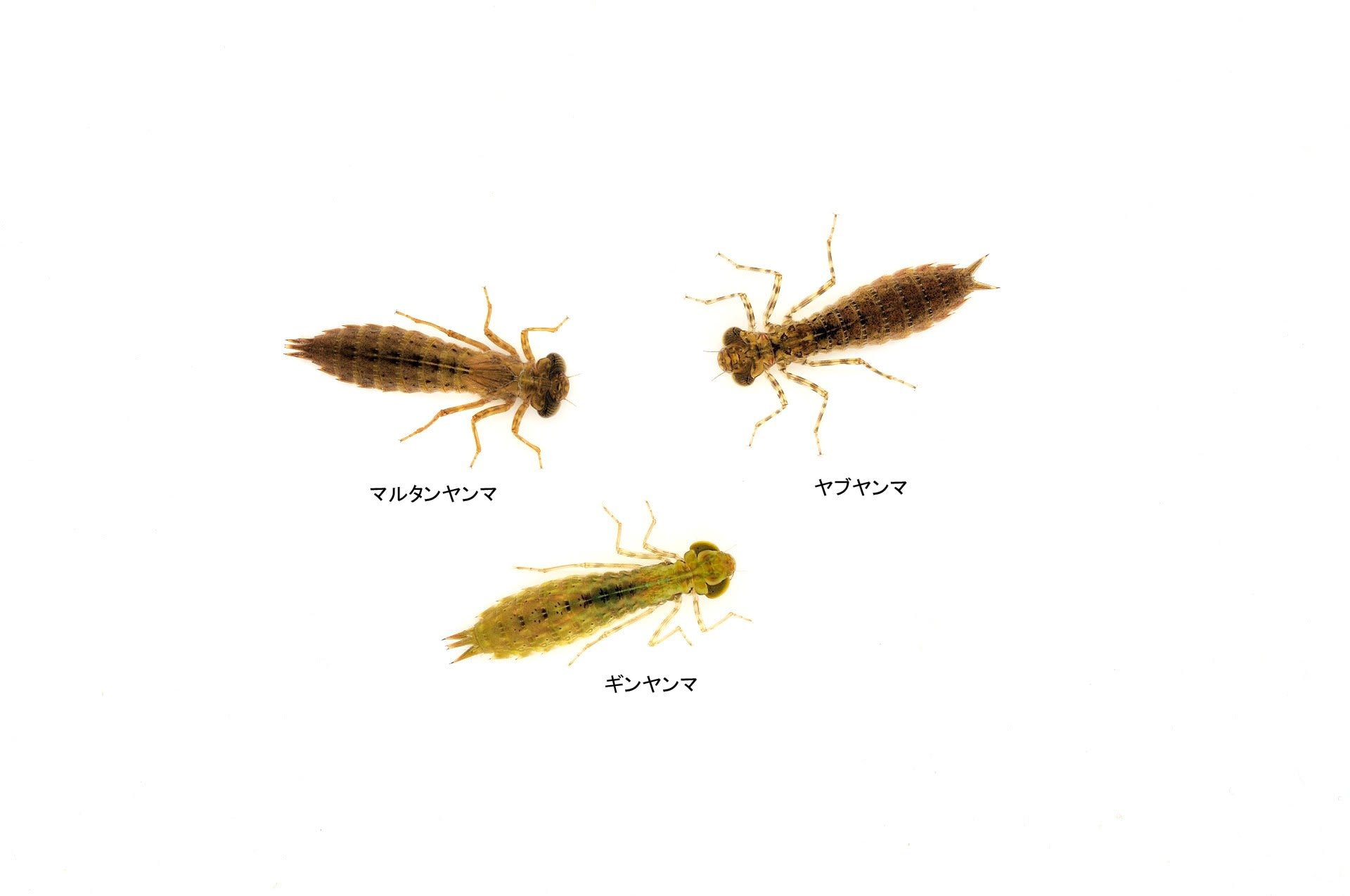前回の観察から1ヶ月が経過したので、変化を見にホソミオツネントンボの越冬地へ訪れた。
今回は越冬風景をぜひ観たいと、リクエストいただいていたSさんをご案内。
レクチャーを受けても初めてのフィールドで発見できる可能性はかなり低い。結果はいかに...
先ずは1ヶ月前に見つけた個体をチェックして行く。すると...
ホソミオツネントンボ 雄

Nikon D810+AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED
ホソミオツネントンボ 雌

Nikon D810+AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED
ホソミオツネントンボ 雄

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
手前にオス
ホソミオツネントンボ 雌

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
奥にメス。1ヶ月前に発見した個体は同じ場所で変化なしの様子。
ホソミオツネントンボ 雌

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
新たに見つけたメス。私は枝ですと言っているようだった。
すると、Sさんの方からスマホの撮影音が聞こえ、いましたとの事!
え、マジで、オス?メス?を伺うとメスとの回答。凄い優秀だ。どれどれ...
ホソミオツネントンボ 雌

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
お~ツル植物に擬態した素晴らしい姿。絶対に初めてでは見つけられないと思っていたけれどお見事!日頃からフィールドで生物観察を行う事が好きな人の眼は違う。と言う事もあるが、寒く広大でゴチャゴチャしたフィールドなのに楽しそうに探していて、越冬場所のイメージと集中力と言うその姿勢が発見に繋がったのだと思う。
ホソミオツネントンボを撮影するSさん

Nikon D810+AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED
この日の成果は2オス10メスの発見に成功。毎回、何故かメスの割合が高い。
クワの木も点在しているので、クワエダシャクの越冬幼虫も探して見ると、みっけ!
クワエダシャクの越冬幼虫

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
え!コレ幼虫なの?と思ってしまうほどクワの小枝に擬態した姿が非常に素晴らしい。ただ、クワエダシャクの越冬幼虫はクワを片っ端から探せば見つかるけれど、ホソミオツネントンボの越冬は樹木や植物に決まりが無いないので難易度は高い。まだ捜索していないエリアがあるので、次回は10オスを目標に楽しんでみよう。初挑戦で見事に発見されたSさん、楽しんで頂けたようで何より。また行きましょう。2月に入ったからそろそろヤマアカガエルのシーズン...あ、そうだフッチーも。
撮影日:2月1日