feelfeelwindowさん
水戸黄門を見ていて疑問に思ったのですが、当時の中国の事を清国と呼んでいましたが、本当に江戸時代は中国の事を清国と呼んでいたのですか?
当時は支那と呼んでいたのではないのですか?
それとも現在は支那という表現が使えない為に清国という表現になっているのでしょうか?
質問日時: 2011/12/8 06:11:11
解決日時: 2011/12/14 09:26:54
komasaram
水戸黄門の時代設定は1690年から1700年までの10年間です。
明は1644年に滅んでおり、水戸光圀は17年後の1661年に藩主になりました。
水戸光圀が隠居の時代の支那は「清国」です。
江戸時代には確かに「支那」と読んでいた可能性がありますが、何しろ今は「コジキ」も「メクラ」も自粛されます。
意外と昭和の初めを扱った昭和時代劇で「支那」ということばが出てくる場合があります。
「山河燃ゆ」では「支那」を自主規制して「中国」を使って、視聴者から「当時は支那と読んでいたのでは」という問合せがあったようで、NHKは「当時は中華民国だった」と弁明したようです。
また、「支那」は「秦」から来てますが、日本で広まったのは蘭学が普及した享保年間以降ではないでしょうか。
オランダ語でChinaは「シーナ」です。ポルトガル語でも同じ発音ですから江戸初期で「シーナ」が使われていた可能性も少しはありますね。
なお、日中戦争の時代に「中国」も使われていたとすると「支那」だけでなく「中国」も戦争の時期に中国に対する敵対や侮蔑の文脈で使われていた可能性もあり、単語だけ取り替えても無意味ということになりますね。
江戸時代の日本人はロシアを「オロシヤ」、アメリカを「メリケン」と言っていたはずなのに「龍馬伝」では「ロシア」「アメリカ」でした。
回答日時:2011/12/8 10:02:36
編集日時:2011/12/8 16:54:41
BLOG内検索 水戸黄門 清国
水戸黄門を見ていて疑問に思ったのですが、当時の中国の事を清国と呼んでいましたが、本当に江戸時代は中国の事を清国と呼んでいたのですか?
当時は支那と呼んでいたのではないのですか?
それとも現在は支那という表現が使えない為に清国という表現になっているのでしょうか?
質問日時: 2011/12/8 06:11:11
解決日時: 2011/12/14 09:26:54
komasaram
水戸黄門の時代設定は1690年から1700年までの10年間です。
明は1644年に滅んでおり、水戸光圀は17年後の1661年に藩主になりました。
水戸光圀が隠居の時代の支那は「清国」です。
江戸時代には確かに「支那」と読んでいた可能性がありますが、何しろ今は「コジキ」も「メクラ」も自粛されます。
意外と昭和の初めを扱った昭和時代劇で「支那」ということばが出てくる場合があります。
「山河燃ゆ」では「支那」を自主規制して「中国」を使って、視聴者から「当時は支那と読んでいたのでは」という問合せがあったようで、NHKは「当時は中華民国だった」と弁明したようです。
また、「支那」は「秦」から来てますが、日本で広まったのは蘭学が普及した享保年間以降ではないでしょうか。
オランダ語でChinaは「シーナ」です。ポルトガル語でも同じ発音ですから江戸初期で「シーナ」が使われていた可能性も少しはありますね。
なお、日中戦争の時代に「中国」も使われていたとすると「支那」だけでなく「中国」も戦争の時期に中国に対する敵対や侮蔑の文脈で使われていた可能性もあり、単語だけ取り替えても無意味ということになりますね。
江戸時代の日本人はロシアを「オロシヤ」、アメリカを「メリケン」と言っていたはずなのに「龍馬伝」では「ロシア」「アメリカ」でした。
回答日時:2011/12/8 10:02:36
編集日時:2011/12/8 16:54:41
BLOG内検索 水戸黄門 清国













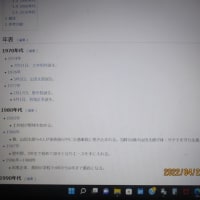



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます