
「ブログで数式を表示させる方法:@WIKIを利用」という記事に対して271828さんから紹介いただいたhttp://www.codecogs.com/というサイトのOnline LaTeX Equation Editorというサービスを使って、ブログに数式を表示させる方法をいくつか試してみた。
Online LaTeX Equation Editor
http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php
アウトラインが美しく表示されてとてもよい感じだ。
TeXでは半角円記号(欧文だとバックスラッシュ)は頻繁に使う。けれどもgooブログは半角円記号の入力、保存していないので、半角円記号の箇所は「%5C」と置き換えて入力すればよい。(2011年1月25日に追記)
記事中に埋め込む数式は、次の2つのHTMLタグのどちらかの書式で記述する。「~」の箇所が数式のところ。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? ~ />
<img src="http://www.codecogs.com/gif.latex? ~ />
数式の入力と表示例をいくつか紹介しよう。
1)べき乗
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ >

2)文字サイズの指定は解像度を指定することで行う。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?%5C300dpi a^2"/ >

表示サイズをHTMLタグから指定すると表示がぼやけてしまうので注意。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ width="50" height="50" alt="">

3)数式のインライン表示
数式をインライン表示させるときには<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ >のように入力する。
数式をインライン表示させるときには のように入力する。
のように入力する。
4)行列
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbegin{pmatrix}a_{11} & a_{12} %5C%5C a_{21} & a_{22} %5Cend{pmatrix}"/>

5)ドット付きの行列
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbegin{pmatrix}a_{11} & %5Ccdots & a_{1n}%5C%5C %5Cvdots & %5Cddots & %5Cvdots%5C%5C a_{m1} & %5Ccdots & a_{mn} %5Cend{pmatrix}"/>

6)集合
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbigcup_{i=1}^{n}{X_i}"/>
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbigcap_{i=1}^{n}{X_i}"/>


7)ベクトル
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Coint %5Cvec{F} %5Ccdot d%5Cvec{s}=0"/>

8)測地線の方程式(一般相対性理論)
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cfrac{d^{2}x^{%5Clambda}}{dr^{2}}+%5CGamma^{%5Clambda}_{%5Cmu %5Cnu} %5Cfrac{dx^{%5Cmu}}{dr}%5Cfrac{dx^{%5Cnu}}{dr}=0"/>
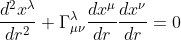
9)重力場の方程式(一般相対性理論)
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? R^{%5Cmu %5Cnu} - %5Cfrac{1}{2}g^{%5Cmu %5Cnu}R = %5Cfrac{8 %5Cpi G}{c^{4}}T^{%5Cmu %5Cnu}"/>
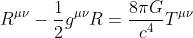
10)定積分
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? I = %5Cint _{a} ^{b} f(x)dx"/>

TeXで数式入力するためのリンク集:
即席 TeX 講座(EMANの物理学)
http://eman-physics.net/bbs/tex_kouza.html
LaTeXコマンドシート一覧
http://www002.upp.so-net.ne.jp/latex/
TeX数式の利用方法
http://hooktail.maxwell.jp/yybbs/texuse.html
LaTeX 入門
http://mail2.nara-edu.ac.jp/~asait/latex/tex_introduction.htm
数式(TeX)
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/sensei/kumazawa/texindex3.html
ギリシャ文字の読み方とTeXのコマンド
http://www.nyanya.sakura.ne.jp/es/math/greek.html
関連記事:
てふてふ:
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/2edaf550cfb8db85edba4e74a847373b
とね日記(数式の部屋)を開設してみた。
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/eafdc64dcb09ca7865bb324a3572792f
とね@Wikiを開設 (数式入力のために)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c3a8469a14a4a6c80091fb6d92427ee7
ブログで数式を表示させる方法: @WIKIを利用
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ec73b1097a19f12527d1f23cba0432e5
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。




Online LaTeX Equation Editor
http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php
アウトラインが美しく表示されてとてもよい感じだ。
TeXでは半角円記号(欧文だとバックスラッシュ)は頻繁に使う。けれどもgooブログは半角円記号の入力、保存していないので、半角円記号の箇所は「%5C」と置き換えて入力すればよい。(2011年1月25日に追記)
記事中に埋め込む数式は、次の2つのHTMLタグのどちらかの書式で記述する。「~」の箇所が数式のところ。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? ~ />
<img src="http://www.codecogs.com/gif.latex? ~ />
数式の入力と表示例をいくつか紹介しよう。
1)べき乗
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ >
2)文字サイズの指定は解像度を指定することで行う。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?%5C300dpi a^2"/ >
表示サイズをHTMLタグから指定すると表示がぼやけてしまうので注意。
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ width="50" height="50" alt="">
3)数式のインライン表示
数式をインライン表示させるときには<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex?a^2"/ >のように入力する。
数式をインライン表示させるときには
4)行列
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbegin{pmatrix}a_{11} & a_{12} %5C%5C a_{21} & a_{22} %5Cend{pmatrix}"/>
5)ドット付きの行列
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbegin{pmatrix}a_{11} & %5Ccdots & a_{1n}%5C%5C %5Cvdots & %5Cddots & %5Cvdots%5C%5C a_{m1} & %5Ccdots & a_{mn} %5Cend{pmatrix}"/>
6)集合
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbigcup_{i=1}^{n}{X_i}"/>
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cbigcap_{i=1}^{n}{X_i}"/>
7)ベクトル
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Coint %5Cvec{F} %5Ccdot d%5Cvec{s}=0"/>
8)測地線の方程式(一般相対性理論)
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? %5Cfrac{d^{2}x^{%5Clambda}}{dr^{2}}+%5CGamma^{%5Clambda}_{%5Cmu %5Cnu} %5Cfrac{dx^{%5Cmu}}{dr}%5Cfrac{dx^{%5Cnu}}{dr}=0"/>
9)重力場の方程式(一般相対性理論)
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? R^{%5Cmu %5Cnu} - %5Cfrac{1}{2}g^{%5Cmu %5Cnu}R = %5Cfrac{8 %5Cpi G}{c^{4}}T^{%5Cmu %5Cnu}"/>
10)定積分
<img src="http://www.codecogs.com/eq.latex? I = %5Cint _{a} ^{b} f(x)dx"/>
TeXで数式入力するためのリンク集:
即席 TeX 講座(EMANの物理学)
http://eman-physics.net/bbs/tex_kouza.html
LaTeXコマンドシート一覧
http://www002.upp.so-net.ne.jp/latex/
TeX数式の利用方法
http://hooktail.maxwell.jp/yybbs/texuse.html
LaTeX 入門
http://mail2.nara-edu.ac.jp/~asait/latex/tex_introduction.htm
数式(TeX)
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/sensei/kumazawa/texindex3.html
ギリシャ文字の読み方とTeXのコマンド
http://www.nyanya.sakura.ne.jp/es/math/greek.html
関連記事:
てふてふ:
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/2edaf550cfb8db85edba4e74a847373b
とね日記(数式の部屋)を開設してみた。
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/eafdc64dcb09ca7865bb324a3572792f
とね@Wikiを開設 (数式入力のために)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c3a8469a14a4a6c80091fb6d92427ee7
ブログで数式を表示させる方法: @WIKIを利用
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ec73b1097a19f12527d1f23cba0432e5
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。


























お久しぶりです。記事がお役に立ったようで、よかったです。
ブログを拝見させていただきましたが、水素原子の電子雲の動画すばらしいですね。
「物理超入門」のほうも期待しています。がんばってください!
参考にさせていただきました。
ありがとうございます。
一番上でなくてすみません!(笑)
実はこの箇所は自分で登録した順番になっているのです。知名度から言えば大栗先生が一番上のはずなのですけどね。
> 「こんな間違いをするようでは
心配だ」と
> 言われたばかりなのです。
僕もトンデモを書いていることありますよ。とんでもなく知識のある方が読むこともあるのだと思うと、思いつきで記事は書けなくなりますね。(笑)
恐縮至極です。
僕は、かなりの、おっちょこちょいで、
この前もエルミート演算子での実数固有値を実数関数と思い違えて、
「こんな間違いをするようでは心配だ」と
言われたばかりなのです。
トンデモを書こうというつもりは、ないんですが、、、
こちらこそ、宜しくお願いします。
ところでkafukaさんのブログを僕のブログのリンク集に加えさせていただきました。僕のほうの物理の勉強の進度はまだまだこれからですが、今後よろしくお付き合いくださいますようお願いします。m(_ _)_
2)セキュリティ
これは、大丈夫です。
動かすCGIは、本CGIとmemetex.cgi だけで、
これは、学内や研究所内のサーバに置けます。
(memetex.cgiは、GPLライセンスです)
1)アクセスが集中したときのレスポンス
これが問題ですね。
僕は、元々COBOLやC++のプログラマで、
今回は、phpの勉強を兼ねて、このCGIを作ったわけで、
基本的にWebシステムには暗いのです。
高速化には、Webの専門家の手が必要と
思っています。
あと、3)相互排除(排他制御)も気をつけたつもりですが、穴があるかも知れません。
> これって大学とか研究所の掲示板に使えませんでしょうか?
機能の点から言えば十分に使えると思いますよ。2つの点が気になりますけど。
1)アクセスが集中したときのレスポンス
2)セキュリティ:数式とはいえ学内の情報の一部が外部サーバーを経由するのが許されるかどうか。
でも学校っていうのは案外こういうことに無頓着だから、実際上は何も問題おきないと思います。(研究所や企業は別として。)
(今、時々見てるのですが、皆さん見てるのか、かなり遅い ^^;
それから、考えたのですが、これって、
大学とか研究所の掲示板に使えませんでしょうか?
ほとんど、無修正で使えると思います。
gooブログの理系ユーザーにとって朗報だと思います。ありがとうございます!
僕もいくつか試してみて紹介記事を書かせていただきたいですが、よろしいでしょうか?
手こずりましたが、完成しました。
http://blogs.yahoo.co.jp/kafukanoochan/62474900.html
Gooブログは、urldecode()とmb_detect_encoding()の間に、
utf_decode()の追加が必要でした。
(Yahooブログは、単なる勘違い^^;
他に使用可能なのは、、、
・Hatenaブログ 例: http://d.hatena.ne.jp/kafukanoochan/20100118
・cocolog 例: http://kafukanoochan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/
・Biglobe(webry)
です。
他は、要望があれば作ります。
(基本的に上方向互換です。Gooブログで utf_decode()を入れただけ)
morimoto0703のページを読ませていただきました。かなりいいところまで完成しているのですね。さすがです。
> ただ、こんなことをしないといけないのは、
> Gooブログだけのようです。
Orz...
僕もけったいなブログサービスを選んでしまいましたねぇ。(笑)
全角の¥で逃げています。
つまり、全角の¥が来たら、半角の¥に置き換えて、
mimetex.cgi に渡しています。
http://blog.goo.ne.jp/morimoto0703/
ただ、こんなことをしないといけないのは、
Gooブログだけのようです。
gooブログで使えるようになると嬉しいですが、Yahooブログのほうは実現がもっと難しいのですね。
「明日中に」とお書きになっていらっしゃいますが、急いでしていだく必要はございません。でも、こういうプログラミング的な作業って一気に集中してやりたくなってしまうものなのですよね。僕も元プログラマーなので同じように思います。
ありがとうございます。
で、「全角数式のTeX表示のWebサービス」なんですが、
使用可能なは、現在のところ、
・Hatenaブログ 例: http://d.hatena.ne.jp/kafukanoochan/20100118
・cocolog 例: http://kafukanoochan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/
・Biglobe(webry)
です。
・Gooブログ は、明日中に何とかします。(CGIのEncodeが特殊なのです)
(Yahooブログは、再挑戦中です。実際可能かどうか不明)
これは便利なものをお作りになられましたね。Web上に置いたテキストファイルからの入力もできるので数式をメンテナンスしやすそうです。
いろいろな式で試してみたいと思っています。
僕はkafukaさんよりも少し年下なのだと思いますが、勉強のほうも頑張っていきましょう。kafukaさんが1年前から学校で物理学を勉強を始められたのを知ったとき、なかなかできないことだなと(僭越ながら)感心していました。
「全角数式のTeX表示のWebサービス」です。つまり、
全角の∫とか∂を、そのまま書いた数式をTeX表示するわけです。
数式エディタを使う場合、
ブログ本文の作成と数式エディタを往ったり来たりして、貼り付けせねばならず、その毎に、思考が中断されます。
で、イラがきて、partialとか、直接 打ちたくなるわけです。
だったら、初めから∂と打てればいい、というわけです。
もちろん、全角の∫とか∂を使わず、LaTeX文法を直接書くこともできます。(mimetex.cgi互換)
説明は、
http://blogs.yahoo.co.jp/kafukanoochan/62474900.html
にあります。
尚、以前fkさんに使って頂いていました。
また、全充さんに評価して頂きました。
http://blogs.yahoo.co.jp/iwata1sei/22860190.html
いえいえ、どういたしまして。僕もブログで数式を使いたいことがあるので自分のために調べたという背景もあります。
> カジョリの『初等数学史』
現物は見たことがありませんが、500ページ近くもある分厚い本なのですね。
三角関数表や対数関数表という言葉を久しぶりに目にして、中学時代にポケットサイズの三角関数表、対数表の本を持っていたことを思い出しました。どこの出版社から出ていたのかちょっと思い出せませんが。
高校1年になってはじめて関数電卓を親に買ってもらい肌身離さず持っていたことを覚えています。関数の精度は確か6桁だったと思います。
色々実験して頂きありがとうございました。インラインで数式を入れる方法までレポートして頂けたとは。
三角関数表を使って乗除する方法はカジョリの『初等数学史』に記載されているようです。調べてみます。