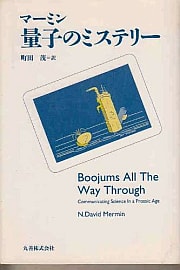
「マーミン量子のミステリー:デヴィッド マーミン」
内容紹介:
著者のマーミン博士は、科学をいかに分かりやすい文章・スタイルで説き明かすかに強い関心をもつ世界的な物理学者。本書では、ミクロ世界の自然が決まった“部品”からできているのではなく、きわめて奇妙な確率的存在であること、そしてこの世界では、観測するという行為自体が対象に影響を与えることになり、観測そのものが原理的に不可能であること、などを平易・簡潔に解説。量子物理学と聞くと何やら複雑な数式やらを想像するが、本書はそんな心配は無用。科学をわかり易く説明することに腐心してきた学者による量子論への招待。
1994年5月刊行、160ページ。
著者について:
デヴィッド・マーミン(ウィキペディア、ホームページ)
コーネル大学名誉教授(物理学)。米国物理学会のリリエンフェルト賞および米国物理教育学会のクロプステッグ賞を受賞。米国科学アカデミー、米国芸術科学アカデミーの会員。この数十年の間に、量子論の基礎的な問題に関する多くの著作を執筆しており、科学の啓蒙に関する明瞭さと機知には定評がある。
訳者について:
町田茂(まちだ しげる)
1926生まれ。京都大学名誉教授。理学博士。1949年東京大学卒業。広島大学講師,立教大学助教授,同教授を経て京都大学教授,現在京都大学名誉教授。主な研究分野は素粒子論,量子力学の基礎。著書に『現代科学と物質概念』(共著,青木書店),『量子論の新段階』(丸善),『基礎量子力学』(丸善),『量子力学の反乱』(学研)がある。
理数系書籍のレビュー記事は本書で356冊目。
本書は2016年10月に紹介した「マーミン相対論―新しい発想で学ぶ: デヴィッド マーミン」の姉妹本である。
翻訳の元になった原書はこちら。1990年に出版された。目次を見ると26章から構成されており、日本語版にはその半分が含まれている。
「Boojums All the Way through: Communicating Science in a Prosaic Age: N. David Mermin」(Kindle版)

本書を読んだ理由は、物性物理学の権威でもあり、一般向けの科学教養書の世界でも定評があるマーミン博士が量子論に関して、どのような知見を提供してくれているかという一点に尽きる。「マーミン相対論―新しい発想で学ぶ: デヴィッド マーミン」に感銘を受けただけに、本書も期待して読んだ。
160ページという薄い本で、量子論の中でもテーマを「量子論の物理的解釈」、「EPR論文」、「ベルの定理」に絞って解説している。章立ては次のとおり。
第1章:量子のミステリー
第2章:ひいきチームの加勢ができる?―アインシュタイン‐ポドルスキー‐ローゼンの実験形而上学
第3章:気味の悪い遠隔作用―量子論の不思議
第4章:青天の霹靂―アインシュタイン‐ポドルスキー‐ローゼンのパラドックス
第5章:ニールス・ボーアの哲学的著作
第6章:量子論の醜い混乱
第7章:夢見が悪いのはなぜ?
結論から言うと期待は外れてしまった。非常にわかりにくい。その理由は次のようなことだ。
- 長い文章が多く、読み解くのが非常に困難。
- 「~でないとは、必ずしも~ない。」のような二重否定の文章が次々に続くので、何を言いたいのかわからない箇所が多い。
- 同じ事がらを、何度も繰り返して解説しているので、冗長に見えてしまう。
本書の原書が書かれたのは1990年。アスペの実験(1982年)の後に書かれている。しかし、EPR論文で示される「奇妙な遠隔作用=量子エンタングルメント」が実験で確認されたのはもっと後で、量子テレポーテーションの実験が成功したのは1998年のことである。(参考記事)であるから、本書執筆の段階では依然として遠隔作用は奇妙なものだった。
- 1935年:EPR論文
- 1964年:ベルの定理(ベルの不等式)
- 1982年:アスペの実験(量子力学の正当性が実験により確認された。)
- 1990年:本書の執筆
- 1998年:量子テレポーテーションの実験成功(遠隔作用が実験により確認された。)
そして現代では量子コンピュータも個人で実験できるようになり(参考記事)、量子の「状態の重ね合わせ」が現実のものであることを私たちは知っている。
本書でマーミン博士はベルの定理を簡略化した思考実験を提案し、そのための実験装置を紹介、解説している。光子をひとつずつ発射して状態を観測する次のような装置だ。

実験は膨大な回数行い、結果は確率として判断、考察することになる。

偏光板を用いた実験装置。(量子消しゴム実験に相当)

ただし、量子消しゴム実験は本質的には古典的な現象であるので注意いただきたい。堀田先生はこの点に関して次の記事をお書きになっている。
「量子的」と呼ばれつつ、古典的な本質をもつ現象
http://mhotta.hatenablog.com/entry/2014/05/17/094449
マーミン博士は量子論を理解する物理学者として第3世代だと、ご自身でお書きになっている。量子論を創始したボーアやハイゼンベルク、アインシュタインなど第1世代の物理学者にとって、それは確かに奇妙な理論だった。現在発売されている「Newton(ニュートン) 2018年3月号」でも「シュレディンガーの猫」の問題が取り上げられ、4通りの解釈方法が紹介されている。(参考記事:「「シュレーディンガーの猫」のパラドックスが解けた!:古澤明」
「量子のミステリー」を知りたければ、量子力学発展史を学ぶべきであり、そのためには本書よりも次の本を読むほうがよいと思った。
量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突:マンジット・クマール
https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/19d16104cb20787443c84b8692b0424b
アインシュタインの反乱と量子コンピュータ: 佐藤文隆
https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9fa38724ad6881636cdff2903ee14a5b
このようなわけで、本書は強くお勧めできる本ではないというのが今日の結論だ。
関連記事:
マーミン相対論―新しい発想で学ぶ: デヴィッド マーミン
https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/6e47253b0622e867f57fb15b88d18149
ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。




「マーミン量子のミステリー:デヴィッド マーミン」

訳者まえがき
日本語版への序
第1章:量子のミステリー
第2章:ひいきチームの加勢ができる?―アインシュタイン‐ポドルスキー‐ローゼンの実験形而上学
第3章:気味の悪い遠隔作用―量子論の不思議
第4章:青天の霹靂―アインシュタイン‐ポドルスキー‐ローゼンのパラドックス
第5章:ニールス・ボーアの哲学的著作
第6章:量子論の醜い混乱
第7章:夢見が悪いのはなぜ?
注および文献





















マーミン先生のご専門にも近いし、町田先生の訳だし、多分分かり易いと思っていたのですが、そうでもないようですね。
そういう意味で、私にとってこの記事の内容は有意義でした。ありがとうございました。
この記事はきっとT_NAKAさんに読んでいただけると思って書きました。
本書はとても読みにくく、詳しく解説をすることができませんでした。実験装置の図だけ載せたのはそのためです。
量子エンタングルメントが当たり前な時代になったので、この本で議論していることの意義も、相対的に下がってしまいました。