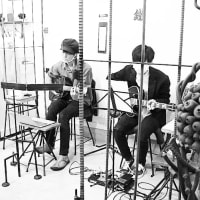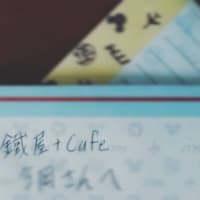鉄芸。
生きる為に無くても良いものであり、
生きていく為には
無くてはならないものでもある。
鉄のある暮らしと
鉄でつくる暮らし。
在るものを使って暮らすことと
つくったものを使って暮らすこと。
色々。
生きることは食べること
暮らすことはつくること。
沖縄の職人さんが
云っていた言葉。
戦時戦後、
物資の無い時代を生き抜いた者の
深く尊いお言葉は、
作品制作の原点である。
作品制作時、
必ず、楽曲をひとつ決める。
楽曲が先に決まって、
作品制作テーマが決まることもある。
その時に、
生きる、暮らすを
強く感じる沖縄の島唄を
選ぶことが多い。
民謡は労働歌や
暮らしの中の出来事を唄ってることが
多いからだろうか?
制作には合う。
鉄は熱いうちに打てと
云われるだけあって
せっかちになる鉄制作。
落ち着かせてくれる独特な音階が
奏でるリズム、テンポも
制作には合う。
沖縄民謡に欠かせない三線。
戦後物資不足の中でも
食料缶、パラシュートの紐、
野設ベットの骨組などを遣い、
三線をつくった
沖縄の人々の想い。
それが、
カンカラ三線である。
すべてが、
生きること、暮らすこと。
制作の原点は、
ここにある。
鉄造形家/鉄彫刻家
イマオカヒデノリ