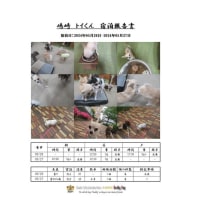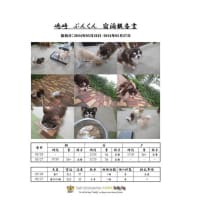Health food for dogs
dog food
ドッグフードのTVコマーシャルで、「原材料」や「添加物」について詳しく表現しているのを見たことがありますか?
私は残念ながら一度も見たことがありません。
しっぽを振ってがつがつ食べてるシーンや、どこそこの誰かが推奨してるとか、年齢に合わせた栄養素が入っているとかばかりです。
そのドッグフードの良い「イメージ」だけを表現していますね。
どこにも「安全」とか「安心」できる要素の表現が見当たらないはずです。
間違ったドッグフード選びの多くは、
・昔から知っているから
・テレビで見たことがあるから
・有名だから
などの『先入観』だけで選ぶ行為です。
「大丈夫だろう。」という安心感があるので、ドッグフードのパッケージの裏側をちゃんと読まない傾向にあります。
また、ちゃんと読んだとしても、どこでも見かける量販ドッグフードの成分表には真実がほとんど表示されていません。
『栄養バランスが良さそう』であり、『美味しそう』に見えるように工夫はしてあますが、あくまで工夫しているだけです。
本当の中身をメーカー(企業)は伝えません。
例えば、『洗う成分の100%が天然成分』といようなボディーソープがありますが、洗う成分以外は界面活性剤や安定剤・保存料・着色料などの化学薬品が含まれています。
また、スポーツドリンクなどの清涼飲料水も、いろいろなビタミンやアミノ酸などが体に有効であるとコマーシャルでは言っていますが、人工的に造られた合成ビタミンなどは体には吸収されず、逆に結石などをつくる原因になることもあるそうです。
清涼飲料水をペットボトル1本飲みきると、ガムシロップを小ジョッキに一杯飲んだのと同じ量の糖分を摂取することになるのです。(製品による)
某清涼飲料水メーカーの開発者は、自分とその家族には自社の清涼飲料水を一滴たりとも飲ませない。
という実話さえあります。
このようにテレビコマーシャルなどでは真実の半分以下の情報しか知り得ることはできないのです。
美味しそうなイメージ・体に良さそうなイメージ・天然成分っぽいイメージ。
全て『イメージ』だけで、真相は消費者には伝わりません。
調べると、全国放送で有名タレントやタレント犬を用意して、毎日何回も放送すると数千万円~数億円の宣伝費だそうです。
そんなあいまいな「イメージ」にコストをかけるなら、もっといいフードを開発するコストへ回してもらいたいものです。
仮に5キロ300円のドッグフードならば、1キロあたり60円となります。
1キロ60円の中に、宣伝広告費、製造開発費、商品管理費、人件費、運賃、仲介業者手数料、販売店利益が含まれているのです。
それでいて、メーカーに利益が発生するわけですから、ドッグフードの原材料などタダ同然で調達する必要があるのです。
昔から流通しているドッグフード・・・
みんなが知ってるドッグフード・・・
ゴミでもかき集めてこない限り、あの価格は実現不可能です。
全くあてにならないパッケージの『表示』!原材料は5%のみ?
補足ですが、ペットフード公正取引協議会では、
引用:
『事業者は「ビーフ」・「チキン」など特定の原材料をペットフードの内容量の5%以上使用している場合でなければ、該当のペットフード商品名、絵、写真、説明文に当該当原材料を使用している旨の表示をしてはならない』
「ペットフード公正取引協議会/ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則解説書(第2版)/特定事項の表示基準・第6条」
と定められています。
これだけを見ると疑問点は無いように見えますね。
しかし、逆に言うと「5%だけ入っていれば、原材料として表示しても良いですよ~」と言っているのと同じ事に気づきましたか?
ですから95%トウモロコシなどの穀物類でも、たった5%ビーフを使っていればそのフードは「良質なビーフで出来ています!」と表示して販売することが可能かもしれません。
ドッグフードの原料の20%は闇に葬られている!!
使用する原材料の80%だけを表示すればよいので、残りの20%はどんな物を使用していても表示する義務すら無いのです。
これを悪用しようと思えば、80%天然成分で出来ているけど、残りの20%が毒物で出来ているドッグフードを作り、「天然素材・保存料無添加」として販売する事だって可能かもしれません。
一体何のための基準なのか、さっぱり分かりません.....
この「ペットフード公正取引協議会」というのはフードメーカー42社で構成されています。(2006年6月現在)
ペットフード工業会が発行している「ペットフードハンドブック」には、「ペットフードハンドブック」
引用:
『ペットフード工業会は、ペットのための専用の食事であるペットフードの安全性・品質の向上に努め、ペット飼育を通じて得られる心のゆとりや多くのペットオーナーの方が願う健やかなペットライフの実現に貢献できるよう、様々な活動に携わり、たゆまぬ努力を続けて行きます。』
このようなすばらしい表現が用いられています。
しかし、こんな意見もあります。
引用:
『ペットフード公正取引協議会のガイドラインというのは、業界団体の自主規制のようなものだから、お互いに損になるとわかっていることを取り決めるはずがない。
まずは、自分だったらどうするか立場を変えて考えてみれば分かることだろう。』
ペットの命を守る『著・坂本徹也』(ハート出版)より引用
という見方もあるようです。
そう言われれば、「そりゃそうか」と思います。
だって、たった5%入っているだけで「原材料」として認めちゃうし、全体の80%だけを表示すればそれでいいんですからね。
ペットフードハンドブックに記載されている、「たゆまぬ努力」ってどんな努力なんでしょう?
フードの○○ミールという表示について
『ミール=ごちゃ混ぜ』というイメージがありますが、ちょっと違います。
正確には『完全に挽き粉状にする』という意味です。
ミートミール(肉粉)やミートボーンミール(肉骨粉)などの評判があまりにも悪いので、「ミール」という文字があるだけで何かものすごく粗悪な印象を受けてしまい、いつの間にか「ミール=危険」という印象が強くなったようです。
何をミールしたかで、危険・安全が分かれます。
食用レベル、もしくはそれ以上の高い品質部位をミールして原材料として使用するのなら全く問題はありません。
それどころか優れたドッグフードと言えるでしょう。
■ミールは安全?危険?
「○○ミール」という原料が危険か安全か?と考えても収拾がつきません。
安全な○○ミールもあれば、ひどく危険な○○ミールも存在します。
今は飼い主がそれを見抜かなければならない時代になって来ています。
ドッグフードのパッケージを見比べるだけではなく、フードメーカーのポリシーやプライドを見比べる必要があると思います。
全ての原材料が高品質であるという証明を明確に発表しているフードメーカーが言う、「○○ミール」は信用しても良いでしょう。
しかし、原材料についてとくに詳しい表示も無いようなドッグフードに使用されている「○○ミール」は信用しない方が良いでしょう。
フード成分表示の疑問?
「前から不思議に思っていたんだけど、<粗蛋白質><粗繊維>と書いてあるのは、普通の蛋白質や食物繊維とは違うの?」
確かに人間用の食品だと、成分表示に<粗蛋白質><粗脂肪><粗繊維>など「粗」のついたものはありません。
しかしながら、フードの成分表示には頭についています。
粗は「粗悪」「粗雑」「粗末」など、悪いイメージの方がいるかもしれませんね。
検索してみると、
「粗悪な原料を使っているから<粗○○>」これは間違い。
「純粋な成分以外のものも含まれているから<粗>がついている」これが正しいのです。
「・・・やっぱりフードって無責任なんだ!!」と考えた方は大きな誤解をしています。
<粗>がついているフードの成分表示は無責任な表示ではなく、「純粋な蛋白質以外も含んでいる」という意味で、むしろ、人用の食品より正確な表示を行っているというのが正しい理解なのです。
食品の成分表示が<粗>を省略しているということです。
単に、食品とフードの表示方法の違いです。
ただし・・・「粗繊維」だけは単なる表示方法の違いではありません。
フード成分表示にある「粗繊維」を、いわゆる「食物繊維」のことだと思っている方が多いのではないかと?
「粗繊維」と「食物繊維」は測定対象も測定方法も異なり、関係としては、「粗繊維」=「食物繊維の一部」に過ぎません。
繊維質は、愛犬の食事を見極める際の重要なポイントのひとつです。
■園長のひとりごと
園長は犬幼稚園に来られた飼主さんと愛犬の食事に関してお話をします。
原材料や原産国を選択基準にされている方は多いのですが?
手作りの方も?犬種別も?
価値観に個人差があるのは十分理解できます。
しかし、正確な情報をお持ちの方は少ないようです。
食べ物の選択は愛犬の健康に重大な影響を与えると思います。
勉強してくださいね。
フード成分表示の疑問「粗○○」とは?
粗蛋白質量○%と、粗脂肪、粗繊維、粗灰分とは?
食品の蛋白質を定量するには、食品中の窒素含量を測定し、その値に、6.25(たんぱく換算係数)を乗じて求めます。
この値を「粗蛋白質」といいます。
蛋白質の正確な量の測定は、その構造が明らかにされているものだけが可能で、食品では正確な測定は難しいので、このような換算値を用います。
粗蛋白質と真の蛋白質量の違いは、
・蛋白質以外の窒素分で、アミン、核酸、硝酸塩などを含んでいる。
・蛋白質の種類により含まれる割合が16%(100÷6.25)とは限らないということ。
蛋白質以外でも、食品の成分を測定する際に直接目的とする成分を分析することは難しいので、その成分のおおよその目安となる物質を測定することにより、求めます。
直接その成分を分析している訳ではないので、「粗○○」といいます。
粗脂肪、粗繊維、粗灰分の測定方法は、それぞれ、
1.粗脂肪は、エーテル抽出法、酸加水分解法、クロロホルム・メタノール抽出法などがあり、食品により使い分けられます。
2.粗繊維は、1.25%の熱希硫酸と1.25%の熱水酸化ナトリウムで抽出し、残ったものの量を測定する。
3.粗灰分は、550~600℃で燃焼させた残ったものの量を測定する。
葉物野菜に多く含まれる硝酸性窒素、お茶やコーヒーのカフェインといった窒素化合物なども「蛋白質」として算出されてしまいます。
ただ、多くの加工食品では蛋白質以外の窒素化合物の含有量は少ないため、窒素量を元に算出された数値が蛋白質として表示されています。
ちなみに、「中国産メラミン混入ドッグフード、粉ミルク事件」も、窒素化合物であるメラミン(メラミン樹脂(プラスチック)の原料)の特性を悪用して蛋白質含量を多く見せかけた事件でした。
フード成分表示の疑問「粗繊維」とは?
「粗繊維」とは、どのようなものですか。
「粗繊維」とは、飼料の一般成分の一つです。
検査は、飼料を弱酸(1.25%H2SO4)と弱アルカリ(1.25%NaOH)で順次煮沸した後、アルコール及びエーテルで順次洗浄した残渣(ざんさ)から、その灰分を差引いたものです。
粗繊維には、セルロースのほかにリグニン、ペントサン、キチンなどの一部が混入しています。
粗繊維の含量と飼料の栄養価とは密接な関係があり、一般に粗繊維の多いものほど栄養価は低くなっています。
参考資料
「新編 飼料ハンドブック 第二版」(社)日本科学飼料協会