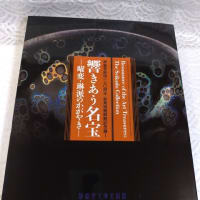公的な職制ではありませんが、武家には『取次衆』
といわれる人々がいます。現代で言えば『渉外担当』
にあたり、自家と他家の間の交渉を担当します。よく
テレビで出てくるような「有力武将同士がたびたび
大広間で直接会見する」といったことは当時ありえ
ないことであって、全んどの場合互いの『取次衆』が
主に成り代わって段取りを進めていきます。たとえば
「会社同士のビッグプロジェクトを進めるとき、実質的
にはプロジェクトリーダーが段取りを進め、社長が出て
くるのはキーポイントとなるときだけ」といえばわかり
やすいでしょうか?
【源平盛衰記の時代】
*平大相国清盛の家では源大夫判官季貞・平越中次郎
兵衛盛嗣らが『取次衆』を務めていました
*清盛の嫡男である小松内大臣重盛の家では平主馬
判官盛国が『取次衆』を務めていました
*源頼朝の家では安達藤九郎盛長らが受け持っていま
した
【信長公記の時代】
*織田家では、信秀の時は平手中務丞政秀が『取次衆』
*信長の時は丹羽五郎左衛門長秀が受け持ちました
*徳川家では家康のとき、酒井忠次・石川数正および
大久保一門が『取次衆』に当たるかもしれません
現代と戦国時代では大きく違う点があります。現代の
渉外担当が決められた月給で動いているのと比べ、
戦国時代の『取次衆』は仲介するたび「引出物」
(=女性物の小袖、小刀、金銀など)を受け取って
いたので、莫大な手数料を稼ぐことができたようです。
成立させれば主からの褒美も出るので『往復ビンタ』
でもうかります!ただ扱う案件が、身方同士・身方対敵・
対朝廷・対幕府・対宗教などと多岐にわたるので、軍事力・
交渉力・知性と教養・人間の魅力・統率力・財力などの
要求される難しい業務です。そのうえで主君に忠誠を誓う
という・・・難しそう・・・

にほんブログ村
といわれる人々がいます。現代で言えば『渉外担当』
にあたり、自家と他家の間の交渉を担当します。よく
テレビで出てくるような「有力武将同士がたびたび
大広間で直接会見する」といったことは当時ありえ
ないことであって、全んどの場合互いの『取次衆』が
主に成り代わって段取りを進めていきます。たとえば
「会社同士のビッグプロジェクトを進めるとき、実質的
にはプロジェクトリーダーが段取りを進め、社長が出て
くるのはキーポイントとなるときだけ」といえばわかり
やすいでしょうか?
【源平盛衰記の時代】
*平大相国清盛の家では源大夫判官季貞・平越中次郎
兵衛盛嗣らが『取次衆』を務めていました
*清盛の嫡男である小松内大臣重盛の家では平主馬
判官盛国が『取次衆』を務めていました
*源頼朝の家では安達藤九郎盛長らが受け持っていま
した
【信長公記の時代】
*織田家では、信秀の時は平手中務丞政秀が『取次衆』
*信長の時は丹羽五郎左衛門長秀が受け持ちました
*徳川家では家康のとき、酒井忠次・石川数正および
大久保一門が『取次衆』に当たるかもしれません
現代と戦国時代では大きく違う点があります。現代の
渉外担当が決められた月給で動いているのと比べ、
戦国時代の『取次衆』は仲介するたび「引出物」
(=女性物の小袖、小刀、金銀など)を受け取って
いたので、莫大な手数料を稼ぐことができたようです。
成立させれば主からの褒美も出るので『往復ビンタ』
でもうかります!ただ扱う案件が、身方同士・身方対敵・
対朝廷・対幕府・対宗教などと多岐にわたるので、軍事力・
交渉力・知性と教養・人間の魅力・統率力・財力などの
要求される難しい業務です。そのうえで主君に忠誠を誓う
という・・・難しそう・・・
にほんブログ村