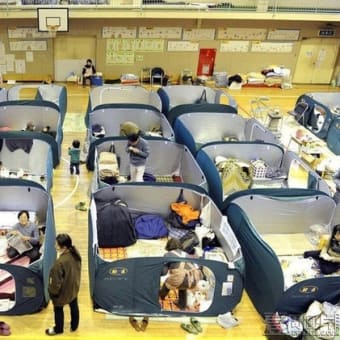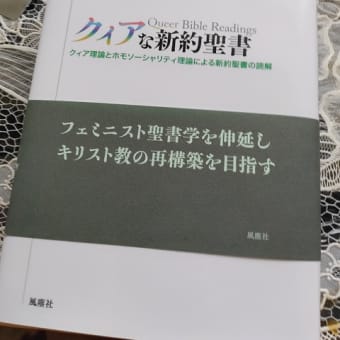今日調布の文化会館たづくりで映画を見た。
街中で定食を食べて、16時ごろ、ふらっと入ったら、安部公房の催しがやっていた。で、覗いたら、映画をやるという。もう60年以上前の安部公房脚本「おとし穴」であった。
多分難解な映画と思われるのが関の山。とはいえ、やっぱり夢のような雰囲気で十分見応えというか、見た後に夢を見たように引きつけられる、そんな感じがした。
三井三池炭鉱事件がモチーフらしい。それを知らないとしても、僕自身はその内容を見て、当時の炭鉱の労働が背景にあることは理解できた。
2つだけ考えたことを。
1つは、映画における表現方法。殺人事件であるが、殺人された人物が死者のまま生者とは接することができないで、この世を観察している。生者の世界という現実。そして、死者から見た世界という現実。この生者という現実と死者という虚構が重ね合わさることで、人間を問うような構成が面白かった。
2つ目には、炭鉱の労働組合の争い、そしてその争いを引き起こす会社の謀略、この経営者と労働者の分断である。こちらは非常に社会性に富んでいる。
時代背景は労働運動が盛んな時代なのであろうが、そこに経営者の謀略で、労働者の団結が崩され、疑心暗鬼が殺人にまでなってしまう。
これは今の時代を逆説的に反映することになる。新自由主義によって、労働者の地位は下がっている。労働組合の親玉である連合をみれば、労働者側ではなく、経営者側についている。
経営者側が消費税を上げ、非正規雇用の割合を増やす。経営者側が行なっているのは、正規雇用と非正規雇用の分断であろう。それがこの映画のころ、60年前の頃から、この分断の手法は”洗練”されてしまっている。
今じゃこの社会システムをデフォルトとしてしまう社会意識が支配的であるから、労働運動自体が力を持つとさえ考えられなくなってしまっている。
まだ色々考えることはあるけれど、こんなところで。