多く、中旬から下旬は曇りや雨の日が多かった。
その中の全天日射量について、自宅で計測したデータと気象台のデータをグラフをで比較してみた。その結果殆んど差は無く近似値であったので、我が家の日射計も使えることが判明した。

また、全天日射量と日射時間のグラフも作成し、日射時間と全天日射量の関係をみると
日射時間が「ゼロ」でも2~9MJ/平米の日射量があることが解ります。

久しぶりにアマチュア無線を聞いて見ようと思い立ち「マルツパーツ」で
販売している、7MHz帯のSSB/CW受信機製作キットを購入し組み立ててみました。
本キットには、組み立ての詳細説明と調整方法が詳しく記入されたマニュアルが
ついているので、比較的簡単に組み立てることが出来ました。
今回は調整のための簡易信号発生器製作キットも合わせて購入し、完成後の
受信帯域の調整をおこないました。
組み立て前の基板
組み立ては基板上の背の低い抵抗から初めて、ジャンパー線、コンデンサー、
トランジスタ、ICソケットと進みます。
マニュアルには、それぞれ個々の部品にチェックボックス設定されていて1個づつ
確認しながら進めることができるので、間違いが少なく組み立てることができます。
次に、ボリューム、「FCZコイル」を取り付け、基板に取り付ける部品は完了です。
半田付けをチェックした後、基板周辺の部品への配線を済ませ、ケースに組み込みます。
部品取り付け VR等取付け 基板周辺の配線 ケースに組込み完成




各部電圧のチェック
基板内の6箇所について電圧チェックを行います。
組み立て時と同じようにチェックボックスがあり、電圧の許容範囲が表示されているので
その範囲内にあるかどうか、テェックを行います。
7MHz簡易基準信号発生器の組み立て
この発信機は「MRX-7D-FK」の調整に使用する 5.88MHzから8.3MHzまでの範囲を出力する
発信機です。
リニアテクノロジ社製のLTC99を使い半固定抵抗器で周波数を可変します。
非常に簡単な回路でブレッドボードに組み込むようになっています。
部品一式 組み立て 出力 周波数測定 出力 波形
日照時間は気象庁発表のデータで132.2時間で平年比107%でしたが、前年同月よりは少なく、発電量も昨年に比べて下がっております。
消費電力は残暑の関係かと思いますが、昨年より若干増加しております。


全天候日射量は我が家の屋根に取り付けている日射計のデータです。
一時期調子が悪くて使っておりませんでしたが、データが計測できるようになったので使ってみました。気象台のデータが発表されたら比較してみたいと思います。
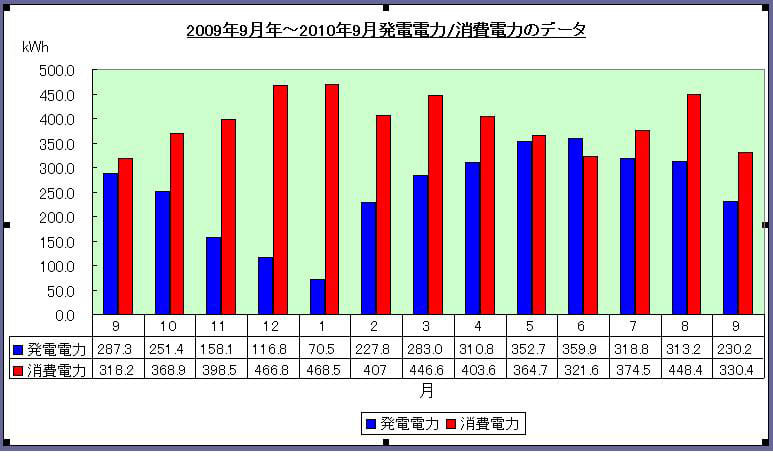
太陽電池の日毎の最高温度と最低温度をグラフにしてみました。
日にちが進むほど温度が下がっていくのがわかります。































