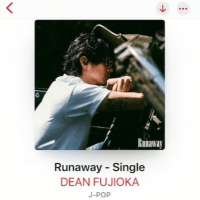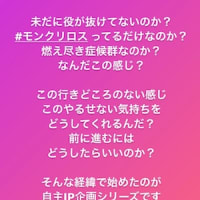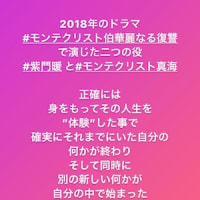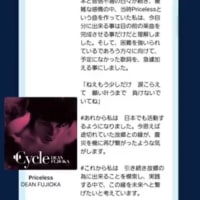重複回避また記録として、訪問したら記録するページ(3)。
記録優先!随時追記あり。
京都は★、奈良は●、その他は■
<2011年>
1月
★上賀茂神社・護王神社・八坂神社(ブログに)
★光雲寺
★両足院(秘仏 毘沙門天)
※第45回京の冬の旅 非公開文化財特別公開
★金戒光明寺
★東北院
2月
★玉林院
※第45回京の冬の旅 非公開文化財特別公開
●興福寺国宝館
3月
★真如堂(大涅槃図)
★東山祈りの灯り
4月
■祇園神社・湊川上温泉・雪見御所の跡・荒田八幡神社・
宝地院
★養源院・円山公園
★松尾大社
★平清盛公西八条殿跡
5月
■近江八幡
■安土(沙沙貴神社、安土城跡、安土城天主 信長の館ほか)
★葵祭(下鴨神社、上賀茂神社)
●霊山寺(大弁財天、十二神将ほか)
※秋の公開時には薬師三尊像ほか仏像が内陣で見られる。
6月
★赤山禅院(屋根の上のお猿さん確認)
■満願寺(川西市 清和源氏ゆかりの寺 坂田金時の墓)
★頼光寺(川西市 清和源氏ゆかりの寺 紫陽花が見頃だった)
7月
★祇園祭
■大阪天満宮
■住吉大社
8月
★並河靖之七宝記念館・大寧軒
■伊勢神宮 (ブログに)
豊受大神宮 下宮(+ 別宮 多賀宮・土宮・風宮)
皇大神宮 内宮(+ 別宮 荒祭宮・風日祈宮)
別宮 月読宮
■二見浦(二見興玉神社、夫婦岩ほか)
●秋篠寺(伎芸天立像。ほの暗い部屋で光の加減かお顔だけ
が黒く見える。左に小首を傾げ、優しく微笑んでおられるの
が本当にありがたくただじっと見ていられればいいと思う。)
●春日大社中元万燈籠、東大寺万灯供養、氷室神社
★五山送り火

★宝積寺(十一面観音菩薩立像・三重塔ほか)
★大山崎山荘美術館(企画展「かんさいいすなう」では作家
さんが製作した椅子に実際にすわることができて楽しい♪)
9月
★宝菩提院 願徳寺(如意輪観世音菩薩半跏像)
国宝の「如意輪観世音菩薩半跏像」に再びお目もじが叶った。
ほぼ20年ぶり。お顔が日本ぽくなかったと記憶していたが、
やはりとても美しく間近で拝顔できた。ご住職がお話してく
ださる時にいったん部屋を暗くしてお顔にスポットライトを
当てられるので、額の石がいっそう光ってみえる。写真と実物
とで目の大きさが違って見えるのも不思議。二重まぶたなので
角度によって照明によって変わって見えるのだろうか。
★勝持寺(花の寺)
■葛井寺(千手千眼観世音菩薩座像)

毎月18日に開扉される千手千眼観世音菩薩さま。左に501本、
右に500本の小さな手がビッシリ。さらに持物を持つ大きな
手が40本。手を合わせた真手が2本。すべての手には眼が。
何人をも見逃さず、聞き逃さず、あらゆる手段で救ってくだ
さるという。「なにがなんでも救うたるで!」というお心が
ありがたいやら申し訳ないやら。
■辛国神社
■道明寺(十一面観世音菩薩像)・道明寺天満宮
毎月18日・25日に拝顔できるご本尊で国宝の十一面観音さま
は菅原道真公が手ずから彫ったもの。高さ約90cm。これま
た優雅なお顔。お香や線香の煙により黒くなったとの説明あり。
その試し彫り約60cmの仏像は「こころみの観音様」と呼ば
れご本尊の不在時に拝観できるそうだ。
●当麻寺


<本堂>中将姫が蓮の糸で織った當麻曼荼羅を本尊として祀る。
国宝の厨子、須弥壇などみどころ多し。
<金堂>大きな弥勒仏坐像(白鳳時代・国宝)、十王のような
顔で顎髭がある四天王立像(多聞天以外は白鳳時代・重文)等。
<講堂>ご本尊は丈六の阿弥陀如来座像(重文)。他に妙幢菩
薩(重文)、地蔵菩薩(重文)など。講堂の裏に現存する日本
最古の石灯籠があり、元々はこちらが寺の正面玄関だったそう。
<東塔・西塔>国宝の双塔が美しい。
●傘堂

★同聚院(十万不動明王座像)
★霊雲院(文殊菩薩座像←上半分が見えない、九山八海の庭
★京都府京都文化博物館「帰ってきた江戸絵画 ニューオー
リンズ ギッター・コレクション展」与謝蕪村や池大雅、
伊藤若冲、俵屋宗達、酒井抱一ほか
水墨画が多かった。全体にボリュームが少ないのが残念。
若冲は6点ほどで寒山拾得図がよかった。
●長岳寺
山の辺の道、古墳群
●檜原神社
●大神神社
10月
★神護寺(国宝 五大虚空蔵菩薩坐像、国宝 薬師如来立像ほか)
多宝塔に安置された五大虚空蔵菩薩坐像は10月の第2土日
に特別公開。向かって右から緑(宝光)、赤(蓮華)、白(法界)、
黒(業用)、黄色(金剛)の順に5体並んで壮観。筒型の宝冠を
かぶりお顔は丸く優しい目をしておられる。季節は秋だけ
ど春の匂いがする笑みだった。金堂の薬師如来さまのどっ
しりふくよかな姿に引きつけられる。ただくっきりした小
鼻も突き突き出た口も遠くからしか眺められない。日光・
月光菩薩、十二神将、四天王、すべて一堂に見られるのも
うれしい!
★西明寺
★高山寺
高雄は紅葉には早過ぎて観光客が少なく、ゆっくりできた。
数回来ているのに五大虚空蔵菩薩を観たのは初めてだった。
■浄土寺(兵庫県小野市)

行ってきました、憧れの浄土寺へ。お堂に入っていきなり
国宝の阿弥陀三尊像とご対面。大きゅうござりまする。
三体の像を、正面遠くから立ったまま、近寄って正座して、
横から、斜めから、真後ろから、反対回りに歩いて、と
散々眺める。円形の須弥壇がモダンな雰囲気。阿弥陀如来、
勢至菩薩、観世音菩薩の立体来迎図は後ろに雲の尻尾が立っ
ており、まさにいま雲に乗って到着した感じ。重源上人の
示す浄土世界を形にしたのは快慶。
蔀戸の向こうから西日が差し込み、それが床板に反射し、
阿弥陀三尊像が赤く染まって見えるの絶好のタイミングは
7月下旬~8月上旬の午後3時半~5時半頃とのこと。
●般若寺(コスモス寺、白鳳秘仏・阿弥陀如立像)

●奈良豆比古神社

●樹齢1300年以上の楠

●転外門、北山十八間戸、東大寺境内散歩
11月
●十輪院(元興寺の塔頭、本尊は石仏龕)
奈良・十輪院の地蔵菩薩様は平安時代に造られた優し
いお顔の石仏。外にあるお地蔵様を拝むために、屋根
付きの礼堂を建てたのは鎌倉時代で、その後お地蔵様
を厨子で囲って石仏龕(せきぶつがん)とし、最後に
その石仏龕に屋根をつけたそうだ。
中央の地蔵菩薩の両側には釈迦如来、弥勒菩薩が。
石仏龕をよく見ると一番外は仁王門になっている。内
側には聖観音、不動明王、十王、四天王などが描かれ、
部分的に彩色が残っている。とても珍しいものを拝観さ
せていただいた。また、本堂(元の礼堂)は国宝。天井が
低く、貴族の邸宅を感じさせる造りになっている。
>> 公式サイトはこちら
吉備真備の長男・ 朝野宿禰魚養の開基といわれ、魚養は
遣唐使として留学後、日本に帰国。境内には魚養塚(お墓)
がある。庭には不動明王石像、合掌観音菩薩石像、春日
曼荼羅石、愛染曼荼羅石、十三重石塔など多くの石仏が
点在している。
●興福寺特別公開(北円堂、三重塔)

北円堂は日本に現存する八角円堂で最も美しいとされる。
安置されているのは弥勒如来(国宝・運慶一門の作)、
苑林菩薩・大妙相菩薩半跏像、無著・世親立像(国宝・
運慶一門の作)。四天王立像(国宝・平安時代初期)。
ここの持国天、多聞天は非常に引き付けられる顔立ち、
表情で、ちょっとアラビアンナイトを思い出した。
三重塔の本尊は弁才天坐像。頭の上に宇賀神(体が白蛇)
と鳥居を載せた変わった姿をしている。弁才天様の背に
描かれている千体仏が元々のご本尊だそう。
■高野山(ブログに)
(奥の院・総本山金剛峯寺・霊宝館・大伽藍大塔・金堂・大門)
快晴!紅葉も終盤。季節的には冬支度が始まっていた。
お大師様の御廟までの参道には2万基以上の供養塔・墓所が
並ぶ。武田信玄・勝頼、上杉謙信・景勝、伊達政宗、織田
信長・・・・・・名だたる武将たちの誰よりも墓石が大きい
「一番石」は秀忠夫人(江姫)ですと!歌舞伎ファン的には
初代市川團十郎、曽我兄弟。熊谷直実と平敦盛の供養塔も。
3つの橋を渡ってようやくたどりついたお大師様の御廟。手
前の部屋に並んだ献灯も壮観だった。
霊宝館で旬の話題は深紗大将立像。快慶の銘が最近見つかっ
たそうで今年10月に記者発表されたばかり。胸回りの髑髏、
お腹に浮かび上がる顔、両膝に施された像の顔。その造形の
緻密さ、表現力の素晴らしさには全くほれぼれ。
12月
●元興寺(ブログに)
●東大寺ミュージアム(ブログに)
■神戸ルミナリエ

■住吉川

★「川西英コレクション収蔵記念展 夢二とともに」
(京都国立近代美術館)12月18日
いやー、愛を感じました。
川西英といえば神戸の風景版画がすぐに頭に浮かぶ。そのひと
がこれほどコアな夢二ファンとは知らなかったなー。ま、私自
身が竹久夢二についてよくは知らないせいもあるけれど。
セノオ楽譜の表紙絵がボリュームといい内容といい、とても
見応えがあってよかった。初公開の肉筆画も3点あった。
でも一番すごいと感じたのは夢二に関するチラシ等を集めて自
分で貼り合わせた「貼り交ぜ」と称する独自のコレクション。
(川西英手製「竹久夢二木版貼り交ぜ 千代紙」ほか。)
これは愛ですよー、コレクターズ愛。
夢二から川西英に送られた手紙にもこんな一文が!「丹念に
集めてくださってありがとうございます。僕の手許には作品は
何も残っていませんから」と。画家って自分で自分の作品は所
有しないものなのかしら。そして、こういうコレクターの存在
は画家にとってどれほど心強いことか・・・。
竹久夢二についてほんの少しのことしか知らない私に、この
コレクションは新鮮な視点とオドロキを与えてくれました。
後から気づいた、きものパスポートを持っていけばよかった。
★北野天満宮・御土居

★椿寺
■神戸ハーバーランド

記録優先!随時追記あり。
京都は★、奈良は●、その他は■
<2011年>
1月
★上賀茂神社・護王神社・八坂神社(ブログに)
★光雲寺
★両足院(秘仏 毘沙門天)
※第45回京の冬の旅 非公開文化財特別公開
★金戒光明寺
★東北院
2月
★玉林院
※第45回京の冬の旅 非公開文化財特別公開
●興福寺国宝館
3月
★真如堂(大涅槃図)
★東山祈りの灯り
4月
■祇園神社・湊川上温泉・雪見御所の跡・荒田八幡神社・
宝地院
★養源院・円山公園
★松尾大社
★平清盛公西八条殿跡
5月
■近江八幡
■安土(沙沙貴神社、安土城跡、安土城天主 信長の館ほか)
★葵祭(下鴨神社、上賀茂神社)
●霊山寺(大弁財天、十二神将ほか)
※秋の公開時には薬師三尊像ほか仏像が内陣で見られる。
6月
★赤山禅院(屋根の上のお猿さん確認)
■満願寺(川西市 清和源氏ゆかりの寺 坂田金時の墓)
★頼光寺(川西市 清和源氏ゆかりの寺 紫陽花が見頃だった)
7月
★祇園祭
■大阪天満宮
■住吉大社
8月
★並河靖之七宝記念館・大寧軒
■伊勢神宮 (ブログに)
豊受大神宮 下宮(+ 別宮 多賀宮・土宮・風宮)
皇大神宮 内宮(+ 別宮 荒祭宮・風日祈宮)
別宮 月読宮
■二見浦(二見興玉神社、夫婦岩ほか)
●秋篠寺(伎芸天立像。ほの暗い部屋で光の加減かお顔だけ
が黒く見える。左に小首を傾げ、優しく微笑んでおられるの
が本当にありがたくただじっと見ていられればいいと思う。)
●春日大社中元万燈籠、東大寺万灯供養、氷室神社
★五山送り火

★宝積寺(十一面観音菩薩立像・三重塔ほか)
★大山崎山荘美術館(企画展「かんさいいすなう」では作家
さんが製作した椅子に実際にすわることができて楽しい♪)
9月
★宝菩提院 願徳寺(如意輪観世音菩薩半跏像)
国宝の「如意輪観世音菩薩半跏像」に再びお目もじが叶った。
ほぼ20年ぶり。お顔が日本ぽくなかったと記憶していたが、
やはりとても美しく間近で拝顔できた。ご住職がお話してく
ださる時にいったん部屋を暗くしてお顔にスポットライトを
当てられるので、額の石がいっそう光ってみえる。写真と実物
とで目の大きさが違って見えるのも不思議。二重まぶたなので
角度によって照明によって変わって見えるのだろうか。
★勝持寺(花の寺)
■葛井寺(千手千眼観世音菩薩座像)

毎月18日に開扉される千手千眼観世音菩薩さま。左に501本、
右に500本の小さな手がビッシリ。さらに持物を持つ大きな
手が40本。手を合わせた真手が2本。すべての手には眼が。
何人をも見逃さず、聞き逃さず、あらゆる手段で救ってくだ
さるという。「なにがなんでも救うたるで!」というお心が
ありがたいやら申し訳ないやら。
■辛国神社
■道明寺(十一面観世音菩薩像)・道明寺天満宮
毎月18日・25日に拝顔できるご本尊で国宝の十一面観音さま
は菅原道真公が手ずから彫ったもの。高さ約90cm。これま
た優雅なお顔。お香や線香の煙により黒くなったとの説明あり。
その試し彫り約60cmの仏像は「こころみの観音様」と呼ば
れご本尊の不在時に拝観できるそうだ。
●当麻寺


<本堂>中将姫が蓮の糸で織った當麻曼荼羅を本尊として祀る。
国宝の厨子、須弥壇などみどころ多し。
<金堂>大きな弥勒仏坐像(白鳳時代・国宝)、十王のような
顔で顎髭がある四天王立像(多聞天以外は白鳳時代・重文)等。
<講堂>ご本尊は丈六の阿弥陀如来座像(重文)。他に妙幢菩
薩(重文)、地蔵菩薩(重文)など。講堂の裏に現存する日本
最古の石灯籠があり、元々はこちらが寺の正面玄関だったそう。
<東塔・西塔>国宝の双塔が美しい。
●傘堂

★同聚院(十万不動明王座像)
★霊雲院(文殊菩薩座像←上半分が見えない、九山八海の庭
★京都府京都文化博物館「帰ってきた江戸絵画 ニューオー
リンズ ギッター・コレクション展」与謝蕪村や池大雅、
伊藤若冲、俵屋宗達、酒井抱一ほか
水墨画が多かった。全体にボリュームが少ないのが残念。
若冲は6点ほどで寒山拾得図がよかった。
●長岳寺
山の辺の道、古墳群
●檜原神社
●大神神社
10月
★神護寺(国宝 五大虚空蔵菩薩坐像、国宝 薬師如来立像ほか)
多宝塔に安置された五大虚空蔵菩薩坐像は10月の第2土日
に特別公開。向かって右から緑(宝光)、赤(蓮華)、白(法界)、
黒(業用)、黄色(金剛)の順に5体並んで壮観。筒型の宝冠を
かぶりお顔は丸く優しい目をしておられる。季節は秋だけ
ど春の匂いがする笑みだった。金堂の薬師如来さまのどっ
しりふくよかな姿に引きつけられる。ただくっきりした小
鼻も突き突き出た口も遠くからしか眺められない。日光・
月光菩薩、十二神将、四天王、すべて一堂に見られるのも
うれしい!
★西明寺
★高山寺
高雄は紅葉には早過ぎて観光客が少なく、ゆっくりできた。
数回来ているのに五大虚空蔵菩薩を観たのは初めてだった。
■浄土寺(兵庫県小野市)

行ってきました、憧れの浄土寺へ。お堂に入っていきなり
国宝の阿弥陀三尊像とご対面。大きゅうござりまする。
三体の像を、正面遠くから立ったまま、近寄って正座して、
横から、斜めから、真後ろから、反対回りに歩いて、と
散々眺める。円形の須弥壇がモダンな雰囲気。阿弥陀如来、
勢至菩薩、観世音菩薩の立体来迎図は後ろに雲の尻尾が立っ
ており、まさにいま雲に乗って到着した感じ。重源上人の
示す浄土世界を形にしたのは快慶。
蔀戸の向こうから西日が差し込み、それが床板に反射し、
阿弥陀三尊像が赤く染まって見えるの絶好のタイミングは
7月下旬~8月上旬の午後3時半~5時半頃とのこと。
●般若寺(コスモス寺、白鳳秘仏・阿弥陀如立像)

●奈良豆比古神社

●樹齢1300年以上の楠

●転外門、北山十八間戸、東大寺境内散歩
11月
●十輪院(元興寺の塔頭、本尊は石仏龕)
奈良・十輪院の地蔵菩薩様は平安時代に造られた優し
いお顔の石仏。外にあるお地蔵様を拝むために、屋根
付きの礼堂を建てたのは鎌倉時代で、その後お地蔵様
を厨子で囲って石仏龕(せきぶつがん)とし、最後に
その石仏龕に屋根をつけたそうだ。
中央の地蔵菩薩の両側には釈迦如来、弥勒菩薩が。
石仏龕をよく見ると一番外は仁王門になっている。内
側には聖観音、不動明王、十王、四天王などが描かれ、
部分的に彩色が残っている。とても珍しいものを拝観さ
せていただいた。また、本堂(元の礼堂)は国宝。天井が
低く、貴族の邸宅を感じさせる造りになっている。
>> 公式サイトはこちら
吉備真備の長男・ 朝野宿禰魚養の開基といわれ、魚養は
遣唐使として留学後、日本に帰国。境内には魚養塚(お墓)
がある。庭には不動明王石像、合掌観音菩薩石像、春日
曼荼羅石、愛染曼荼羅石、十三重石塔など多くの石仏が
点在している。
●興福寺特別公開(北円堂、三重塔)

北円堂は日本に現存する八角円堂で最も美しいとされる。
安置されているのは弥勒如来(国宝・運慶一門の作)、
苑林菩薩・大妙相菩薩半跏像、無著・世親立像(国宝・
運慶一門の作)。四天王立像(国宝・平安時代初期)。
ここの持国天、多聞天は非常に引き付けられる顔立ち、
表情で、ちょっとアラビアンナイトを思い出した。
三重塔の本尊は弁才天坐像。頭の上に宇賀神(体が白蛇)
と鳥居を載せた変わった姿をしている。弁才天様の背に
描かれている千体仏が元々のご本尊だそう。
■高野山(ブログに)
(奥の院・総本山金剛峯寺・霊宝館・大伽藍大塔・金堂・大門)
快晴!紅葉も終盤。季節的には冬支度が始まっていた。
お大師様の御廟までの参道には2万基以上の供養塔・墓所が
並ぶ。武田信玄・勝頼、上杉謙信・景勝、伊達政宗、織田
信長・・・・・・名だたる武将たちの誰よりも墓石が大きい
「一番石」は秀忠夫人(江姫)ですと!歌舞伎ファン的には
初代市川團十郎、曽我兄弟。熊谷直実と平敦盛の供養塔も。
3つの橋を渡ってようやくたどりついたお大師様の御廟。手
前の部屋に並んだ献灯も壮観だった。
霊宝館で旬の話題は深紗大将立像。快慶の銘が最近見つかっ
たそうで今年10月に記者発表されたばかり。胸回りの髑髏、
お腹に浮かび上がる顔、両膝に施された像の顔。その造形の
緻密さ、表現力の素晴らしさには全くほれぼれ。
12月
●元興寺(ブログに)
●東大寺ミュージアム(ブログに)
■神戸ルミナリエ

■住吉川

★「川西英コレクション収蔵記念展 夢二とともに」
(京都国立近代美術館)12月18日
いやー、愛を感じました。
川西英といえば神戸の風景版画がすぐに頭に浮かぶ。そのひと
がこれほどコアな夢二ファンとは知らなかったなー。ま、私自
身が竹久夢二についてよくは知らないせいもあるけれど。
セノオ楽譜の表紙絵がボリュームといい内容といい、とても
見応えがあってよかった。初公開の肉筆画も3点あった。
でも一番すごいと感じたのは夢二に関するチラシ等を集めて自
分で貼り合わせた「貼り交ぜ」と称する独自のコレクション。
(川西英手製「竹久夢二木版貼り交ぜ 千代紙」ほか。)
これは愛ですよー、コレクターズ愛。
夢二から川西英に送られた手紙にもこんな一文が!「丹念に
集めてくださってありがとうございます。僕の手許には作品は
何も残っていませんから」と。画家って自分で自分の作品は所
有しないものなのかしら。そして、こういうコレクターの存在
は画家にとってどれほど心強いことか・・・。
竹久夢二についてほんの少しのことしか知らない私に、この
コレクションは新鮮な視点とオドロキを与えてくれました。
後から気づいた、きものパスポートを持っていけばよかった。
★北野天満宮・御土居

★椿寺
■神戸ハーバーランド