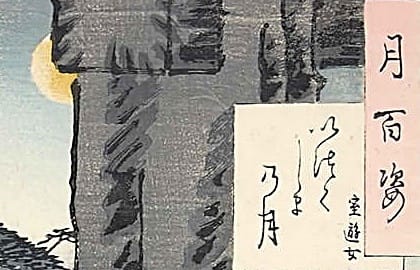月岡芳年 月百姿
『法輪寺乃月 横笛』
明治二十三年印刷

横笛(よこぶえ)は建礼門院徳子の雑子女(侍女) 生没年不詳
平重盛の侍 斎藤時頼(さいとうときより)は
宴の席で舞った横笛に心を奪われ恋に落ちるが
父茂頼に叱責され嵯峨の奥「往生院」に出家し
滝口入道と名を改めます。

国立国会図書館デジタルコレクション 010
平家物語 巻十 横笛より
月もおぼろの二月十日余りの頃、横笛は滝口入道を探して往生院へ向かい
ようやく滝口入道のいる僧房を探しあて、もう一度会いたいと供の者を使わせる。
障子の隙間から横笛の姿を見て心が揺らいだ滝口入道だが、すぐに人を出し
「そのような人は居りません お門違いではないでしょうか」と言わせた。
横笛は力なく涙を抑えて帰るのですが、真の心を伝えたく
近くにあった石に自らの指を切り、流れる血で詠を書いた
『山深み 思い入りぬる柴の戸の まことの道に我れを導け』