
No.218 2006/8/2作成
この画像は、土星探査機カッシーニが7月26日に撮影した土星のGリングの画像を元に作ったものです。
色は分かりやすくするためにつけた人工的なもので、青→緑→赤と進むに連れてより明るいことを示しています。
下側は土星の影です。
左側がリングの内側です。
このアニメーションでは、撮影された画像をやぎが独自に分析して作成したGリングの構造モデルです。
Gリングが少なくとも4本の帯からできているのが分かります。
正式名称がないのでここではとりあえず内側から順にG1、G2、G3、G4と呼ぶことにします。
図にはそれぞれ1(赤)、2(緑)、3(シアン)、4(暗いシアン)と書いておきました。
明るさはG1>G2>G3>G4の順に暗くなっていきます。
G1の内縁、G1-G2間、G2-G3間の境界は比較的明瞭です。
また、Gリングの内側にもリング粒子が薄く広がっています。
ここでは(FリングとGリングの間にあるので)F-Gリングと呼んでおきます。
また、擬似カラー画像でたくさんの斜めの短い線は恒星です。
元の画像:NASA/JPL提供
この画像は、土星探査機カッシーニが7月26日に撮影した土星のGリングの画像を元に作ったものです。
色は分かりやすくするためにつけた人工的なもので、青→緑→赤と進むに連れてより明るいことを示しています。
下側は土星の影です。
左側がリングの内側です。
このアニメーションでは、撮影された画像をやぎが独自に分析して作成したGリングの構造モデルです。
Gリングが少なくとも4本の帯からできているのが分かります。
正式名称がないのでここではとりあえず内側から順にG1、G2、G3、G4と呼ぶことにします。
図にはそれぞれ1(赤)、2(緑)、3(シアン)、4(暗いシアン)と書いておきました。
明るさはG1>G2>G3>G4の順に暗くなっていきます。
G1の内縁、G1-G2間、G2-G3間の境界は比較的明瞭です。
また、Gリングの内側にもリング粒子が薄く広がっています。
ここでは(FリングとGリングの間にあるので)F-Gリングと呼んでおきます。
また、擬似カラー画像でたくさんの斜めの短い線は恒星です。
元の画像:NASA/JPL提供











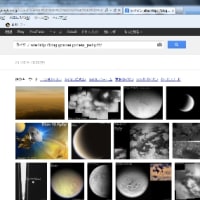
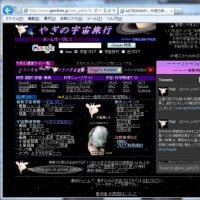


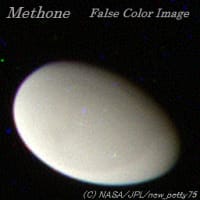
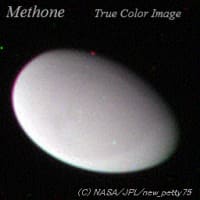



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます