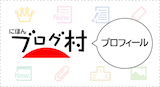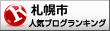小さい発見でも楽しいもの。
たとえ小さくても積み重ねていくと、さらにまたそこから発見があるかもしれません。
ウォーキング中に「発見」があると、ウォーキングがやめられなくなります。
色々関心を持ってみるといいですよ。
たとえ小さくても積み重ねていくと、さらにまたそこから発見があるかもしれません。
ウォーキング中に「発見」があると、ウォーキングがやめられなくなります。
色々関心を持ってみるといいですよ。
よくビルなどの入口付近に、「定礎」と刻まれた石が壁に埋め込まれているのを見ます。
「定礎」とは建築工事の開始を記念して、建物の安泰を祈るために行われる「定礎式」で設置される礎石のこと。
現在では略式化が進み、建物が竣工した際に「定礎」と記された石板を埋め込むようになりました。
「定礎」には特に決まった形式がなく、自由に作れることから、意匠を凝らしたものも見られ、そちらを路上観察のテーマにされている愛好家の方もいらっしゃいます。
(ちなみに、私は見て楽しんでいる程度で、特に記事にしていたりはしておりません。)
そんな訳で、常日頃、路上観察をしている私、ビルの観察もチョロチョロ無意識に行っておりまして、先日、こちらを発見しました。

「竣工」であります。
(札幌エスタのビルにて。)
「竣工」とは、工事が完了して建造物が出来上がること。
私、初めて「竣工」と記された石板をビルで見ました。
何故、「定礎」とせず、「竣工」としたのか、そこが実に興味深い点であります。
そして以前読んだ本のうんちくを思い出しました。
それは、『図解 眠れなくなるほど面白い建築の話』(スタジオワーク著)という本。
この本によると、日本には建物は住み続けることで完成に近づいていくという文化がある、とあります。
例えば、古民家などに見られる柱や梁、縁板の光沢。
これは竣工時からあったものではなく、住む人が何代にも渡って乾拭きし続けたことで生まれたもの。
時間をかけて作り出した美と言えるでしょう。
建築にとっての「竣工」はただの「完成」ではなく、むしろ美しさの始まりなのです。
(第1章「建物は住み続けることで完成していく」より)
もしかすると、このビルが「定礎」ではなく「竣工」としたのには、そうした考えが根底にあったからなのかもしれません。
このビルを訪れるたくさんの人々に利用されることによって、ビルの目指す理想が実現し、そして完成する。
利用する人たちと共に歩んでこそ、このビルの未来がある、という造り手の願いや考えが込められているのかもしれません。
まぁ、考えすぎかもしれません。
単にビルが完成した日時を記しただけだったのかもしれません。
しかし、色々な想像をしたり、調べたりできたので、面白かったです。
良い発見でした。
それとも、もしかして全国のとある街では「定礎」よりも「竣工」の方が一般的だったりするのでしょうか。
今後も「定礎」の観察を続けたいと思います。

<参考資料>
- Tokyo Station City「知られざる定礎の世界」
 当ブログへの問い合わせについて
当ブログへの問い合わせについて仕事等で当ブログに連絡をしたい場合は、
下記のアドレスまでメールにて
お知らせください。
(コメント、感想用ではありません。)
obenben194@gmail.com