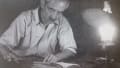<一昨年の春の記録から>
【湧水】~安曇野を訪ねて~ 2014.5.26
松本から、諏訪湖を経由し、富士見町高原のミュージアムへ訪問。
天候悪く「美ヶ原」を取りやめ、「安曇野」でゆっくりすることに。
北アルプスの山々には、まだ雪があり、「安曇野」の原風景を楽しみました。
(写真は、大王わさび農園)
安曇野のわさび田を流れる水は、すべて、この大王わさび農場のわさび畑の中から湧き出す北アルプスの雪解け水(伏流水)だそうです。


「土地」 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
人の世の転換が私をここへ導いた。
古い岩石の地の起伏と
めぐる昼夜の大いなる国、
自然がその親しさときびしさとで
こもごも生活を規正する国、
忍従のうちに形成される
みごとな収穫を見わたす国。
その慕わしい土地の眺めが 今
四方の空をかぎる山々の頂きから
もみじの森にかくれた谷川の河原まで、
時の試練にしっかりと堪えた
静かな大きな書物のように
私の前に大きく傾いてひらいている。
【自註】
山国の信州で、人は山の自然の強力な支配に従順であり、しかもそこから生活の知恵を生み出し、勤勉と忍耐と持久とを学び養う。
富士見高原でもそうだった。
そしてそれ故にこそ私は自分の住む土地と人々とを愛さずにいられなかった。
とは言えまだ新参者の私である。
見なければならない物、知らなければならない事がこれから先いくらでもある。
してみれば今このように眼前にしている広大な土地の眺めは、私にとってずっしりと重い大きな貴重な本にも等しい。
思えば心強くまた楽しいことである。
**********
私の住む大阪府豊中市(ウッスラ青空。季節の歩みは、足踏みしていますが、きれいな夕日でした。2016.2.24<朝・夕>撮影)