
土佐のくじらです。
さて、織田信長の有名なキャッチフレーズ、天下布武ですが、何やら、軍事力で国を支配するっぽい、強面なキャッチコピーなので、誤解されているかも知れません。
しかしこれは、戦国時代を終わらせる・・・という、信長の意思表示だったと思われます。
そう、覇王のイメージの強い信長ですが、最終的には戦のない世の中を目指していたと思われます。
信長の戦の仕方や、政治の行い方は、当時の一般的な、戦国時代の常識的なものは少なく、極めて独自性の強いものが多かったのですが、それはこの、天下布武=脱戦国時代の実現・・・ということにスポットを当てれば、そこからほとんどブレなく導き出されており、実直に実践されているのですね。
この天下布武政策の実現のために、信長がまず行ったのは何か。
それが、兵農分離政策です。
当時は、武士と言っても、半農半武、兼業農家の地域消防隊員みたいな立場です。
武士とは言っても、実は農民なのですね。
豊臣秀吉が農民から天下人へ・・・と言われていますが、秀吉は小作農出身というだけで、当時はみんな、武士=農民だったのです。
ですからこの時代は、農繁期には戦ができませんでした。
当たり前ですよね。
そんなひどいことをする殿様は、下克上の時代には、きっと謀反の対象だったでしょうね。
この、農繁期に戦ができない・・・という時代的ボトルネックを、信長は、兵農分離・・・すなわち、日本で始めて職業としての武士、今で言う、職業軍人を始めて創り出したのです。
ですから、信長以降の織田家の兵隊は、傭兵が多かったはずですね。
では信長は、どうやって職業軍人としての武士を雇ったか。
それは、銭を使って雇ったんです。
それまでは・・・というか、後の江戸時代もそうですが、家臣には、土地を与えたり、米を与えたりして雇っていたんですね。
信長は、日本史に時折歴史上現れる、銭本位制の政治指導者なのですね。
過去には、平清盛や足利義満がいました。
織田家の家臣は、銭で雇われた傭兵ですから、織田軍は戦が年中、いつでもできるようになったのです。
これでは織田家周辺諸大名は、たまったものではなかったでしょうね。
小さな一つの戦では、織田軍をたとえ防ぎえたとしても、長く防ぐことはできなかったと思います。
織田軍は、1年中戦ができます。
他のところでは、秋から春にかけてしか戦ができません。
戦国時代・・・というか、今まではずっとそうしてきましたから、どこも農繁期に戦する時代になるなんて、誰も思ってもいなかったのですよ。
織田信長は、桶狭間とか、長篠の戦とか、戦術面ばかりが強調されて紹介されることが多いのですけが、実は、システマティックな面、そして組織で勝つという面において、織田軍は強かったのですね。
傭兵の潜在的な希望者は、結構いたんじゃないでしょうか。
当時は、土地本位制ですので、多くの土地を持たない農家の次男三男などは、一声掛ければ、すんあり傭兵になったんじゃないかと思いますね。
どうせ殿様から、「戦じゃ!」って言われたら、当時はみんな、問答無用で戦に行く身でしたのでね。
農作業免除で、手っ取り早く銭をくれる、信長の兵農分離政策は、民衆も喜んだのではないでしょうか。
天下布武・・・という大戦略を実現するための、組織面での戦術の一つが、兵農分離・・・だったわけです。
戦国を終わらせる!という掛け声は、誰でも言おうと思えば言うことが出来ます。
しかし大事なのは、それを実現させるための具体策です。
具体策なしの掛け声だけでは、一時期人は付いてきても、いつかは薄い仮面は剥がされます。
これは、現代でも当てはまることです。
デフレ脱却!と言いながら、増税していたのでは、本末転倒の掛け声倒れです。
でも疑問が残りますね。
なぜ信長だけが、銭で家臣を雇えたのでしょうか?
それは、信長独自の経済政策にあるのです。
ではまたお会いしましょう。(^^)/
(続く)













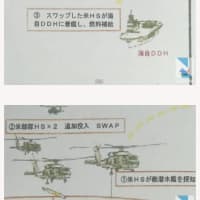






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます