
土佐のくじらです。
今日2本目の記事です。
私、少し焦っています。
縄文時代で少し寄り道してしまって、ムーやらアトランティスにまで話が飛びましたので、(笑)
当初の予定より、相当ペースが遅れております。(^^;
朝書いた記事では、弥生時代こそ、日本の神代の時代である・・・ということを書きました。
今回もう少しだけ、この時代の背景について、その説明をさせてください。
この時代こそ、日本に米作が入って来た時代であり、そして、日本神道の宗教アイテムは、【米と酒】であります。
この【米】と【酒】をキーワードに、弥生時代=神代の時代説で、これからこの時代の分析を続けて参ります。
それが、日本の神話の時代を紐解く鍵となると思います。
日本のお米は、”ジャポニカ米”という種類で、中国北部や朝鮮半島のお米とは種類が違うものです。
中国南部、福建省あたりが原産地とされる、水分を多く含んだお米ですね。
北部アジアとは種類が違いますので、日本米は沖縄を経由して、日本列島に入って来たものと推測されます。
しかし、沖縄など西南諸島では、地質の関係上、水田ができなのですね。
土壌がサンゴ礁でできていて、水はけが良すぎて、ジャポニカ米に必要な水田ができないのです。
ですから日本のお米は、種籾(たねもみ)の形で一気に日本列島に上陸した可能性が大きいです。
沖縄からも縄文遺跡が出てきますから、縄文後期に海路で、南方から日本に入ってきたのでしょうね。
沈まぬ船による海洋文明である縄文文明ならば、それは軽くできたことでしょう。
じわじわ、沖縄で稲作をして、順々に米作が広がっていったイメージが私にもありましたが、
現実はそういうことは不可能と思われるので、一気に九州にまで伝播したと思われます。
※「奄美大島では水田が可能。」「奄美は土壌も、珊瑚礁ではない。」と、奄美のアマミキヨさんがブログに書いていらっしゃいました。
奄美大島で水田が可能なら、ジャポニカ米の栽培が奄美でなされた後、稲作が九州に伝播したかも知れません。
(アマミキヨさん、記事にしてくださってありがとうございました。)
そして縄文の栗、弥生のお米。
この二つの時代の主食で、最も違うのは栄養分ですね。
栄養の量も、摂取できる種類も、圧倒的にお米が優れています。
玄米ならば、カルシウム意外は全て、必要量が摂取できる・・・という、”ほぼ完全食”がお米です。
ですから、寒流が流れ始め寒冷化して、栗の採取量が少なくなっただけでなく、栗VS米では、主食としては、太刀打ちできないでありましょうね。
実際の人口区分においても、縄文時代の日本列島は、1500万人から人口が増えることはありませんでした。
弥生化し、米の生産を始めた日本は、明治の頃に3000万人の人口を持つまで、じりじりと人口を増やしております。
文明力=人が食っていける力=人口
という、背景が読み取れます。
現代日本は、人口減社会となりつつありますが、明治以降の新たな日本文明が、縄文末期のように限界が来ているのかも知れません。
日本が新たな文明を持つことができれば、人口減社会から抜け出せる可能性があるとも言えます。
さて、歴史の流れを見ると、やはり九州から弥生化して行ったはずです。
それが大体、今から3000年くらい前と言われています。
(もう少し前かも知れません。)
その、日本の弥生化の時代は、同時に中国大陸における、巨大国家誕生の時代でもあります。
実は、弥生時代というのは、日本としては、外交上の脅威が始まった時代・・・と言うことが出来ると思います。
約4000年前に、中国では夏(か)という王朝ができています。
3000年前だと、秦・そして漢ですね。
実は、秦・漢は当時まだ、直接的には日本へ脅威とはなりません。
距離が離れているのもありますが、実は漢民族というのは、完全な大陸民族であって、海の外にはまったく興味がない人たちなのです。
(ですから、尖閣=中国領説はウソです。)
脅威となるのは、やはり朝鮮半島なのですね。
特に、秦の始皇帝が、万里の長城を造って以降、北方の脅威を中国人が感じなくなってからは、漢民族による朝鮮半島へのチョッカイがはじまるのですね。
恐らく、チョッカイを出された古代朝鮮民族は、九州地方への動きを強めた可能性もありますね。
それは良い面、悪い面、両面あったと想像いたします。
つまり、経済的にも、文化的にも、軍事的にも・・・です。
現実、九州ー朝鮮半島の交流は、相当あったと思います。
朝鮮半島からも、縄文遺跡と思われる遺物が出土します。
それで、”縄文朝鮮半島根源説”があったりしますが、日本での縄文遺跡の出土率は、半島とは比較にならないくらい多いですから、縄文文明は、日本根源に間違いないでしょう。
沈まぬ舟を持つ縄文人ならば、積極的に朝鮮半島にも進出し、交易できたはずです。
良きにつけ、悪しきにつけ、九州と朝鮮半島は、かなりお互いに影響を受け、そして影響を与える環境に、この時代(縄文後期、弥生時代前半)にはなっていたことが、想像されるわけですね。
そしてそれが、日本神道の国創りや、邪馬台国伝説へとつながって行く・・・
そんなミステリアスな雰囲気が、縄文とは違う弥生の魅力ですね。
つまり、その後の日本の、外交政策の基本的な指針が、形成されたのが弥生時代である・・・とも言える訳なのです。
(続く)













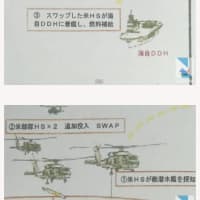






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます