
土佐のくじらです。
本日2本目の記事です。(笑)
前回記事では、奈良盆地の地形的条件から、神武東征の目的は、朝鮮半島からの防御にある・・・ということを述べました。
要するに大和朝廷は、奈良盆地という、朝鮮半島からの攻撃を想定した上での、鉄壁の要塞のような場所に造られた・・・ということです。
奈良要塞都市説と言っても良いですね。
今日は、神武東征伝説の最終章なんですが、私はこの期間における、九州ヤマト国と、他の国々との関わりが、その後の、日本神道の儀式や文化に、相当の影響を与えているのではないか・・・? と、考えています。
今回の記事の内容は、右翼系の方や、国粋主義的思想をお持ちの方から見れば、「不敬罪だ!!」と、揶揄されるものかも知れません。(笑)
卑しくも、拍手というものは、場の穢れを祓い云々也・・・と、お怒りになるやも知れません。
しかし、宗教というのは、それが拡がる過程における、さまざまな事柄が、行事や宗教アイテムに、取り入れられているものなのですね。
たとえば、キリスト教におけるクリスマスツリーは、その顕著な例ですね。
イエス様が人生をお過ごしになったユダヤの地には、モミの木なんかありませんね。
ユダヤは砂漠地方ですから、モミの木のような針葉樹はありませんし、当然雪もかぶっておりません。
これはドイツの、”冬至の祭り”の風習を、キリスト教が取り入れたのですね。
イエス様の誕生日が、12月25日というのも、かなり怪しいです。
恐らく、冬至=イエス様ご生誕日・・・と、キリスト教伝道者が、勝手に決めたんじゃないでしょうかね。(笑)
仏教でも、旅の行者が持つ、ジャラジャラと音の出る”杖”が、宗教アイテムですが、これなどは、古代インドでの、”蛇除け・猛獣除け”ですね。
お釈迦様も、インド中を行脚なさっていますので、移動に関する道具がジャラジャラ杖なのです。
お線香なども虫除けでしょうし、精舎でたくさんの人が一堂に集まるとさすがに臭いので(笑)、それで香を焚く工夫がなされていたはずです。
ですから、日本神道も同様に、儀式や儀礼建築物などは、教えの内容やそれが持つ芸術性だけでなく、その伝道背景などにも、かなり影響されているはずなのです。
日本神道と言えば、建築物は神社ですね。
神社は大抵、森の中にありますね。
いわゆる、”鎮守の森”ですね。
”森”というのは、手付かずの木々の集まりです。
一方、”林”というのは、人工的に整備された、木々の集まりです。
大抵、森の中に神社はあります。
そして祠(ほこら)があって、大きな鈴を鳴らして、拍手(かしわで)を打ちますね。
一般的な神社では、柏手は2回で、出雲大社だけは拍手4回です。
この一連の、神道の儀式、建築文化は、神武東征という名の、ヤマト国の使者と他の国々の代表者との、”極秘の打ち合わせや交渉で使われた儀式”なのではないでしょうか?
つまり、ヤマト国の使者は、朝鮮半島諸国に動きを知られては困るので、他の縄文系諸国に、かくまわれていたはずなのです。
奈良盆地という、難攻不落の要塞地形であれば、ヤマトの国の軍隊は、奈良盆地に攻め入ることは不可能です。
私なら諦めます。(笑)
地元での、何らかのお膳立てがなければ、征服どころか無事に進入することすらできません。
つまり、九州から奈良盆地への神武東征は、軍事侵攻ではなかったと私は考えます。
つまり、東征・・・という軍事行動ではなく、大部分は交渉・・・だったはずなのです。
交渉の場所や打ち合わせ方法、交渉成立の後の打ち上げの宴が、日本神道における宗教儀式に繋がったのではないでしょうか?
その様子は、このようなものではなかったでしょうか?
ヤマトの国の使者(もしくは天皇)は、まず”森”の中に祠を建てます。
そこが打ち合わせの場所となります。これが神社の原型ではないでしょうか?
それが、日本神道における最高の司祭としての天皇・・・という位置付けの原型につながると思います。
そしてそこに、縄文系の代表者が、ヤマト国の使者に会いに来た時の”合言葉”的なものが、
まず鈴を鳴らし、拍手2回(出雲国の使者には4回)だったのではないでしょうか?
交渉内容は、ヤマト国への協力依頼と、米の生産技術に関するものが多かったはずです。
今でも、天皇陛下は年中行事として、多くの農業、特に米に関する行事を行っていらっしゃいます。
4月上旬に種籾(たねもみ)を蒔く 【お手まき】 5月下旬に【お田植え】、そして、10月上旬に【お稲刈り】をしています。
またその秋収穫された米は、11月23日の【新嘗祭】という、収穫を感謝する祭儀で使われます。
また今でも、お祝い事の際には、赤飯が炊く習慣があります。
めでたいから赤い色を着けるのかと、私も最近まで思っていましたが、どうやら、日本の古代のお米は、赤かったらしいのですね。
その後の品種改良で、お米の色は白くなりましたが、赤飯は古代、この時代の祭りなどの際に使われた、”赤いお米”にまつわるものかも知れません。
さて、神武東征伝説は、ひとまずこれにて。
次回からはいよいよ、古代ミステリーハンター土佐のくじら歴史館のメインイベントです。
そうです。
古代日本最大の謎、邪馬台国の謎解きのチャレンジに挑戦いたします。(笑)
(続く)













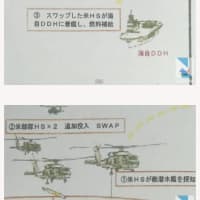






そうでつ。
そういうことでつ。(笑)
と、いうことですが、
土佐のくじらさんの説からすると、
九州からの遍都をするにあたって、
大々的にやると、半島に漏れるので、
秘密裏に行いたい。
ということを、「かくまってくれ」という意味で言ったわけでしょうか。