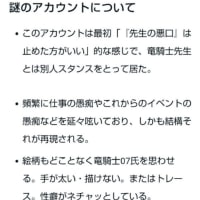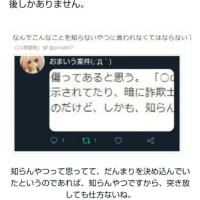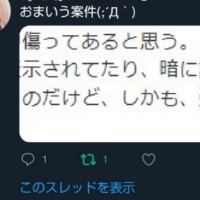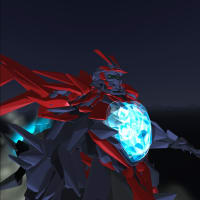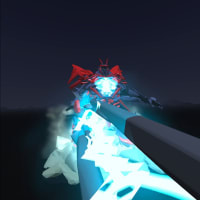「楽園」
冷たかった冬の風が、少し暖かくなり、遥か地平線までつづく草原がざわめいた。
あの日からかなりの月日が流れた。
最初の二ヶ月までは、日の出、日の入りを数えていたが、やがて日時などが意味を持たない事に気付き、今はただ緩やかに流れる時に身をまかせていた。
あの日…。
私は学校に向かう途中だった。
一瞬にして世界から人が消え去り、地上で動く存在は私だけになった。
世界は変化し、かつて街とよばれた廃墟は朽ち果て、美しい自然が汚いものをすべて覆いつくした。
何があったのかわからない。
でも何の不便があるわけでもなく、私の名前や存在も含めて、どうでもよくなっていた。
不思議に食料にも困る事はなかったし、水も空気も、すべてが存在した。
木の下であったり、岩の上であったり…
欲しいと願った時に、それは存在した。
何も悩む必要はない、私だけの楽園。
幸福だった。満ち足りていた。
でも、ある日…。
いつもと違った感情が私を襲ったのだ。
それは退屈なのか、好奇心なのかわからない。
ただ、私の楽園が存続する事を脅かす感情であることは間違いなかった。
でも、私はそれに逆らえなかったのだ。
住みなれた楽園を離れ、私の気持ちを乱していた小屋へと向かう。
絵本に出てくるような丸太を組合せて作られた小屋の扉を開ける。
甘いミルクのような香り。
小屋の中にはピンクのカーペットを敷き詰めた小部屋があり、アンティークの机と椅子が置かれていた。
壁には写真がたくさん飾られている。
顔はよく見えないけど、その女の子はとても幸福そうに見えた。
家族…か。
私はなんで存在してるの?
それに意味はあるの?
長い間動かなかった私の心の振り子は、錆をふるい落として少しづつ揺れ始めた。
その揺れは、机の上にあった日記を開いた時に最高潮に達した。
「〇月○日、元気な赤ちゃん誕生。女の子です。私の分身がこうして腕の中にいる事に不思議な感情と、ただ有難うという言葉だけが浮かんできて、嬉しいのに涙が溢れます」
「この世界が、この子にとって少しでも楽しいところだったら良いのに、勉強なんてできなくてもいいです。人よりノンビリ屋さんでも良いのです。ただ、この子が元気で生きていてさえくれれば… 本当に産まれてきてくれて有難う」
壁の写真は… 私だ…。
謝りたい… 有難うと言いたい、ただ、ただ抱きしめてあげたい。
まばゆい光が私を包み…壁が崩れてゆく…
一瞬光が視界を奪ったのだが、それはカーテンから漏れる光だった。
私の部屋…。
私が逃げ込んだ小さな楽園。
何日も閉めていたはずのカーテンから、一筋の光がもれて部屋を横断するラインを描いていた。
ボサボサの髪を束ねながら、パジャマのまま立ち上がる。
扉の前には、ラップをかけたチャーハンが置いてあった。
添えられたメモに、あの小屋でみた日記と同じ字で、母からのメッセージが書かれていた。
「昼ご飯、置いておきます。奈緒ちゃんが部屋から出てきてくれるの待ってるからね」
…
私は、どれくらい部屋に篭っていたのだろう。
この汚い世界から、私を否定するあいつらから逃げたいと思ったのだ…。
私なんて、部屋を舞うホコリよりも軽い存在だと思っていた。
私が生きる意味や価値なんて無いのだと…。
私がここにいる事を望んでくれた人がいる。
私の事を想ってくれる人がいる…。
当たり前と思い込んで、そんな大事な事に気付かなかったのだ。
傷ついたって、落ち込んだって、進んで行こう。
それを望んで私をここに読んでくれた人がいるのだから。
冷たかった冬の風が、少し暖かくなり、遥か地平線までつづく草原がざわめいた。
あの日からかなりの月日が流れた。
最初の二ヶ月までは、日の出、日の入りを数えていたが、やがて日時などが意味を持たない事に気付き、今はただ緩やかに流れる時に身をまかせていた。
あの日…。
私は学校に向かう途中だった。
一瞬にして世界から人が消え去り、地上で動く存在は私だけになった。
世界は変化し、かつて街とよばれた廃墟は朽ち果て、美しい自然が汚いものをすべて覆いつくした。
何があったのかわからない。
でも何の不便があるわけでもなく、私の名前や存在も含めて、どうでもよくなっていた。
不思議に食料にも困る事はなかったし、水も空気も、すべてが存在した。
木の下であったり、岩の上であったり…
欲しいと願った時に、それは存在した。
何も悩む必要はない、私だけの楽園。
幸福だった。満ち足りていた。
でも、ある日…。
いつもと違った感情が私を襲ったのだ。
それは退屈なのか、好奇心なのかわからない。
ただ、私の楽園が存続する事を脅かす感情であることは間違いなかった。
でも、私はそれに逆らえなかったのだ。
住みなれた楽園を離れ、私の気持ちを乱していた小屋へと向かう。
絵本に出てくるような丸太を組合せて作られた小屋の扉を開ける。
甘いミルクのような香り。
小屋の中にはピンクのカーペットを敷き詰めた小部屋があり、アンティークの机と椅子が置かれていた。
壁には写真がたくさん飾られている。
顔はよく見えないけど、その女の子はとても幸福そうに見えた。
家族…か。
私はなんで存在してるの?
それに意味はあるの?
長い間動かなかった私の心の振り子は、錆をふるい落として少しづつ揺れ始めた。
その揺れは、机の上にあった日記を開いた時に最高潮に達した。
「〇月○日、元気な赤ちゃん誕生。女の子です。私の分身がこうして腕の中にいる事に不思議な感情と、ただ有難うという言葉だけが浮かんできて、嬉しいのに涙が溢れます」
「この世界が、この子にとって少しでも楽しいところだったら良いのに、勉強なんてできなくてもいいです。人よりノンビリ屋さんでも良いのです。ただ、この子が元気で生きていてさえくれれば… 本当に産まれてきてくれて有難う」
壁の写真は… 私だ…。
謝りたい… 有難うと言いたい、ただ、ただ抱きしめてあげたい。
まばゆい光が私を包み…壁が崩れてゆく…
一瞬光が視界を奪ったのだが、それはカーテンから漏れる光だった。
私の部屋…。
私が逃げ込んだ小さな楽園。
何日も閉めていたはずのカーテンから、一筋の光がもれて部屋を横断するラインを描いていた。
ボサボサの髪を束ねながら、パジャマのまま立ち上がる。
扉の前には、ラップをかけたチャーハンが置いてあった。
添えられたメモに、あの小屋でみた日記と同じ字で、母からのメッセージが書かれていた。
「昼ご飯、置いておきます。奈緒ちゃんが部屋から出てきてくれるの待ってるからね」
…
私は、どれくらい部屋に篭っていたのだろう。
この汚い世界から、私を否定するあいつらから逃げたいと思ったのだ…。
私なんて、部屋を舞うホコリよりも軽い存在だと思っていた。
私が生きる意味や価値なんて無いのだと…。
私がここにいる事を望んでくれた人がいる。
私の事を想ってくれる人がいる…。
当たり前と思い込んで、そんな大事な事に気付かなかったのだ。
傷ついたって、落ち込んだって、進んで行こう。
それを望んで私をここに読んでくれた人がいるのだから。