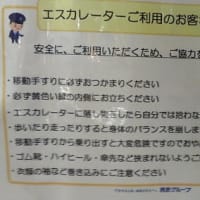2月7日(火)小菅 優(Pf)
~ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会シリーズ 第3回~
紀尾井ホール
【曲目】
1.ピアノ・ソナタ第9番 ホ長調Op.14-1
2.ピアノ・ソナタ第10番 ト長調Op.14-2

3.ピアノ・ソナタ第27番 ホ短調Op.90
4.ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調Op.27-1

5.ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調Op.27-2「月光」


【アンコール】
1. シューマン/リスト編/献呈

2. シューマン/子供の情景~「詩人は語る」
小菅優によるベートーヴェン・ンソナタシリーズの3回目。強烈なインパクトを放って「今最高のベートーヴェン!」とまで思った初回に比べると、2回目ではまだ更に掘り下げる余地も感じたが、今夜の3回目では、初回のような手放しの絶賛とまではいかないにしても、小菅ならではの持ち味と感じていたものを存分に聴かせてくれただけでなく、これまでは気付かなかったこのピアニストの別の素晴らしい一面を新たに見せてくれた。
以前から魅了されていた僕にとっての小菅さんならではの持ち味とは、新鮮で活き活きとした即興性。作曲家の魂が瞬間に乗り移って、インスピレーションの息吹を送り続けてくるのを受け止め、煌めく楽想を次々と紡いで行く魅力。ベートーヴェンならではの、瞬間的に起こる気分の転換や、ハッと息を飲むディナミークの変化、或いは火に油を注ぐようにどんどんとテンションを高めて行くシーンを、小菅はいとも容易く、乗りに乗って、楽しげに聴かせ、聴き手を鮮やかなドラマの中へ引き込む。そんな魅力が全開したのが、作品14の2の第3楽章や、作品27の1。まさに小菅の思うままに音楽が運び、抜群の効果を発揮し、幸せな気分にしてくれた。
小菅の別の素晴らしい一面を感じたのは最後に演奏した「月光」。ここでは、多彩に気分を変え、鮮やかにフレーズを描き分けるやり方とは一転、全曲がひとつのトーンに貫かれた揺るぎのない世界を形作った。そこで貫かれていたひとつのトーンとは、重苦しいほどに内面的な世界。第1楽章は、生暖かい空気が漂う暗闇のなか、時より風向きを変えて吹く湿った風に乗って聴こえてくる調べが、近づいたり離れたりしているような陰鬱。この楽章は、よく言われる作曲家の恋物語的な感傷やファンタジーとは無縁の、逃げたくなるような重苦しさに支配されていた。
第2楽章について、小菅はプログラムのなかで「よく(軽やか)な楽章と言われますが、私はそうは思わない。確かにこの楽章だけ希望が見えるし舞曲的な要素もあるものの、蔭も見えるし(前触れ)も感じられますよね 」と語っているが、演奏を聴いてそれがどういうことかが納得できた。これまでの小菅のイメージでは、この楽章を、持ち味の即興性で軽々と活き活きと奏でることもできただろうが、そうはせずに、湿り気のある、やはり陰鬱な気分がつきまとう演奏。それは、第3楽章で起こる「破局」を予感し、そこから逃れようとしているようにも聴こえた。
そしてその「破局の」第3楽章がやってくる。この、ある意味ドラマチックな楽章でも、小菅は持ち前の多彩な音色のパレットは封じ込め、モノトーンとも言える重苦しい音色を貫き、「これでもか」と言わんばかりに、這上がってくる者達を情け容赦なく打ちのめす。その気迫、エネルギーの凄まじさに圧倒された。多彩さが「売り」と思っていた小菅の、これは新たな境地の開拓!「この曲、全然ポジティヴじゃないですよね…」、とプログラムで語っていた小菅の言葉を余すことなく音で体現した演奏だった。この先に予定されている後期のソナタ群の演奏が今から楽しみになった。
アンコールでは、そうした重苦しい気分からは一気に解放され、シューマンの溢れる歌の世界に酔った。この歌謡性を、作品90の第3楽章などでももっと惜しみなく出してくれれば、とも思ったが、そうしなかったのはベートーヴェンの様式感への節度ある配慮だったのだろうか。
小菅 優 ベートーヴェン・ソナタ・シリーズ vol.2~2011.6.30 紀尾井ホール~
小菅 優 ベートーヴェン・ソナタ・シリーズ vol.1~2010.10.27 紀尾井ホール~
~ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会シリーズ 第3回~
紀尾井ホール
【曲目】
1.ピアノ・ソナタ第9番 ホ長調Op.14-1

2.ピアノ・ソナタ第10番 ト長調Op.14-2


3.ピアノ・ソナタ第27番 ホ短調Op.90
4.ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調Op.27-1


5.ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調Op.27-2「月光」



【アンコール】
1. シューマン/リスト編/献呈


2. シューマン/子供の情景~「詩人は語る」

小菅優によるベートーヴェン・ンソナタシリーズの3回目。強烈なインパクトを放って「今最高のベートーヴェン!」とまで思った初回に比べると、2回目ではまだ更に掘り下げる余地も感じたが、今夜の3回目では、初回のような手放しの絶賛とまではいかないにしても、小菅ならではの持ち味と感じていたものを存分に聴かせてくれただけでなく、これまでは気付かなかったこのピアニストの別の素晴らしい一面を新たに見せてくれた。
以前から魅了されていた僕にとっての小菅さんならではの持ち味とは、新鮮で活き活きとした即興性。作曲家の魂が瞬間に乗り移って、インスピレーションの息吹を送り続けてくるのを受け止め、煌めく楽想を次々と紡いで行く魅力。ベートーヴェンならではの、瞬間的に起こる気分の転換や、ハッと息を飲むディナミークの変化、或いは火に油を注ぐようにどんどんとテンションを高めて行くシーンを、小菅はいとも容易く、乗りに乗って、楽しげに聴かせ、聴き手を鮮やかなドラマの中へ引き込む。そんな魅力が全開したのが、作品14の2の第3楽章や、作品27の1。まさに小菅の思うままに音楽が運び、抜群の効果を発揮し、幸せな気分にしてくれた。
小菅の別の素晴らしい一面を感じたのは最後に演奏した「月光」。ここでは、多彩に気分を変え、鮮やかにフレーズを描き分けるやり方とは一転、全曲がひとつのトーンに貫かれた揺るぎのない世界を形作った。そこで貫かれていたひとつのトーンとは、重苦しいほどに内面的な世界。第1楽章は、生暖かい空気が漂う暗闇のなか、時より風向きを変えて吹く湿った風に乗って聴こえてくる調べが、近づいたり離れたりしているような陰鬱。この楽章は、よく言われる作曲家の恋物語的な感傷やファンタジーとは無縁の、逃げたくなるような重苦しさに支配されていた。
第2楽章について、小菅はプログラムのなかで「よく(軽やか)な楽章と言われますが、私はそうは思わない。確かにこの楽章だけ希望が見えるし舞曲的な要素もあるものの、蔭も見えるし(前触れ)も感じられますよね 」と語っているが、演奏を聴いてそれがどういうことかが納得できた。これまでの小菅のイメージでは、この楽章を、持ち味の即興性で軽々と活き活きと奏でることもできただろうが、そうはせずに、湿り気のある、やはり陰鬱な気分がつきまとう演奏。それは、第3楽章で起こる「破局」を予感し、そこから逃れようとしているようにも聴こえた。
そしてその「破局の」第3楽章がやってくる。この、ある意味ドラマチックな楽章でも、小菅は持ち前の多彩な音色のパレットは封じ込め、モノトーンとも言える重苦しい音色を貫き、「これでもか」と言わんばかりに、這上がってくる者達を情け容赦なく打ちのめす。その気迫、エネルギーの凄まじさに圧倒された。多彩さが「売り」と思っていた小菅の、これは新たな境地の開拓!「この曲、全然ポジティヴじゃないですよね…」、とプログラムで語っていた小菅の言葉を余すことなく音で体現した演奏だった。この先に予定されている後期のソナタ群の演奏が今から楽しみになった。
アンコールでは、そうした重苦しい気分からは一気に解放され、シューマンの溢れる歌の世界に酔った。この歌謡性を、作品90の第3楽章などでももっと惜しみなく出してくれれば、とも思ったが、そうしなかったのはベートーヴェンの様式感への節度ある配慮だったのだろうか。
小菅 優 ベートーヴェン・ソナタ・シリーズ vol.2~2011.6.30 紀尾井ホール~
小菅 優 ベートーヴェン・ソナタ・シリーズ vol.1~2010.10.27 紀尾井ホール~