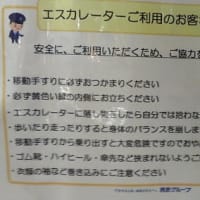12月9日(金)フェルトホーヴェン指揮オランダ・バッハ協会合唱団&管弦楽団
東京オペラシティコンサートホール:タケミツメモリアル
【曲目】
バッハ/ロ短調ミサ曲 BWV232
【演 奏】
S:ドロテー・ミールズ、ヨハネッテ・ゾマー/A:マルゴット・オイツィンガー/T:チャールズ・ダニエルズ/B:ピーター・ハーヴェイ
ヨス・ファン・フェルトホーフェン指揮オランダ・バッハ協会合唱団&管弦楽団
2008年に聴いた「ヨハネ」がとても感銘深かったフェルトホーヴェン指揮オランダバッハ協会がロ短調ミサをやるというので聴いてきた。合唱は「ヨハネ」の時よりも増強されて最大で15名。
この演奏で特徴的だったのはその合唱部分の扱い。ソリスト達によって1パート1人ずつで担当する部分と、トゥッティで歌われる部分が交替しながら進んで行く。多くの場合、ソリスト達が先導し、合唱がそれに続いて応唱するというパターンが取られた。器楽曲で言えば、複数のソロ楽器とオーケストラによるコンチェルト・グロッソのような掛け合いが行なわれる。このため、演奏により変化と動きが生まれ、響きがより立体的になり、ドラマチックな効果が生まれた。
まず"Kyrie"の冒頭合唱がトゥッティで柔らかく厳かにホールに響き、オケによる主題提示に続くフーガはソリストで歌われ、2度目はトゥッティで歌われる。"Credo"の最初のフーガもソロで始まり、合唱に引き継がれる。ミサ曲ではよくソロが受け持つ"Et incarnatus est"が合唱で歌われたのは意外だったが、やっぱりここは合唱で奥行を与えられるのがいい。その次の"Crucifixus"はソリスト達により歌われたが、こちらは生々しさが露わになって、ソロによる効果が出ていた。通奏低音が徐々に音を失い、最後の方はポジティヴオルガンだけが残り、キリストの「死」が象徴的に表されていた。"Sanctus"では、「聖なるかな」と唱和する部分が合唱で歌われ、3連符によるメリスマの部分はソリストが担当して、立体的な構造が現れた。ここは二重合唱だったのか、と思ったが、そういうわけではないようなので、これもフェルトホーヴェンのアイディアか。
このように、合唱部分に多く施された工夫が、研究による成果なのか、或いはフェルトホーヴェンのアイディアなのかは知らないが、こうした工夫が功を奏していた。更に、前回「ヨハネ」と同様に、全体的にゆっくり目のテンポで、温かな音色で、丁寧に抑揚を紡ぐやり方が、神への奉仕のようにも聴こえ、深い祈りが感じられた。トランペットが入り、華やかな音響になる楽曲での、溶け合う響きの美しさも素晴らしかった。決して派手な音にはならず、こうしたところからもひたむきな神への賛美が感じられた。そしてこれは、プレイヤー達の卓越した技術が支えていることも間違いない。
フェルトホーヴェンの演奏からは、神の威光をことさら大きく見せつけるようなところが全くなく、清貧の精神に貫かれていると言っていいほどの謙虚さを感じる。"Agnus Dei"のアルトのソロ、今回はソリストが女声(オイツィンガー)だったので、カウンターテナーのストイックな歌ではない、豊饒に包み込むような歌を密かに期待していたが、これはカウンターテナー以上にストイックな歌唱で、まさに死に行くキリストを見つめて立ち止まる様子が歌われていた。そもそもここで歌に酔いしれたりするのは不謹慎で、共にキリストの犠牲を我が身のものとして受け止め、祈らなければならない、と諭されているような厳しささえ感じた。そんなわけで、最後の"Dona nobis pacem"の合唱からも、天に昇るような幸福感をもたらしてはもらえなかった。
今夜のロ短調ミサを聴いて、これがいかに優れたホンモノの演奏であるかといういうことは十分に感じ、理解できたと思う。とても美しいとも感じた。だが、そこから真の感動を得るには、このミサの典礼文が伝える宗教的な意味を共有し、それに心から共感していることが求められているような気がしてしまい、そんな信仰は持ち合わせないボクには少々入っていけないものを感じた。ソロはもっと艶やかなベルカントで歌って欲しいし、合唱も少し大袈裟なくらい感動的に歌ってくれたほうがいい。ロ短調ミサは、豊かな響きで、陶酔できるほどに包み込んでくれるような、俗っぽいくらいの演奏が個人的には好きだ。
フェルトホーフェン指揮オランダ・バッハ協会合唱団&管弦楽団「ヨハネ受難曲」(2008.2.25 紀尾井ホール)
東京オペラシティコンサートホール:タケミツメモリアル
【曲目】
バッハ/ロ短調ミサ曲 BWV232

【演 奏】
S:ドロテー・ミールズ、ヨハネッテ・ゾマー/A:マルゴット・オイツィンガー/T:チャールズ・ダニエルズ/B:ピーター・ハーヴェイ
ヨス・ファン・フェルトホーフェン指揮オランダ・バッハ協会合唱団&管弦楽団
2008年に聴いた「ヨハネ」がとても感銘深かったフェルトホーヴェン指揮オランダバッハ協会がロ短調ミサをやるというので聴いてきた。合唱は「ヨハネ」の時よりも増強されて最大で15名。
この演奏で特徴的だったのはその合唱部分の扱い。ソリスト達によって1パート1人ずつで担当する部分と、トゥッティで歌われる部分が交替しながら進んで行く。多くの場合、ソリスト達が先導し、合唱がそれに続いて応唱するというパターンが取られた。器楽曲で言えば、複数のソロ楽器とオーケストラによるコンチェルト・グロッソのような掛け合いが行なわれる。このため、演奏により変化と動きが生まれ、響きがより立体的になり、ドラマチックな効果が生まれた。
まず"Kyrie"の冒頭合唱がトゥッティで柔らかく厳かにホールに響き、オケによる主題提示に続くフーガはソリストで歌われ、2度目はトゥッティで歌われる。"Credo"の最初のフーガもソロで始まり、合唱に引き継がれる。ミサ曲ではよくソロが受け持つ"Et incarnatus est"が合唱で歌われたのは意外だったが、やっぱりここは合唱で奥行を与えられるのがいい。その次の"Crucifixus"はソリスト達により歌われたが、こちらは生々しさが露わになって、ソロによる効果が出ていた。通奏低音が徐々に音を失い、最後の方はポジティヴオルガンだけが残り、キリストの「死」が象徴的に表されていた。"Sanctus"では、「聖なるかな」と唱和する部分が合唱で歌われ、3連符によるメリスマの部分はソリストが担当して、立体的な構造が現れた。ここは二重合唱だったのか、と思ったが、そういうわけではないようなので、これもフェルトホーヴェンのアイディアか。
このように、合唱部分に多く施された工夫が、研究による成果なのか、或いはフェルトホーヴェンのアイディアなのかは知らないが、こうした工夫が功を奏していた。更に、前回「ヨハネ」と同様に、全体的にゆっくり目のテンポで、温かな音色で、丁寧に抑揚を紡ぐやり方が、神への奉仕のようにも聴こえ、深い祈りが感じられた。トランペットが入り、華やかな音響になる楽曲での、溶け合う響きの美しさも素晴らしかった。決して派手な音にはならず、こうしたところからもひたむきな神への賛美が感じられた。そしてこれは、プレイヤー達の卓越した技術が支えていることも間違いない。
フェルトホーヴェンの演奏からは、神の威光をことさら大きく見せつけるようなところが全くなく、清貧の精神に貫かれていると言っていいほどの謙虚さを感じる。"Agnus Dei"のアルトのソロ、今回はソリストが女声(オイツィンガー)だったので、カウンターテナーのストイックな歌ではない、豊饒に包み込むような歌を密かに期待していたが、これはカウンターテナー以上にストイックな歌唱で、まさに死に行くキリストを見つめて立ち止まる様子が歌われていた。そもそもここで歌に酔いしれたりするのは不謹慎で、共にキリストの犠牲を我が身のものとして受け止め、祈らなければならない、と諭されているような厳しささえ感じた。そんなわけで、最後の"Dona nobis pacem"の合唱からも、天に昇るような幸福感をもたらしてはもらえなかった。
今夜のロ短調ミサを聴いて、これがいかに優れたホンモノの演奏であるかといういうことは十分に感じ、理解できたと思う。とても美しいとも感じた。だが、そこから真の感動を得るには、このミサの典礼文が伝える宗教的な意味を共有し、それに心から共感していることが求められているような気がしてしまい、そんな信仰は持ち合わせないボクには少々入っていけないものを感じた。ソロはもっと艶やかなベルカントで歌って欲しいし、合唱も少し大袈裟なくらい感動的に歌ってくれたほうがいい。ロ短調ミサは、豊かな響きで、陶酔できるほどに包み込んでくれるような、俗っぽいくらいの演奏が個人的には好きだ。
フェルトホーフェン指揮オランダ・バッハ協会合唱団&管弦楽団「ヨハネ受難曲」(2008.2.25 紀尾井ホール)