
悪貨は良貨を駆逐する。・・・グレシャムの法則はしばしば経済で話題になったり、汚染に対する警鐘などのお話で、先のフレーズはよく耳にしたりします。
ソモソモ金本位制で、金そのものが貨幣な場合その貨幣の金の純度(貨幣に含まれている金の密度)で、その貨幣の価値が決まっていて例えば、その貨幣の金の純度を変えてしまえば、貨幣の価値が変わって信頼が崩れて物価が上がってしまったり・・・・。
商品を安く仕上げて高く販売するために、手間ヒマを省いたり公害を垂れ流したりも商品の価値に問題が現れて、大きな問題になったり・・・。
とにかく経済性・利潤の追求をするあまりに、低きに流れようとすれば、悪影響を及ぼしたりします。
また、経済の世界では大国が小国を駆逐しようとする事は、今まで往々にして繰り返されて来ましたし、これからも続くのかもしれません。
その様な大国の振る舞いはまるで、過去の植民地政策や社会主義諸国の囲い込み的なイメージに通じる様な気もします。
力を持つ者はそれで生産性が高まれば余剰が生まれて、利益を追求する事が出来るので、そのために背景の力を利用して、経済的に優位に立とうとするのは一つの現象。
植民地も社会主義の囲い込みも、過去の香ばしくはないケースの様で、今ではすでに過去の遺物になったのでは、とも感じていましたが性懲りのない独裁的な国では如何なモノなのでしょうか・・・?
本来の原初的なというか、需要と供給のシンプルな発想でのみでの商品の価値とかとは(少々ややこしい言い回しになりますが)、それとは別の関税とか取引での交渉とかが、本来のシンプルな価値にうまく繋がりが保てないと、本来のシンプルな価値に比べてより価値の低い商品になって結局、高く買わされたり、本来価値ある商品が市場から消えてしまったりして、コレってヤッパリ都合がヨロシクありません・・・?
経済大国は、これまでの純粋な価値関係とは別の、国力にモノを言わせた外交的パワーを駆使して、ゴリ押し的な操作で経済的にも格差を広げようと注力したりします。
この様な外交・交渉も大きな範疇でくくれば、一つの経済政策なのかもしれませんが、狭い範囲での物々交換から貨幣経済に進んできた頃の、価値は場所を異にすれば価値が変わる素朴な交易の様な価値ともまた、色合いの異なる一種独占的な、別のパワーを利用しての外交・交渉の色合いが加味されたイメージがあって、添えが原因で異臭を放っている様にも感じます・・・。
ここで小国が、大国のその様な外交を上手くしのいで生き続けるために、希少価値もしくは、多様性に関わる事で生き抜く手段を考えたりして、工夫をしなければいけなくなったり・・・?
今の世でも、単純に少ないモノに価値がある場合はあるのだし、商品や流通、企業の単一化は、利便性が向上する場合もあるけれども反面、澱(よど)みも産まれやすく、コレマタ悪臭を漂わせて後々、脆弱性も産み出していずれ劣化していくような出来事は、よく似たケースを歴史が物語っているとも思うのですが・・・?
どちらにしろ独占とか単一化とかは、いずれ経済を駆逐してしまいます。
そこから見え隠れする横柄に振る舞うように見える態度は、いずれ異臭を放って周囲にネガティブな空気を漂わせて、とても気分の良い状況ではない事になるのでしょう・・・。
その様な傲慢の露呈は遠からず、我身を亡ぼすのが世の常(?)、力なき周囲の叱責の声に耳を傾けられなくなった時、それがアリの一穴にも通じる事にもなるのでしょう・・・。
歴史上、夏の傑王、殷の紂王、周の厲王は易姓革命の顕著な例で記録を残し、フランス革命や、ロシア革命もご同様によく似たケースとして、教科書でも紹介されたり・・・?
末喜(ばっき)や妲己(だっき)、褒姒(ほうじ)の様な絶世の美女と乱れた王様の典型的な傾国のお話とか、余りにも臣民あるいは農奴と乖離しすぎた王家の末路とか・・・。それらを題材にした書籍は飽くことなく出版されて、今なお読み継がれています。
映画「キング・コング」も何となく重なる様な気もしたり・・・?
例えば鉄鋼、純鉄よりも炭素が少量含まれれば、硬くなったり、ニッケルを加えれば錆びにくくなったり・・・。これは極論気味だけれど、時として単一化が、弱点にもなり得る事があって、少ない成分の残留で鉄は性質が大きく変わったりするのも、当たらずとも遠からず的な、たとえになるかもしれません。
自然界の法則ならば少数派はいずれ、絶滅の危機が危惧される可能性が高くなるのは必然です。
これが人の営みの自由貿易では、経済力や国力や大きい者が断然有利になって、一方の力なき者たちは、生き残る余地を考えなければならなくなり、色々な工夫が要求されたりもします。
つまり、力なき者たちが生き残るための一つの手立てが必要になって来て、例えば商品に付加価値とか伝統や習慣のような価値に見合う商品、地産でないと意味がない商品とか、何かに特化しそれを足がかりにして、存命を図らないといけない・・・。
例えば、大航海時代前の胡椒とか、絹、ジャコウ・乳香、などは当時代替するモノがなかったから高値がついても、売れたりしました。
人間の世界では本音と建前があって、自然界ではそんな建前はない・・・。それはある意味、気取る必要がないからなのかもしれません。
その時の建前とは、優位性とか覇権掌握のための人間にのみ通用する武器として用いられたりして、力で抑え込もうとする大国が小国の生殺与奪権を握らんがための手段にもなったりして、その様な建前論で大国は、経済的優位性を確保しようとする・・・。
自然界では例えば大昔、隕石の衝突が巨大生物の恐竜を絶滅させて、当時矮小な哺乳類の繁栄を促す結果になったり、ウィルスの変異は多細胞な生物以上に時短で可能なので、ワクチンに対抗する如く、インフルエンザが中々絶滅しない様に、まだまだ人知の及ばない謎の小さきものの反抗するたとえも、考えられそうです。
生物界での少数派や弱者は、紛らわしさや隠ぺいを活用して存在感を目立たぬ様にして、多数派の戦略から身を守る事も知られています。
単なる巨大化には疎漏が悩みの種として歴史上、様々なお話が残ってもいます。ソコにはアリの一穴から瓦解の可能性も秘めている事が、示唆されていたりとイメージされるのは、くどい様ですが如何にも否めない・・・。
大きな国こそ正々堂々と、小国の同意を取り付けらる様に努力すべきなのかもしれません。
世界一になるのが正義なのか、共存共栄で大国こそが、多様性を死守しないと、降りかかる火の粉にさらされる表面積は大国の方が、広い様な気がするのですが・・・。














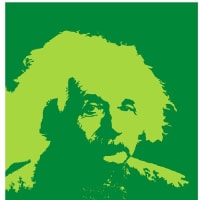
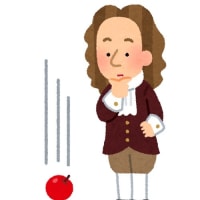




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます