今日もブログをカチャカチャ・・・!
更新、更新と精を出す日々。
この国の私たちは、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字を駆使してアレしたりコレしたり、ブログを書いたり・・・というか、キーボード操作・・・?
毎日活用している、文字・漢字。
今やその成り立ちに気にもせず。情報を収集したり、発信したり・・・!
それは、いたし方のないご時世・・・?
漢字、実は今その起源は 説文解字(せつもんかいじ)という中国の古~い文献が主流となって、それを活用している国々では気にせずに、情報の通信をしているのが常態となっているテイ・・・?
この字典を綴ったのは、許慎(きょしん)。
2,000年以上も前の中国大陸が 漢 と言われていた時代の文学者。
漢字は甲骨文字が祖となった文字。その解釈をしたのが、説文解字。
その説文解字に2,000年以上も後になって、それって違うんじゃない・・・?と、研究した学者が、白川 静 博士。
当初、彼の成果に世間は無視に近い状態だった。
けれども、月日が重なるにしたがって、白川 静 博士の研究成果の絶大な説得力、洞察力は漢字の見直しを迫った。
そこで情報の通信の源の一つ、文字 の成り立ちを根本から研究された件についての、チョット出しブログという事で本日の日記を・・・。
だって、面白いのだから・・・ツマリ、ソシュールや許慎の様な歴史的偉人を向こうに回した感のする、孤高のイメージがぬぐい切れない 白川 静 博士の人生を賭した研究の成果は、強烈な磁力があるから・・・。
というのもそも、甲骨文字は象形文字。映像の様に視覚に訴えかける表現。ことばもまた概念の映像ともいえると・・・。ことばは経年で変化して行くけれども、文字は草創期における概念の世界が、視覚的形象として定着して、通時性を保っている事を正に証明した偉人が、白川 静 博士だと思うから・・・。少々、小難しい表現になったけれども・・・m(_ _)m
という事で、突然なんだけれど、名 について。
名は説文解字では、夕暮れに人影が見えずらくなった頃に呼びかけるという発想で生まれた文字だとされていたそうで・・・?
それを白川博士は、甲骨文字ではそうではなくて、名の夕の部分はニクヅキを現していて、神に奉納する肉を意味し、名の口の部分はサイと言って、祈りを納めた器を意味し、その合体が 名 であると・・・。次に、その他の口の付く漢字について・・・。
吉・・・士は刃物、口は祈りを込めたモノを入れた箱。刃物は除霊作用があったとされる。
吉とは良い事の状態を表す文字。
害・・・ウ冠は屋根。真ん中の圭の様な字は昔は、突き抜けていた。
つまり針を刺した状態を指す。
奉納するサイ(口)に禍をなそうとしている状態を表すと・・・。
可・・・口に鞭を向けている様子。叱咤して悲願成就をしている様を表していると・・・。
口 以外に・・・弓矢の 矢 では・・・。
矢・・・族は一族を示す矢を使っている。矢は武器であると同時に、ある集合の印を象徴する。
矢が地面に突き刺さって至。
矢は邪霊を退ける効果があるとされた。
屋・・・屋は除霊された場所。室も安心出来る空間。
ソコには突き刺さった 矢 が、すなわち 至 が存在している。
・・・とマァこんな具合。
くどい様ですが、甲骨文字とは神との対話のために生まれた文字だった。祈り、呪術にさへ昇華しようとした、強い願い・思いが生んだヒトが創り出した産物。
その時、甲骨文字は記号 なので、記号だけでは味気ない 文字 への憧憬も込めた日記なのですが・・・(^^ゞ
面白い小説もついでに、ご紹介。二度目のご紹介m(_ _)m

沈黙の王 (文春文庫)

漢字百話 (中公文庫) [ 白川静 ]














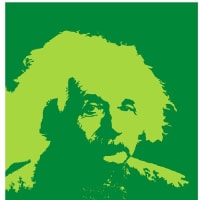
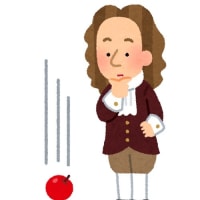




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます