有名な昔の中国でのお話しです。
その国には、ある国から同盟の証としてある宝物が贈られて来ました。隣国の超大国はその情報を嗅ぎ付けて、「我が国に何の報告もなく不遜なる振る舞いである」どうしたものか・・・?
と、その国の王はこのことを協議にかけました。それではこういたしたら如何でしょう、という者が現れました。どうするのかといいますと、「我が国の十五の城をもってその宝と交換したい。」と交渉するのです。
そしてその国との会合を設けその折に、宝を武力にものをいわせて強引に奪い取ってやるのですよ。そうすれば、その国のフヌケ具合と我が国の天下を布武する意気込みが世間に知れ渡り、一石二鳥ではございませぬか。ということになったのです。隣国の超大国は、早速その国へ遣いを出して打診しました。
さて、この難問にホトホト困り果てた宝物を受け取ったその国の王は家臣団に「誰かかの大国へ行く者は居らぬのか」という問いをかけましたが、答えられる者は中々現れません。しかし一人の家臣、ビューケンがそれに応えたのです。
ビューケンは、「我が家の客人に、リンショウジョなる者が居ります。彼ならこの問題を解決出来ることでしょう」と進言するのです。しかしてその王はリンショウジョを召し出し、この大役を任せるのです。
この時点でリンショウジョは無役の庶子にもかかわらず、王に謁見しこの大役を受けることになるわけです。隣国の超大国は、約束を反故にすることで有名でした。つまりは傲慢で居丈高、武力で恫喝をも厭わないお国柄とでも申しましょうか・・・。そんな大国への訪問は、下手をすれば死を意味するのは明らかです。
リンショウジョは王の命を受け隣の超大国へ・・・。
さて、隣の超大国の王の面前です。彼は宝物を王に手渡しました。すると王は横にいる家臣団に、「これがかの宝物よ」といい、家臣たちに見せびらかすのでした。その行状を見て、リンショウジョはおもむろに、「王よ、実はその宝にはわかりにくいのですが、瑕(きず)がございます。それをお示しいたしましょう」と言いながら、宝を取り戻すと、怒髪天を突く形相と共に宝を持ったまま、後ずさりして柱に寄りかかるのです。
そして王の非礼なる態度と、我が主君に対する詐称の思惑あるをツラツラと述べ、「我が血流と共にこの宝物をこの場で木っ端微塵に砕いてくれましょう」と声高に叫びました。
するとこの超大国の王は驚愕の色を満面に露わにし、「まー待て、そなたの言い分は合い判った。この非礼を詫び、如何様にもするであろう」と言ってしまったのです。
後はリンショウジョのペースで事は運んで参ります。結局その大国の王の約束は反故にされるのが判っている彼は、先にその宝を本国へ戻しておいて、自分は残るのです。この時点でリンショウジョは死を覚悟していました。
しかし、この大国の王も飾りではなかったのです。リンショウジョの度量と命懸けの忠心にほだされ、かつ自国の尊大さを周りの国に示すかのように帰国させるのでした。
璧(へき)を完(まっとう)す。完璧の語源となったワケですネ。さて、この話には続きがあります。
時代は少々遡り、唐挙(とうきょ)のお話から。彼ほど凄まじい占いをした人はいないでしょう。ソレが史実なら・・・。
当時、趙(ちょう)という国の武霊王(ぶれいおう)は中国統一を企てるほどの才能と力を有していました。ただ自分の後継者すなわち嗣王選びに迷いを生じ、既に名を馳せていた人相を診て未来を判断するという唐挙に依頼したわけです。
彼は、武霊王の質問にすべて回答し、趙を出ることになりました。その折に武霊王の命を受け、唐挙を迎え入れる使者となった李兌(りたい)にだけ唐挙は、気になる一言を告げたのです。つまり、武霊王の寵愛を最も多く受けている嗣王は武霊王の思惑通りにその席(次代の王)に就きますが、武霊王はその折に落命し、李兌自身はその出来事の中で天運を掴む好機を手に入れることが出来る。
唐挙は李兌にだけそう言い残して、帰途するのです。李兌はゾットしました。誰憚(はばか)る事もない武霊王が、家臣団を思惑通りに操り、隙の一つもない鉄壁の政治を遂行している、今や天運をほしいままにしている武霊王に、降りかかる災難とは。何なのか。
当時の趙は武霊王の富国強兵策が功を奏し、国力も中華で最も充実していた一国でもあったのです。何もかもが上手く行き、未来の見通しは明るいものであったのでした。武霊王自身子宝にも恵まれ、当初は長男を嗣王にという当時の慣例に従い、時は流れていたのですが、その子が成長するに従いその資質に疑問を抱き、次男や三男が誕生するにつれ、武霊王の中で嗣王選びに迷いが生じ始めたのです。
そしてこの度の、唐挙の招聘に至るのでした。時は流れ、その嗣王を決定し、宣言する日も迫りつつある日、武霊王は再度唐挙を招き、確固たる確信を得るがため会談の場を設けます。唐挙の回答は以前のそれと寸分違わないものでした。
再び、唐挙の世話をすることになった李兌は、かつて自分に話してくれた内容の真意を、唐挙に吐露しようとしました。彼は、そんなことも申しましたか。と言う様な面持ちで彼の話を聞いて返事をしたのです。
「心配には及ばぬ。李兌殿の相は当時のまま、即ち好機は訪れる。」と言う様な回答をしました。何が起こるのか、自分はどう対処すればよいのか。そこが知りたかった李兌ではありましたが、肝心なその事を聞き出せなかったのです。
そして事件は勃発し、唐挙の予想通り武霊王は落命するのです。その顛末は結局嗣王の選択に迷いを生じた時点で、既に発生していたのです。彼の息子たちには、有力な側近がそれぞれに配属されて、互いに次の座を狙っていたのです。
息子たち自身もそうであったように、側近の有力者たちが武霊王の心の変移に右往左往させられた挙句、疑心暗鬼に陥り、次王争奪戦が表面化して結果的に、長男は武霊王自身に殺され、武霊王は餓死させられたのです。
そこには李兌と公子成の勢力が大きく関わり、争奪戦の勝利者となった恵文王は、父を見殺しにする事により王位に就いたというどうしようもないトラウマをここで、身に纏うことになるのです。
しかし彼の耐え忍ぶという精神は、善政に通じることにもなり有能な家臣の発掘にも繋がることにもなっていきます。禍福はあざなえる縄の如し。
かのリンショウジョと廉頗(れんぱ)将軍のお話へすすみます。この国の王の名は恵文王。彼の父は武霊王。
武霊王は胡服騎射を武卒に命じた王。つまり馬に乗り胡(外国)の服を着て闘うスタイルを命じたのです。
当時の先進国において、実は、そのスタイルは屈辱的な格好だったのです。しかし険峻な戦地での戦の場合、これまでの戦車(馬に牽かせる)仰々しさでは、機動力におくれをとる場合があり不利である。と考えた武霊王は、家臣団の反対を押し切り、これを実行に移したのです。
服装すら騎乗用に変更したわけですが、これが誇りある武将に不評であったのです。当時の戦士は、日本の着物のような、あるいはスカートのような装いが戦闘服でありました。それを、今で言うズボンに履き替えることは、大変勇気のいることだったのです。
そもそも、外国を胡という言い方の裏には、自分たちは世界の中心で最も優れた民族であり、周辺の国々は、作法や礼儀もなく野蛮で、卑しい民の集まりであるという、中華思想から産まれた蔑みを込めた言い方であったのです。
しかし、胡服騎射は功を奏し、武霊王は周辺諸国から懼れられるほどの力を持つにいたるのです。更に、しかし、彼は非業の死を遂げるのです。李兌(りたい)と公子成(こうしせい)による、政略で餓死させられるのです。
この事件に対し、恵文王はどうしようもない負い目を生涯、持ってしまうのですね。つまり、父を見殺しにしたと。彼は、耐えること忍ぶことを覚えました。そのような彼の元には、有能な人々が集まるようにもなったのです。
楽毅や趙奢(ちょうしゃ)等々。完璧事件のその後、大国の仕返しとも言える会合にもその辣腕を発揮したリンショウジョは、恵文王の絶大なる信頼を勝ちとり、異例の出世をしたのです。しかし、当然のように既成権力者の妬み嫉みは彼の身にも、振り被さってまいります。
厄介なのが、廉頗(れんぱ)将軍でした。彼は他国にも名の通った将軍なのですが、彼にしてさへ「舌先三寸で、窮地を凌いだだけで、あのような出世とは片腹痛いわ。我等などは我が身を犠牲にして、忠誠を誓って居るのに、あのような者の卑賤の出の風下に何故、甘んじなければならぬのか」と所構わず豪語する有様なのでした。
そんな彼を避けるようにリンショウジョは、往来で廉頗将軍の一隊と遭遇するような事があった場合、道をあけて、コソコソとした態度を取る様になり、お伴をしていた彼の家臣はその行動に呆れ返り、私をクビにしてくれとリンショウジョに愛想をつかすのでした。
しかし、リンショウジョは彼に言います。「お主は、廉頗将軍と例の大国の王のどちらを怖れるか?」「それはもう大国の王に決まっているではありませんか」と家臣。
「私はその大国の王に対し堂々と対峙して参った。どうして将軍のことを恐れなどしよう。私の恐れて居るのはな、我ら二人が仲違いをしてどちらか一方でも倒れるようなことが起きてもみよ。忽ちにしてかの大国よりの侵入をゆるす事になるのだぞ」それを聞いて家臣は気が付き、自分の不明を詫びたのでした。
その話が何処からともなく、廉頗の耳に届いたのでした。彼は賓客を伴って肌ぬぎし、茨の鞭を負いリンショウジョの屋敷を訪れるのです。当時の謝罪の様式であったのですね。
廉頗はまるで地が血で染まるように深く頭を下げ、リンショウジョに詫びるのでした。リンショウジョはやさしく手を差し伸べて、彼らを屋敷内へ導いたのです。そして、語る訳です。
「たとえ、このクビに禍が降りかかるような疑惑が世間を賑わすような事があっても、将軍と私は共に"信"を忘れないでいましょう。」刎頚(ふんけい)の交わりです。
その国には、ある国から同盟の証としてある宝物が贈られて来ました。隣国の超大国はその情報を嗅ぎ付けて、「我が国に何の報告もなく不遜なる振る舞いである」どうしたものか・・・?
と、その国の王はこのことを協議にかけました。それではこういたしたら如何でしょう、という者が現れました。どうするのかといいますと、「我が国の十五の城をもってその宝と交換したい。」と交渉するのです。
そしてその国との会合を設けその折に、宝を武力にものをいわせて強引に奪い取ってやるのですよ。そうすれば、その国のフヌケ具合と我が国の天下を布武する意気込みが世間に知れ渡り、一石二鳥ではございませぬか。ということになったのです。隣国の超大国は、早速その国へ遣いを出して打診しました。
さて、この難問にホトホト困り果てた宝物を受け取ったその国の王は家臣団に「誰かかの大国へ行く者は居らぬのか」という問いをかけましたが、答えられる者は中々現れません。しかし一人の家臣、ビューケンがそれに応えたのです。
ビューケンは、「我が家の客人に、リンショウジョなる者が居ります。彼ならこの問題を解決出来ることでしょう」と進言するのです。しかしてその王はリンショウジョを召し出し、この大役を任せるのです。
この時点でリンショウジョは無役の庶子にもかかわらず、王に謁見しこの大役を受けることになるわけです。隣国の超大国は、約束を反故にすることで有名でした。つまりは傲慢で居丈高、武力で恫喝をも厭わないお国柄とでも申しましょうか・・・。そんな大国への訪問は、下手をすれば死を意味するのは明らかです。
リンショウジョは王の命を受け隣の超大国へ・・・。
さて、隣の超大国の王の面前です。彼は宝物を王に手渡しました。すると王は横にいる家臣団に、「これがかの宝物よ」といい、家臣たちに見せびらかすのでした。その行状を見て、リンショウジョはおもむろに、「王よ、実はその宝にはわかりにくいのですが、瑕(きず)がございます。それをお示しいたしましょう」と言いながら、宝を取り戻すと、怒髪天を突く形相と共に宝を持ったまま、後ずさりして柱に寄りかかるのです。
そして王の非礼なる態度と、我が主君に対する詐称の思惑あるをツラツラと述べ、「我が血流と共にこの宝物をこの場で木っ端微塵に砕いてくれましょう」と声高に叫びました。
するとこの超大国の王は驚愕の色を満面に露わにし、「まー待て、そなたの言い分は合い判った。この非礼を詫び、如何様にもするであろう」と言ってしまったのです。
後はリンショウジョのペースで事は運んで参ります。結局その大国の王の約束は反故にされるのが判っている彼は、先にその宝を本国へ戻しておいて、自分は残るのです。この時点でリンショウジョは死を覚悟していました。
しかし、この大国の王も飾りではなかったのです。リンショウジョの度量と命懸けの忠心にほだされ、かつ自国の尊大さを周りの国に示すかのように帰国させるのでした。
璧(へき)を完(まっとう)す。完璧の語源となったワケですネ。さて、この話には続きがあります。
時代は少々遡り、唐挙(とうきょ)のお話から。彼ほど凄まじい占いをした人はいないでしょう。ソレが史実なら・・・。
当時、趙(ちょう)という国の武霊王(ぶれいおう)は中国統一を企てるほどの才能と力を有していました。ただ自分の後継者すなわち嗣王選びに迷いを生じ、既に名を馳せていた人相を診て未来を判断するという唐挙に依頼したわけです。
彼は、武霊王の質問にすべて回答し、趙を出ることになりました。その折に武霊王の命を受け、唐挙を迎え入れる使者となった李兌(りたい)にだけ唐挙は、気になる一言を告げたのです。つまり、武霊王の寵愛を最も多く受けている嗣王は武霊王の思惑通りにその席(次代の王)に就きますが、武霊王はその折に落命し、李兌自身はその出来事の中で天運を掴む好機を手に入れることが出来る。
唐挙は李兌にだけそう言い残して、帰途するのです。李兌はゾットしました。誰憚(はばか)る事もない武霊王が、家臣団を思惑通りに操り、隙の一つもない鉄壁の政治を遂行している、今や天運をほしいままにしている武霊王に、降りかかる災難とは。何なのか。
当時の趙は武霊王の富国強兵策が功を奏し、国力も中華で最も充実していた一国でもあったのです。何もかもが上手く行き、未来の見通しは明るいものであったのでした。武霊王自身子宝にも恵まれ、当初は長男を嗣王にという当時の慣例に従い、時は流れていたのですが、その子が成長するに従いその資質に疑問を抱き、次男や三男が誕生するにつれ、武霊王の中で嗣王選びに迷いが生じ始めたのです。
そしてこの度の、唐挙の招聘に至るのでした。時は流れ、その嗣王を決定し、宣言する日も迫りつつある日、武霊王は再度唐挙を招き、確固たる確信を得るがため会談の場を設けます。唐挙の回答は以前のそれと寸分違わないものでした。
再び、唐挙の世話をすることになった李兌は、かつて自分に話してくれた内容の真意を、唐挙に吐露しようとしました。彼は、そんなことも申しましたか。と言う様な面持ちで彼の話を聞いて返事をしたのです。
「心配には及ばぬ。李兌殿の相は当時のまま、即ち好機は訪れる。」と言う様な回答をしました。何が起こるのか、自分はどう対処すればよいのか。そこが知りたかった李兌ではありましたが、肝心なその事を聞き出せなかったのです。
そして事件は勃発し、唐挙の予想通り武霊王は落命するのです。その顛末は結局嗣王の選択に迷いを生じた時点で、既に発生していたのです。彼の息子たちには、有力な側近がそれぞれに配属されて、互いに次の座を狙っていたのです。
息子たち自身もそうであったように、側近の有力者たちが武霊王の心の変移に右往左往させられた挙句、疑心暗鬼に陥り、次王争奪戦が表面化して結果的に、長男は武霊王自身に殺され、武霊王は餓死させられたのです。
そこには李兌と公子成の勢力が大きく関わり、争奪戦の勝利者となった恵文王は、父を見殺しにする事により王位に就いたというどうしようもないトラウマをここで、身に纏うことになるのです。
しかし彼の耐え忍ぶという精神は、善政に通じることにもなり有能な家臣の発掘にも繋がることにもなっていきます。禍福はあざなえる縄の如し。
かのリンショウジョと廉頗(れんぱ)将軍のお話へすすみます。この国の王の名は恵文王。彼の父は武霊王。
武霊王は胡服騎射を武卒に命じた王。つまり馬に乗り胡(外国)の服を着て闘うスタイルを命じたのです。
当時の先進国において、実は、そのスタイルは屈辱的な格好だったのです。しかし険峻な戦地での戦の場合、これまでの戦車(馬に牽かせる)仰々しさでは、機動力におくれをとる場合があり不利である。と考えた武霊王は、家臣団の反対を押し切り、これを実行に移したのです。
服装すら騎乗用に変更したわけですが、これが誇りある武将に不評であったのです。当時の戦士は、日本の着物のような、あるいはスカートのような装いが戦闘服でありました。それを、今で言うズボンに履き替えることは、大変勇気のいることだったのです。
そもそも、外国を胡という言い方の裏には、自分たちは世界の中心で最も優れた民族であり、周辺の国々は、作法や礼儀もなく野蛮で、卑しい民の集まりであるという、中華思想から産まれた蔑みを込めた言い方であったのです。
しかし、胡服騎射は功を奏し、武霊王は周辺諸国から懼れられるほどの力を持つにいたるのです。更に、しかし、彼は非業の死を遂げるのです。李兌(りたい)と公子成(こうしせい)による、政略で餓死させられるのです。
この事件に対し、恵文王はどうしようもない負い目を生涯、持ってしまうのですね。つまり、父を見殺しにしたと。彼は、耐えること忍ぶことを覚えました。そのような彼の元には、有能な人々が集まるようにもなったのです。
楽毅や趙奢(ちょうしゃ)等々。完璧事件のその後、大国の仕返しとも言える会合にもその辣腕を発揮したリンショウジョは、恵文王の絶大なる信頼を勝ちとり、異例の出世をしたのです。しかし、当然のように既成権力者の妬み嫉みは彼の身にも、振り被さってまいります。
厄介なのが、廉頗(れんぱ)将軍でした。彼は他国にも名の通った将軍なのですが、彼にしてさへ「舌先三寸で、窮地を凌いだだけで、あのような出世とは片腹痛いわ。我等などは我が身を犠牲にして、忠誠を誓って居るのに、あのような者の卑賤の出の風下に何故、甘んじなければならぬのか」と所構わず豪語する有様なのでした。
そんな彼を避けるようにリンショウジョは、往来で廉頗将軍の一隊と遭遇するような事があった場合、道をあけて、コソコソとした態度を取る様になり、お伴をしていた彼の家臣はその行動に呆れ返り、私をクビにしてくれとリンショウジョに愛想をつかすのでした。
しかし、リンショウジョは彼に言います。「お主は、廉頗将軍と例の大国の王のどちらを怖れるか?」「それはもう大国の王に決まっているではありませんか」と家臣。
「私はその大国の王に対し堂々と対峙して参った。どうして将軍のことを恐れなどしよう。私の恐れて居るのはな、我ら二人が仲違いをしてどちらか一方でも倒れるようなことが起きてもみよ。忽ちにしてかの大国よりの侵入をゆるす事になるのだぞ」それを聞いて家臣は気が付き、自分の不明を詫びたのでした。
その話が何処からともなく、廉頗の耳に届いたのでした。彼は賓客を伴って肌ぬぎし、茨の鞭を負いリンショウジョの屋敷を訪れるのです。当時の謝罪の様式であったのですね。
廉頗はまるで地が血で染まるように深く頭を下げ、リンショウジョに詫びるのでした。リンショウジョはやさしく手を差し伸べて、彼らを屋敷内へ導いたのです。そして、語る訳です。
「たとえ、このクビに禍が降りかかるような疑惑が世間を賑わすような事があっても、将軍と私は共に"信"を忘れないでいましょう。」刎頚(ふんけい)の交わりです。














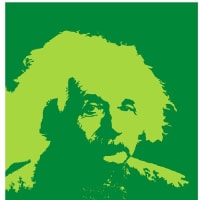
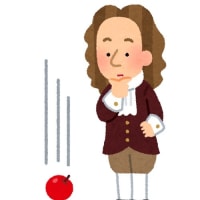




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます