![]() 動物奇譚
動物奇譚
(2) 酔っ払い動物達…2
人類の祖先が木の上で偶然(アルコール耐性遺伝子)を獲得したことによって、動物最強の酒豪になった。確かに欧米やアフリカ系民族には飲んですぐ顔が赤くなるような「酒に弱い体質」の人は殆どいないが日本や中国、韓国にはワインのコルクを嗅いだだけで、顔が赤くなる下戸も多数いる事も又事実である。何故地球のごく一部地域、極東の人達が突然酒に弱くなってしまったのか、その謎を解く有力な仮説を中国の人類学者が打ち立てた。
酒を飲むと、アルコールは肝臓で分解されて、悪酔いや頭痛、動悸の原因ともなる 「アセトアルデヒド」という物質に変わる。この物質は体の細胞を傷つけ、癌など病気のリスクを上昇させる危険な物質で、酒を時には「毒」にもしてしまうのであるが、肝臓で(アルデヒド脱水素酵素)により(酢酸)に分解され、血液によって全身を巡り水と二酸化炭素に分解され、汗や尿、呼気中に含まれて外へ排出されると言う経過を辿る。
中国の研究者は祖先の⾻に残る遺伝⼦の情報から「アセトアルデヒド分解遺伝⼦」を読み解き、凡そ6000年以上前、この分解遺伝⼦の働きが弱い祖先が突如中国に出現した事を突き止めた。調査を進めると「酒に弱い遺伝⼦」の広がり⽅のパターンが、アジアでの「稲作」の広まり⽅とよく似ていることに気付いたのである。 稲作は中国の⻑江流域で始まり、先ず北東部へ、次に東南部へ、その後東アジア⼀帯へと広がった。この稲作の分布と、「酒に弱い遺伝⼦」の分布を重ね合わせると、ほぼ⼀致したのである。一致理由には幾つかの有⼒仮説があるが、その中で尤もらしいと考えられているのが以下のシナリオである。 舞台は、6000年以上前の中国。稲作に適した⽔辺に 多くの⼈が集まって暮らし始めていたが、当時は衛⽣環境も悪く、⾷べ物に病気を引き起こし生命に関わる様な悪性微⽣物などが付着することが多かったが、そんな時、意外にも⽶から造っていた「酒」が役⽴ったと考えられる。アセトアルデヒド分解遺伝⼦の働きが弱い祖先が酒を飲むと、体内には分解できない猛毒のアセトアルデヒドが増えていく。しかし、その毒が悪い微⽣物を攻撃する薬にもなった可能性があるというのである。こうして、「酒に弱い遺伝⼦を持つ⼈の⽅が、感染症に打ち勝って⽣き延びやすかった」 というのが、有⼒な仮説の⼀つで日本の学者もこの仮説を推奨している。 つまり稲作地帯の人達は、酒がもたらす毒まで利⽤し病原菌から身を守ろうと、「酒に弱くなる道を選んだ」可能性があると言うのである。 この「酒に弱い遺伝⼦」が、3000年ぐらい前に稲作⽂化と共に朝鮮半島経由⽇本列島に渡来し、酒に強い縄文人に交じり込んで、今では⽇本⼈のおよそ4割が 「酒に弱い遺伝⼦タイプ」になったと考えられる。中国人の52%、韓国人の30%、も同様である。 以上から日本人の酒豪はインドアーリア系か縄文人の血を引く人間だとの説に結び付く。
酔っ払い動物達に話を戻そう。世界には鳥からゾウまで、自然から得る天然のアルコールで、日常的に酔っぱらっている野生動物がいる。

 大きな冠羽や黒いアイマスクのような模様など、印象的な羽毛で知られる北米の鳥であるヒメレンジャクは、数カ月にわたって果実だけを食べるという珍しい特徴を持っている。果実はエネルギー源として優れているが、熟しすぎた果物やベリーは目に見えない脅威となる。 天然の酵母が熟した果実を発酵させ、糖の分子をエタノールと二酸化炭素に変える。果実が腐り始めていなければ、食べても安全だが、ヒメレンジャクを(酔っ払い)にしてしまう。酒豪ではない彼等は、酔っぱらうと、反射神経が鈍くなり、判断力が低下し、補食されたり、車や電信柱、窓ガラスにぶつかって大怪我をすることもあると言う点では、渋谷に屯する人間達と何等異なるところが無い。動画等からの最近の研究では、半野生動物やペットを含む55種の鳥がアルコールを飲んでいることがわかった。動画の多くは、オウムやカラスなどのいわゆる「賢い」鳥が人の飲み物を口にするというものだったが、彼等が酔っぱらったどうかは定かではない。
大きな冠羽や黒いアイマスクのような模様など、印象的な羽毛で知られる北米の鳥であるヒメレンジャクは、数カ月にわたって果実だけを食べるという珍しい特徴を持っている。果実はエネルギー源として優れているが、熟しすぎた果物やベリーは目に見えない脅威となる。 天然の酵母が熟した果実を発酵させ、糖の分子をエタノールと二酸化炭素に変える。果実が腐り始めていなければ、食べても安全だが、ヒメレンジャクを(酔っ払い)にしてしまう。酒豪ではない彼等は、酔っぱらうと、反射神経が鈍くなり、判断力が低下し、補食されたり、車や電信柱、窓ガラスにぶつかって大怪我をすることもあると言う点では、渋谷に屯する人間達と何等異なるところが無い。動画等からの最近の研究では、半野生動物やペットを含む55種の鳥がアルコールを飲んでいることがわかった。動画の多くは、オウムやカラスなどのいわゆる「賢い」鳥が人の飲み物を口にするというものだったが、彼等が酔っぱらったどうかは定かではない。
ヘラジカはアルコール耐性が弱く、地上に落ちて発酵した大好物のリンゴを食べては酔っ払って木にぶつかるなんてことが屡々ニュースになり、カナダのローカル紙やテレビを賑わすことになる。
アフリカ象も同様でマルラの木の発酵した果実を食べて酔っぱらったという報告は、一般的な文献や科学的な文献にもあふれている。ヘラジカやアフリカ象はアルコールを代謝しにくい遺伝子を持っており、巨大な体でも発酵した果実で酔うことを示している。勿論、彼等は快楽を求めているわけではなく、ただ空腹なだけであると報告は述べている。只ヘラジカ、ゾウ以外の酔っ払い動物の中には空腹を満たす為だけではなく、快楽を求めてと言うケースも考えられるという。
アフリカ部族の中にはマルラの木の実を重要な食料源にして居る人達がいるが、象以外にもアフリカ草原の草食動物はこの木の実が大好物で、時には争奪戦が勃発する。 マルラの木は密生せず草原等で18メートルにも達する高木で,実を自由に食べることが出来るのはヒヒやキリンに限られる。そこで頼りになるのが象達、彼等は時に草食動物を集め、大宴会を催す。この木の下でヘベレケに酔っぱらい、酩酊状態の(象、サイ、キリン、ダチョウ、ヒヒ、イノシシ、鳥達)の様子が観察されて居り、(African Animals Getting Drunk Off Ripe Marula Fruit)という動画で視聴可能である。
最後に北米の草原に住む(プレーリーハタネズミ)の話。
 彼等は1日にワイン15本分に相当する量を飲むことも出来る程の酒豪であるが、げっ歯類としては珍しい一夫一婦制で、大のアルコール好き。其の為、人間と比較する上で興味深い研究対象となる事が多い。オスのひとり飲みは浮気心を助長し、時に夫婦関係を悪化する。そこでプレーリーハタネズミの出番となった。学術誌「Frontiers in Psychiatry」に発表された論文によると、彼等がアルコール摂取後、オスはパートナーと寄り添ってくつろぐか、或いは見ず知らずの別のメスと時間を過ごすかという選択肢を与えた。 その結果、オスだけが酒を飲んだ場合、パートナーと過ごした時間が短いことがわかったが、別のメスと時間を過ごすかは目下実験中である。オスとメスがどちらも酒を飲んだ場合はどちらも飲んでいない場合と同様、仲睦まじく過ごしたとの結果が出ている。しかし別の理由による夫婦関係の悪化がオスの一人飲みを誘発したのかと言う問題は残っている。プレーリーハタネズミについては興味深い話が尽きない。
彼等は1日にワイン15本分に相当する量を飲むことも出来る程の酒豪であるが、げっ歯類としては珍しい一夫一婦制で、大のアルコール好き。其の為、人間と比較する上で興味深い研究対象となる事が多い。オスのひとり飲みは浮気心を助長し、時に夫婦関係を悪化する。そこでプレーリーハタネズミの出番となった。学術誌「Frontiers in Psychiatry」に発表された論文によると、彼等がアルコール摂取後、オスはパートナーと寄り添ってくつろぐか、或いは見ず知らずの別のメスと時間を過ごすかという選択肢を与えた。 その結果、オスだけが酒を飲んだ場合、パートナーと過ごした時間が短いことがわかったが、別のメスと時間を過ごすかは目下実験中である。オスとメスがどちらも酒を飲んだ場合はどちらも飲んでいない場合と同様、仲睦まじく過ごしたとの結果が出ている。しかし別の理由による夫婦関係の悪化がオスの一人飲みを誘発したのかと言う問題は残っている。プレーリーハタネズミについては興味深い話が尽きない。










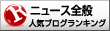
 (シマ牛の写真)
(シマ牛の写真)




