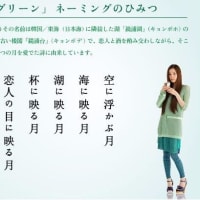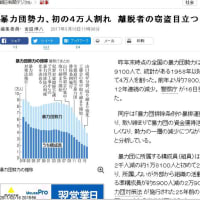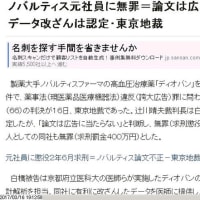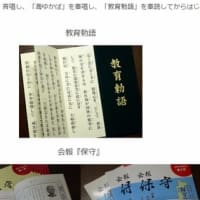朝日新聞の医療サイト アピタル
糖尿病新薬、使い方に注意 過度の低血糖や高血糖…死亡例も
東京本社科学医療グループ 大岩ゆり
糖尿病の新しいタイプの治療薬が相次いで発売されている。ところが予想外の低血糖や高血糖を起こす人が続き、2010年10月までに2人亡くなった。うまく使えば患者の生活の質が上がるだけに、専門家らは緊急情報などを出して適切な使い方を呼びかけている。どんな点に注意すればいいのかを探った。
ジャヌビアとグラクティブでは、当初は意識障害を伴う重篤な低血糖に陥った患者の報告が相次ぎ、厚生労働省は2010年4月、製薬企業に「使用上の注意」の改定を指導した。
さらにビクトーザで6月の発売から使用した20人が高血糖に陥り、うち4人がインスリンの欠乏により意識障害などを起こす「糖尿病性ケトアシドーシス」になり、60代の男性2人が亡くなった。このため、同省は10月に、製薬企業に対し、ビクトーザの「使用上の注意」を改定するよう2度目の指導をした。
なぜ低血糖や高血糖が起こったのか。
ジャヌビアとグラクティブで低血糖を起こした患者の9割は65歳以上だった。従来の血糖を下げる薬のスルホニルウレア剤(SU薬)を併用している人も多かった。
関連薬は本来、血糖の低い時には働かない。このため低血糖を起こしにくいとされていた。これに対してSU薬は血糖が低くても作用する。
日本糖尿病学会理事長の門脇孝東京大教授(糖尿病・代謝内科)は「重篤な低血糖が起きたのはSU薬の量が多かったり、高齢などで腎機能が不十分で薬の体外への排出が遅くなったりという原因が考えられる」と分析する。
専門家らの民間組織「インクレチンの適正使用に関する委員会」は、低血糖を予防するため、65歳以上の高齢者や軽度の腎機能の低下がある人が関連薬とSU薬を併用する場合、SU薬の量を減らすよう推奨している。
ビクトーザで重い高血糖を起こした患者20人のうち17人はインスリン治療をやめていた。ビクトーザは他の関連薬より効果が大きいが、あくまでインスリンの分泌を促す薬で代替にはならない。
「インスリンがほとんど分泌していない人がインスリン注射をやめれば、ビクトーザを注射しても高血糖に陥り、危険だ」と、稲垣暢也京都大教授(糖尿病・栄養内科)はいう。
インクレチン関連薬は、インスリンを分泌する膵臓の細胞が免疫異常などで破壊される1型糖尿病には承認されていない。生活習慣などが原因でインスリンの分泌が衰える2型糖尿病患者のうち、インスリンがある程度、分泌している人が対象だ。インスリンの分泌状況を血液検査で測定し使えるかどうか判断する。
「ただし、腎機能が低下していると数値が高く出るなどわからない場合もあり、より専門的な検査が必要なこともある」と稲垣さんは言う。
◆キーワード
<インクレチン関連薬>
インクレチンは小腸など消化管から出るホルモンでインスリンの分泌を促す働きがある。関連薬は、インクレチンの分泌を促したり、インクレチンが体内で分解されるのを防ぐ働きを促したりする。従来の治療薬と違い、原則として血糖が高い時に作用し、低い時は作用しない。使用上の注意点の詳細は、日本糖尿病協会の「医療従事者向け情報」に載っている。
(2010年11月11日付朝日新聞朝刊医療面から転載)