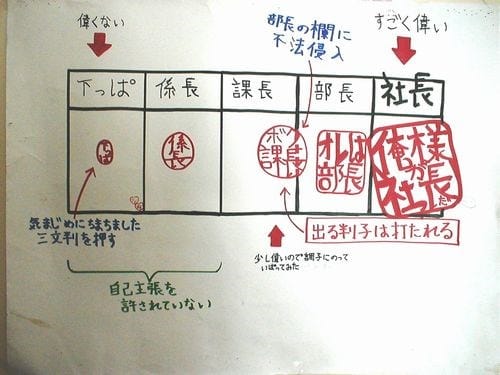2018年8月25日
息子がまだリスボンに住んでいた頃のことで、かれこれ10年ほど前になる。
普段はメッセンジャーに上がってくると午後でも「ohayo」と向こうから声がかかり、「hoihoi」の母親の返事で始まるわたしたち親子の会話は、お互い今日も元気なのを確認するだけのようなもので、ほとんど長話にはならない。
それがある日、多分お互いに夏休みだということもあったのだろう、彼の好きな音楽作曲の話から人生論じみた会話に発展。息子がその頃したいことや、わたしの当時の職場についての話、これから先のわたしの人生計画にも話が及んだ。
「人生計画ってspacesisさん、そろそろ墓場にそろ~りと片方の足くらいは入りそうな歳になるのでは?」と、口さがない人には言われそうだが、私自身はいい気なもので、人生はまだこれからだと思っている。
わたしの第一の人生は、ほろ苦い思い出が多かったポルトガルに来るまでの時代。これは、時折思い出してはエッセイに綴っている。第二の人生は、ポルトガルでの子育て時代とその頃に及ぶ土曜日の補習校の職場時代。そして、第三がこれまで自分が思って見なかった方向にひょっとすると展開するかも知れないこれからの人生。
第三の人生は、その後補習校を退職し、1年をかけてコーディネーターをしたポルト市と国際親善協会共催の2010年、Japan Weekの大仕事、現在携わっている日本語の先生と日本文化紹介のボランティア展示会や子供向けに影絵を作成して上映することにつながったている。
息子はと言えば、せっかく終えた大学のITコースを活かす就職は望んでいないようだ。大学時代の3途中で音楽を云々と言い始めたときは、趣味として続けるのは大いによしとするが、職業とするのは止めてくれと、音楽の道に行くことに賛成した夫とは違い、わたしは反対したのである。
アーティストとしての道を極められるのは、運と真の才能に恵まれたホンの一握りの人たちである。趣味で音楽をしながら一生生活できるほどの財産をわたしたち夫婦はとても子どもに残してはやれない。道は子供達が切り開かなければならないのだ。どうしても諦め切れない場合はいずれその道に入るであろう。その時こそ、誰に遠慮なく音楽の道を選べばいい。回り道になってもそれが本物である。と本人には言わなかったが。
その1年、息子はリスボンで週三回の中学校の非常勤講師をしながら生活費を稼ぎ、他の時間は音楽に費やしてきた。生活はギリギリであるが、それでもエンジョイしているとは本人の言。定職を望まない彼の将来は、少し不安定ではあるが、今しかできないことを楽しんでいたようだ。
イソップの話にある「アリとキリギリス」はあまりにも有名で、今更披露する必要もないのだが。
夏の季節を歌って遊び暮らすキリギリスとは対照的に、暑い日差しを受けながら汗を流して冬の準備にせっせといそしむアリ。それを見て笑うギリギリスではあるが、やがて冬が到来し、食べ物もなく寒さに凍える日々に、思わずアリの家のドアを叩く。今度はアリが笑う日だ。
この教訓話にはなるほどとうなずかされるのだが、わたしはもうひとつの「アリとキリギリス」を知っている。
もう40年以上も昔に、当時知り合った夫から贈られた原語でのサマーセット・モーム短編集に収められている「アリとキリギリス=The Ant and the Grasshopper」だ。
先のことに思い巡らし定職に就きせっせと働きいて貯蓄に精出している兄と、それとは全く逆にろくに仕事にも就かずその日その日を遊び暮らしている弟の兄弟がいる。時々呼び出されては弟に金を無心される兄、その都度将来のことを考えろ、もっとまじめな生活をしろと説教を垂れる。兄はこの弟を心のどこかで見下げている。
ある日、呼び出され「ふん、またか」の気持ちで待ち合わせ場所に出向く。弟の話は金の無心ではなくて、先ごろ大金持ちの未亡人と結婚したのだが、その年上の妻が亡くなり莫大な遺産が転がり込んだということである。
この時の兄の「I´ts not fair!」の悔し紛れの叫びが分からないこともないが、わたしは、「へぇ~。でも人生って案外こんなものかも知れない。」と納得いったようないかなかったような、そんな読後感をもったものだ。
ポルトガルに来てから40年、もちろんわたしは遊び暮らしてきたわけではないが、先を考えて貯めたいにも貯めようがない状態でずっと今日まで来ている。子供達の教育費には分不相応にかけたので、金額にすればひと財産にはなるであろう。
老後、何が一番必要かと言えばやはり金だ、と言ってはばからない人は周囲に結構いる。夫は別だが、どこからも年金の入ってこようがないわたしは、この言葉を耳にするとうなだれるばかりだ。かと言って今更慌てて貯めようにも、70を過ぎてでは仕事をしているものの、大して貯めようがない。
そして、お金は確かに必要だが、「一番」という言葉に心のどこかで反撥を感じる時分がいる。
TEFLEコース(英語教師)を取るので英文学の本を少し読みたいという息子に、「昔パパからもらった記念の本だから返してね」と貸した上述のモームの本だった。息子も「アリとキリギリス」を覚えていて、
「パパがいるから、少しは大丈夫」と言うわたしの言葉に、
「ボクもそうだけどママもキリギリスタイプだね。」と息子に言われた。
そして「パパは典型的なアリタイプだ」と彼は付け加えた。
その通りです、息子よ。
しかし、人生はunfair(アンフェア=不公平)なことの方がfair よりも遙かに多いのだ。それに、アリとアリの夫婦なんて、しんどいかもよ。キリギリスとキリギリスもこりゃ大変だ。
アリとキリギリス、これでなんとか帳尻が合うというものではないか。
冬が到来したら夫と言うアリのドアを叩く、わたしはキリギリスです。そして、このギリギリスはまだ人生の晩夏を謳歌しようと目論んでいる。
息子がまだリスボンに住んでいた頃のことで、かれこれ10年ほど前になる。
普段はメッセンジャーに上がってくると午後でも「ohayo」と向こうから声がかかり、「hoihoi」の母親の返事で始まるわたしたち親子の会話は、お互い今日も元気なのを確認するだけのようなもので、ほとんど長話にはならない。
それがある日、多分お互いに夏休みだということもあったのだろう、彼の好きな音楽作曲の話から人生論じみた会話に発展。息子がその頃したいことや、わたしの当時の職場についての話、これから先のわたしの人生計画にも話が及んだ。
「人生計画ってspacesisさん、そろそろ墓場にそろ~りと片方の足くらいは入りそうな歳になるのでは?」と、口さがない人には言われそうだが、私自身はいい気なもので、人生はまだこれからだと思っている。
わたしの第一の人生は、ほろ苦い思い出が多かったポルトガルに来るまでの時代。これは、時折思い出してはエッセイに綴っている。第二の人生は、ポルトガルでの子育て時代とその頃に及ぶ土曜日の補習校の職場時代。そして、第三がこれまで自分が思って見なかった方向にひょっとすると展開するかも知れないこれからの人生。
第三の人生は、その後補習校を退職し、1年をかけてコーディネーターをしたポルト市と国際親善協会共催の2010年、Japan Weekの大仕事、現在携わっている日本語の先生と日本文化紹介のボランティア展示会や子供向けに影絵を作成して上映することにつながったている。
息子はと言えば、せっかく終えた大学のITコースを活かす就職は望んでいないようだ。大学時代の3途中で音楽を云々と言い始めたときは、趣味として続けるのは大いによしとするが、職業とするのは止めてくれと、音楽の道に行くことに賛成した夫とは違い、わたしは反対したのである。
アーティストとしての道を極められるのは、運と真の才能に恵まれたホンの一握りの人たちである。趣味で音楽をしながら一生生活できるほどの財産をわたしたち夫婦はとても子どもに残してはやれない。道は子供達が切り開かなければならないのだ。どうしても諦め切れない場合はいずれその道に入るであろう。その時こそ、誰に遠慮なく音楽の道を選べばいい。回り道になってもそれが本物である。と本人には言わなかったが。
その1年、息子はリスボンで週三回の中学校の非常勤講師をしながら生活費を稼ぎ、他の時間は音楽に費やしてきた。生活はギリギリであるが、それでもエンジョイしているとは本人の言。定職を望まない彼の将来は、少し不安定ではあるが、今しかできないことを楽しんでいたようだ。
イソップの話にある「アリとキリギリス」はあまりにも有名で、今更披露する必要もないのだが。
夏の季節を歌って遊び暮らすキリギリスとは対照的に、暑い日差しを受けながら汗を流して冬の準備にせっせといそしむアリ。それを見て笑うギリギリスではあるが、やがて冬が到来し、食べ物もなく寒さに凍える日々に、思わずアリの家のドアを叩く。今度はアリが笑う日だ。
この教訓話にはなるほどとうなずかされるのだが、わたしはもうひとつの「アリとキリギリス」を知っている。
もう40年以上も昔に、当時知り合った夫から贈られた原語でのサマーセット・モーム短編集に収められている「アリとキリギリス=The Ant and the Grasshopper」だ。
先のことに思い巡らし定職に就きせっせと働きいて貯蓄に精出している兄と、それとは全く逆にろくに仕事にも就かずその日その日を遊び暮らしている弟の兄弟がいる。時々呼び出されては弟に金を無心される兄、その都度将来のことを考えろ、もっとまじめな生活をしろと説教を垂れる。兄はこの弟を心のどこかで見下げている。
ある日、呼び出され「ふん、またか」の気持ちで待ち合わせ場所に出向く。弟の話は金の無心ではなくて、先ごろ大金持ちの未亡人と結婚したのだが、その年上の妻が亡くなり莫大な遺産が転がり込んだということである。
この時の兄の「I´ts not fair!」の悔し紛れの叫びが分からないこともないが、わたしは、「へぇ~。でも人生って案外こんなものかも知れない。」と納得いったようないかなかったような、そんな読後感をもったものだ。
ポルトガルに来てから40年、もちろんわたしは遊び暮らしてきたわけではないが、先を考えて貯めたいにも貯めようがない状態でずっと今日まで来ている。子供達の教育費には分不相応にかけたので、金額にすればひと財産にはなるであろう。
老後、何が一番必要かと言えばやはり金だ、と言ってはばからない人は周囲に結構いる。夫は別だが、どこからも年金の入ってこようがないわたしは、この言葉を耳にするとうなだれるばかりだ。かと言って今更慌てて貯めようにも、70を過ぎてでは仕事をしているものの、大して貯めようがない。
そして、お金は確かに必要だが、「一番」という言葉に心のどこかで反撥を感じる時分がいる。
TEFLEコース(英語教師)を取るので英文学の本を少し読みたいという息子に、「昔パパからもらった記念の本だから返してね」と貸した上述のモームの本だった。息子も「アリとキリギリス」を覚えていて、
「パパがいるから、少しは大丈夫」と言うわたしの言葉に、
「ボクもそうだけどママもキリギリスタイプだね。」と息子に言われた。
そして「パパは典型的なアリタイプだ」と彼は付け加えた。
その通りです、息子よ。
しかし、人生はunfair(アンフェア=不公平)なことの方がfair よりも遙かに多いのだ。それに、アリとアリの夫婦なんて、しんどいかもよ。キリギリスとキリギリスもこりゃ大変だ。
アリとキリギリス、これでなんとか帳尻が合うというものではないか。
冬が到来したら夫と言うアリのドアを叩く、わたしはキリギリスです。そして、このギリギリスはまだ人生の晩夏を謳歌しようと目論んでいる。