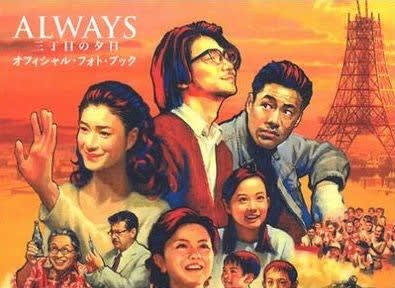2024年1月28日
本を読んでいるとき、あるいは映画を観ているとき、その中でドキリとする言葉、記憶にとどめたいと感じさせられる言葉に出会うことがあります。
最近でこそ興味がある映画に出会わないので映画館で観ていませんが、わたしは大の映画ファンで、好きな映画は何度でも繰り返し観るタイプです。でも映画は観る人によって感じ方見方が違うと思うので評論もどきはしません。
かなり古い映画ですが、観たのは近年だという「The Outsiders」が印象に残っており、言語の本も取り寄せました。その中の折に触れては心に浮かんでくる詩をあげたいと思います。
映画は1967年に18歳で作家デビューしたS.E.ヒントン(女性)の同名小説を1983年にフランシス・コッポラが映画化したものです。下のポスターを見ると、パトリック・スエイジを始めトム・クルーズ、ラルフ・マッチオ(空手キッズの主人公)など後のハリウッドスターたちが揃って出演しています。
物語はオクラホマ州の小さな町が舞台、富裕層と貧困層の不良グループがいがみあっています。富裕層グループにリンチにかけられそうになった仲間のポニーボーイを救おうと、ジョニー(ラルフ・マッチオ)は対立するメンバーの一人を心ならずも刺してしまいます。
二人は町から離れた古い教会に身を潜めるのですが、ある日、美しい朝焼けを見てポニーボーイはロバート・フロストの詩を暗唱し、ジョニーはその詩に感銘を受けます。下がその詩です。
「Nothing gold can stay」 by Robert Frost
Nature´s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf´s a flower
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief.
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.
萌えいずる最初の緑は黄金だ
その色を保ち続けるのは難しい
萌えいずる葉は花である
しかし、それはわずか一瞬だけだ
やがて葉は葉へとおさまる
エデンの園もそれと同じ、年を取り純真さを失い悲しみに沈んだ
そして、暁は終わり今日という一日が始まる
黄金のままであり続けるものはないのだ
フロストの詩が暗唱されるシーン
私たちが持つ純真さ、美しさは大人になるという避けがたい時の流れとともに失われてしまい、どんなものも黄金の輝きを放ち続けることはできない、とフロストの詩は最後に結んでいます。
美しいもの、青春、子供時代ははかないというメタファーでしょうか。
映画の終わりで、二人が隠れ家にしていた古い教会が火事になり、その中にいた町から来ていた子供たちを救い出したジョニーが大火傷を負います。
死に際にジョニー少年は、
あの詩のことをずっと考えていたんだ。あの詩が言っていることは、子供のころはみんな黄金なんだ、若葉の緑のように。すべてがまるで夜明けのように新しくて。大人になっても人生の大切なもの、最初の春のような自然の美しさや純真さ、その「黄金」を忘れないでくれ。「Stay gold」、「輝き続けよ、自分に誠実に生きよ」との言葉をポニーボーイに遺します。
歳を取り人生経験が豊かになると、つい小賢しい世渡り観を身につけがちですが、ジョニー少年が遺した「Stay gold」は、不器用な生き方になるかもしれませんね。
もしわたしが中学生のクラスを担当したら、授業でいっしょに読んでみたいと思われる本の一冊です。
青春時代のようなキラキラした輝きはもうないけれど、いぶし銀てのがあるな、なんて、またおアホなことを考えているのでありますが、貧困層グループの気持ちが哀しいくらいよく分かり、わたしにとっては切ない青春映画です。
スティーヴィー・ワンダーが主題歌「Stay Gold」を歌っています。
本を読んでいるとき、あるいは映画を観ているとき、その中でドキリとする言葉、記憶にとどめたいと感じさせられる言葉に出会うことがあります。
最近でこそ興味がある映画に出会わないので映画館で観ていませんが、わたしは大の映画ファンで、好きな映画は何度でも繰り返し観るタイプです。でも映画は観る人によって感じ方見方が違うと思うので評論もどきはしません。
かなり古い映画ですが、観たのは近年だという「The Outsiders」が印象に残っており、言語の本も取り寄せました。その中の折に触れては心に浮かんでくる詩をあげたいと思います。
映画は1967年に18歳で作家デビューしたS.E.ヒントン(女性)の同名小説を1983年にフランシス・コッポラが映画化したものです。下のポスターを見ると、パトリック・スエイジを始めトム・クルーズ、ラルフ・マッチオ(空手キッズの主人公)など後のハリウッドスターたちが揃って出演しています。
物語はオクラホマ州の小さな町が舞台、富裕層と貧困層の不良グループがいがみあっています。富裕層グループにリンチにかけられそうになった仲間のポニーボーイを救おうと、ジョニー(ラルフ・マッチオ)は対立するメンバーの一人を心ならずも刺してしまいます。
二人は町から離れた古い教会に身を潜めるのですが、ある日、美しい朝焼けを見てポニーボーイはロバート・フロストの詩を暗唱し、ジョニーはその詩に感銘を受けます。下がその詩です。
「Nothing gold can stay」 by Robert Frost
Nature´s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf´s a flower
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief.
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.
萌えいずる最初の緑は黄金だ
その色を保ち続けるのは難しい
萌えいずる葉は花である
しかし、それはわずか一瞬だけだ
やがて葉は葉へとおさまる
エデンの園もそれと同じ、年を取り純真さを失い悲しみに沈んだ
そして、暁は終わり今日という一日が始まる
黄金のままであり続けるものはないのだ
フロストの詩が暗唱されるシーン
私たちが持つ純真さ、美しさは大人になるという避けがたい時の流れとともに失われてしまい、どんなものも黄金の輝きを放ち続けることはできない、とフロストの詩は最後に結んでいます。
美しいもの、青春、子供時代ははかないというメタファーでしょうか。
映画の終わりで、二人が隠れ家にしていた古い教会が火事になり、その中にいた町から来ていた子供たちを救い出したジョニーが大火傷を負います。
死に際にジョニー少年は、
あの詩のことをずっと考えていたんだ。あの詩が言っていることは、子供のころはみんな黄金なんだ、若葉の緑のように。すべてがまるで夜明けのように新しくて。大人になっても人生の大切なもの、最初の春のような自然の美しさや純真さ、その「黄金」を忘れないでくれ。「Stay gold」、「輝き続けよ、自分に誠実に生きよ」との言葉をポニーボーイに遺します。
歳を取り人生経験が豊かになると、つい小賢しい世渡り観を身につけがちですが、ジョニー少年が遺した「Stay gold」は、不器用な生き方になるかもしれませんね。
もしわたしが中学生のクラスを担当したら、授業でいっしょに読んでみたいと思われる本の一冊です。
青春時代のようなキラキラした輝きはもうないけれど、いぶし銀てのがあるな、なんて、またおアホなことを考えているのでありますが、貧困層グループの気持ちが哀しいくらいよく分かり、わたしにとっては切ない青春映画です。
スティーヴィー・ワンダーが主題歌「Stay Gold」を歌っています。