2017年10月23日
2007、2008年以来、確認のために何度も訪れて来たシントラのキンタ・ダ・レガレイラ(レガレイラの森)を、今回はダビンチ・コードシリーズの著者ダン・ブラウンが訪れました。

ニュースではダン・ブラウンがレガレイラの森にある「ダンテ新曲の井戸」の石の扉から入り、Fantastic!すごい!と連発する映像が流されました。

ダン・ブラウン氏にはトマールのテンプル、キリスト騎士団修道院をも是非訪れて関連したミステリー本を書いて欲しいものだと切望するわたしです。
キンタ・ダ・レガレイラを別ブログで取り上げたのは日本語では恐らくわたしが初めてではないかと思います。シンボルが一杯のすごい森なのだと発信していたところが、今では多くの訪問客の中に日本人ツーリストもたくさん見られるようになりました。
実はわたしの中では、キンタ・ダ・レガレイラはまだ不完全な案内に留まったままで、本当の追っかけ、推理はこれからだと言えます。ここ数年、ポルトガル語のディアス先生と週に一度、ポルトの歴史本を読んでポルトガル語を勉強して来たのは、最終的な目的がキンタ・ダ・レガレイラについて出版された原語の本を読むことにあるります。
幸いにディアス先生は神学を勉強なさり宗教には詳しい方で、わたしのヘンチクリンな質問にも付き合ってくださる。下記の分厚い本を一緒に読んでいただこうというのがわたしの目論見なのですが、果たして同意してくださるかどうか。現在読んでいる二冊目のポルトの「通り」の歴史本完読後に、持ちかけるつもりでおり、いいよ、と言っていただけたとしたら、恐らく来年には読み始められると見ています。
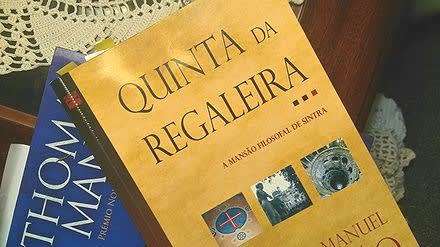
ミステリアスな事も去ることながら、この9月に訪れたバチカン、システィナ礼拝堂の天井画を描いたミケランジェロのように、カトリックが支配した近世のヨーロッパで、神秘主義やメーソン、エルメス主義、錬金術などの異教に傾倒する人たちがどのように自分たちの信条を隠しつつ表現して生きたかに、わたしは大いに興味を持ちます。
キンタ・ダ・レガレイラは、そういった時代を生きぬいた、カトリックからするとPagan(異教徒)とされた人達がシンボルを使用することにより分かる人には伝わるようにと、あまたの秘密が刻み込まれたポルトガル随一の摩訶不思議な森です。
実は日本のバブル期に青木建設が一時期所有し住居として使われていたことはあまり知られていませんが、なぜ買い取ったのか、いったい誰が住んだのか、この辺も大いに興味があるところです。
この秋から、これまで日本語教室で使用してきたテキストが少し物足りなく感じられ、自ら文法説明と口語、短作文練習を含めたものを作成し始め、その仕事に追われてブログ更新が遅れたりしていますが、ダン・ブラウンのレガレイラ訪問で再び探求したい気持ちが再びググッと持ち上がって来ました。
新情報も加えて再度書いていきたいと思います。
2007、2008年以来、確認のために何度も訪れて来たシントラのキンタ・ダ・レガレイラ(レガレイラの森)を、今回はダビンチ・コードシリーズの著者ダン・ブラウンが訪れました。

ニュースではダン・ブラウンがレガレイラの森にある「ダンテ新曲の井戸」の石の扉から入り、Fantastic!すごい!と連発する映像が流されました。

ダン・ブラウン氏にはトマールのテンプル、キリスト騎士団修道院をも是非訪れて関連したミステリー本を書いて欲しいものだと切望するわたしです。
キンタ・ダ・レガレイラを別ブログで取り上げたのは日本語では恐らくわたしが初めてではないかと思います。シンボルが一杯のすごい森なのだと発信していたところが、今では多くの訪問客の中に日本人ツーリストもたくさん見られるようになりました。
実はわたしの中では、キンタ・ダ・レガレイラはまだ不完全な案内に留まったままで、本当の追っかけ、推理はこれからだと言えます。ここ数年、ポルトガル語のディアス先生と週に一度、ポルトの歴史本を読んでポルトガル語を勉強して来たのは、最終的な目的がキンタ・ダ・レガレイラについて出版された原語の本を読むことにあるります。
幸いにディアス先生は神学を勉強なさり宗教には詳しい方で、わたしのヘンチクリンな質問にも付き合ってくださる。下記の分厚い本を一緒に読んでいただこうというのがわたしの目論見なのですが、果たして同意してくださるかどうか。現在読んでいる二冊目のポルトの「通り」の歴史本完読後に、持ちかけるつもりでおり、いいよ、と言っていただけたとしたら、恐らく来年には読み始められると見ています。
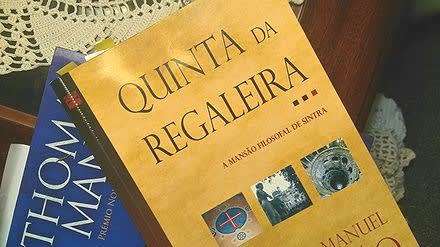
ミステリアスな事も去ることながら、この9月に訪れたバチカン、システィナ礼拝堂の天井画を描いたミケランジェロのように、カトリックが支配した近世のヨーロッパで、神秘主義やメーソン、エルメス主義、錬金術などの異教に傾倒する人たちがどのように自分たちの信条を隠しつつ表現して生きたかに、わたしは大いに興味を持ちます。
キンタ・ダ・レガレイラは、そういった時代を生きぬいた、カトリックからするとPagan(異教徒)とされた人達がシンボルを使用することにより分かる人には伝わるようにと、あまたの秘密が刻み込まれたポルトガル随一の摩訶不思議な森です。
実は日本のバブル期に青木建設が一時期所有し住居として使われていたことはあまり知られていませんが、なぜ買い取ったのか、いったい誰が住んだのか、この辺も大いに興味があるところです。
この秋から、これまで日本語教室で使用してきたテキストが少し物足りなく感じられ、自ら文法説明と口語、短作文練習を含めたものを作成し始め、その仕事に追われてブログ更新が遅れたりしていますが、ダン・ブラウンのレガレイラ訪問で再び探求したい気持ちが再びググッと持ち上がって来ました。
新情報も加えて再度書いていきたいと思います。






























