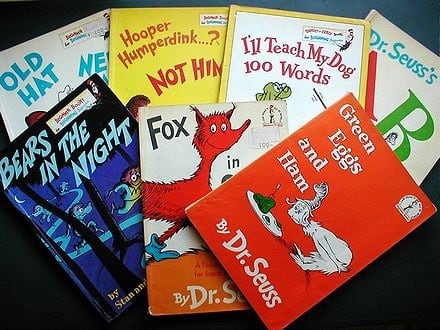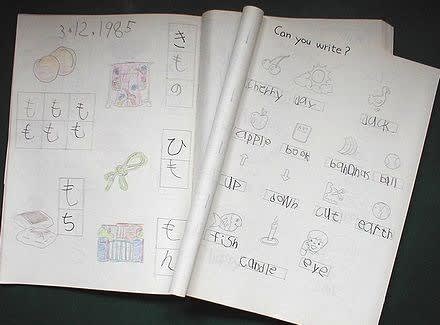2019年5月22日
ひらがなを初めて学ぶとき、「あいうえお」と始める人は多いのではないでしょうか。
「アリのあ」「イヌにい」と言うように。
わたしが子供達に取った方法は少し違います。
ローマ字でもそうなのですが、A,B,C,Dというのは、文字自体が意味を持ちません。
これでは、子供に求められたときに説明に困ります。わたしの場合は、このように、ひらがなの読みを始めました。
母音5文字から、まず始めました。
あお いえ うえ
「あいうえお」の5文字から簡単で、身近な言葉をつかい、こんな風に言葉カードを作りました。
このヒントは、もちろん、先の英語の初歩の教え方から得ました。「か行」に入ると、今度は「あか、かお、いか、えき、いけ、こい、あおい、あかい、」と段々言葉のカードも増えていきます。
実は同じ方法をわたしは今も、日本語教室で初めて日本語に触れ、ひらがなを学ぶ生徒さんに使います。
これは、ひらがなの読みと言葉を繰り返して覚えることになります。
あ行のカードが読めるようになったら、今度は、「あ」「い」「う」「え」「お」の大きめの単独カードを見せます。すると、「あおのあ!」「いえのい!」と言う答えが子どもから返ってきます。
始めは「カード遊びをしようかなぁ」と子供を誘い、最初は2枚の大きなカードを見せてゆっくり読みます。
次は、その2枚のカードをテーブルの上に置き、カルタとりです。次は、もう一枚増やして3枚のカードとりになります。
新しく作ったカードをこれに加えて行きますから、最後はかなりたくさんのカードを並べてのゲームです。
子供からすると、あくまでも、遊びの感覚です。わたしは初期の頃は、子供が飽きる前に切り上げることに気をつけました。
4歳からですと、小学校にあがるまでに、時間はたっぷりあります。ゆっくりと、苦労せず楽しみながら、しかも確実に身につくようにするには、「飽きる前に切り上げる」、これがよかったのではないかと思っています。
「もっとしたい!」
「そうね。でも、お仕事があるから、もうお終い」
こういうことが何度もありました。
子供が幼稚園に行っている間のひらがな言葉のカード作りは、当時、時間を持て余し気味だったわたしにとって楽しみでした。
帰って来ると手を洗わせ昼食を済ませ、少し休憩してから、カード読み遊び。これが土日を除いては毎日繰り返されました。
こうして英語と日本語の言葉覚えが同時進行して行きました。
次回に続きます。
ひらがなを初めて学ぶとき、「あいうえお」と始める人は多いのではないでしょうか。
「アリのあ」「イヌにい」と言うように。
わたしが子供達に取った方法は少し違います。
ローマ字でもそうなのですが、A,B,C,Dというのは、文字自体が意味を持ちません。
これでは、子供に求められたときに説明に困ります。わたしの場合は、このように、ひらがなの読みを始めました。
母音5文字から、まず始めました。
あお いえ うえ
「あいうえお」の5文字から簡単で、身近な言葉をつかい、こんな風に言葉カードを作りました。
このヒントは、もちろん、先の英語の初歩の教え方から得ました。「か行」に入ると、今度は「あか、かお、いか、えき、いけ、こい、あおい、あかい、」と段々言葉のカードも増えていきます。
実は同じ方法をわたしは今も、日本語教室で初めて日本語に触れ、ひらがなを学ぶ生徒さんに使います。
これは、ひらがなの読みと言葉を繰り返して覚えることになります。
あ行のカードが読めるようになったら、今度は、「あ」「い」「う」「え」「お」の大きめの単独カードを見せます。すると、「あおのあ!」「いえのい!」と言う答えが子どもから返ってきます。
始めは「カード遊びをしようかなぁ」と子供を誘い、最初は2枚の大きなカードを見せてゆっくり読みます。
次は、その2枚のカードをテーブルの上に置き、カルタとりです。次は、もう一枚増やして3枚のカードとりになります。
新しく作ったカードをこれに加えて行きますから、最後はかなりたくさんのカードを並べてのゲームです。
子供からすると、あくまでも、遊びの感覚です。わたしは初期の頃は、子供が飽きる前に切り上げることに気をつけました。
4歳からですと、小学校にあがるまでに、時間はたっぷりあります。ゆっくりと、苦労せず楽しみながら、しかも確実に身につくようにするには、「飽きる前に切り上げる」、これがよかったのではないかと思っています。
「もっとしたい!」
「そうね。でも、お仕事があるから、もうお終い」
こういうことが何度もありました。
子供が幼稚園に行っている間のひらがな言葉のカード作りは、当時、時間を持て余し気味だったわたしにとって楽しみでした。
帰って来ると手を洗わせ昼食を済ませ、少し休憩してから、カード読み遊び。これが土日を除いては毎日繰り返されました。
こうして英語と日本語の言葉覚えが同時進行して行きました。
次回に続きます。