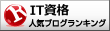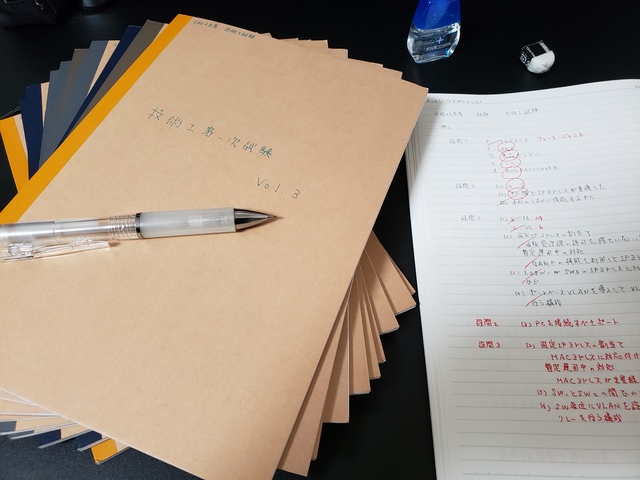このシリーズをいつも見ていただきありがとうございます。
前回は念願の基本情報技術者試験に合格した話をしたが、
一番大事なことは「学び続ける」ということ。
継続は力なり。
まさにこの言葉に尽きる生き方をしてきていると思う。
無事に就職先も決まり、社会人になった私はさらに自分の力のなさを痛感する。
入社1年目の私は、まず社会人およびシステムエンジニア(以下、SE)として必要となる
新入社員研修を受講することになるが、SEに必要な研修は苦労しなかった。
むしろ教えられるぐらい余裕があり、楽しかった。
そして、現場配属。
当たり前だが役に立たない自分がいた。
幸い、情報処理技術者試験の勉強を継続していたこともあり、
同期よりほんの数cmだけ進んでいたに過ぎなかった。
もっと言うと、専門用語が少し分かり、プログラミングが少し出来るだけでしかなかった。
お客様からお金をいただくための「プロ」には程遠かったことを思い出す。
完全に勘違いである。
研修が余裕だっただけに追い打ちがかかっていた。
間違いなく、情報処理技術者試験に合格しているという心の甘さがそのようにさせていたのだろう。
所詮基本情報技術者はSEが飯を食べるために必要な基礎中の基礎を持っているかどうかだけだ。
資格試験に合格している = 仕事ができる ではないのだ。
これに気付いた私は、仕事人間となりさらにいろいろな勉強をした。
・1日48時間あればいいのになぁ~
・もっと学生の時に勉強しておけばよかったなぁ~
・少しでも油断すると置いていかれる、、、
など考えながら、後悔と不安と努力するしかなかった。
それでも変えられるのは「未来」だけ。
前を向くしかないのだ。
このご時世では許されないが、どんなに残業しても、どんなにパワハラ受けても、
どんなにダメ出しされても、どんなに周りから噂話されても、
1歩でも前に進むためにはただひたすら仕事と勉強をした。
そして、小さな成功体験と失敗体験を繰り返しながら、
人よりも1つでも多く仕事をこなし、少しでも学習して知識を身に付けて
周りに追いつかなければとただそれだけを考えて過ごした。
20代はこのような生活をし続けた。
私は素養がないからこれしかなかった。
幸いにも結婚し、子供もできたが、それでもこの生活をつづけた。
今思うと妻と子供には大変申し訳ないことをしていたと思う。
それでも、私なんかよりも寛大な心で見守ってくれた。
感謝でしかなかった。
ただ、この生活を続けることで一つのプロセスを構築できた。
①仕事を通じてわからないことが出る
②わからないことをキーワードに情報処理技術者試験や関連資格を通じて体系的に学ぶ
③わからなかったことが勉強を通じて仕事に活かせるようになる
④仕事に活かせることが当たり前になること、試験にも合格している
この継続性は、高校時代の恩師の言葉に詰まっている。
詳しくは、「そもそもどうして資格試験を目指したの? (その4)」を参照して欲しい。
今思うと、この勘違いから生まれた私なりのプロセスが、
SE人生の中で成長し続けるための礎を築いたのだなと思う。
そういう意味では、若いうちは成功し続けるよりも失敗したほうが良いと思う。
今、私が新人に対する接し方は以下だ。
・成功体験は褒める
・失敗体験は反省させて振り返らせる ※怒らずに叱るを忘れないように注意!
・失敗体験から改善できたことは褒め倒す
今日はここまでにする。続きは次回。
12/17(金) 正午に、IPAのHPで令和3年度 情報処理技術者試験の合格発表が行われた。
当日は仕事に忙殺され、結果はまさに今確認した。
果たして、結果は、、、
不合格である。
解答例が公表され、意外といけるのでは?と感じていたが甘かった。
当然と言えば当然の結果かなと思う。
この試験区分は、技術士第一次試験と同様に数学や物理の要素が強い。
さらに、電気回路なども登場する。
業務経験面でも一般的なシステム開発経験しかないため、経験がない。
つまり、私にとっては難易度が高い試験区分だからだ。
ただ、注目すべきは当機構が公表している「統計情報」。
今回のエンベデッドシステムスペシャリスト試験の合格率は18%以上。
かなり高い。
この試験は合格率を一定に保つために点数調整がされるという。
なので、ある程度できた感触を持っていたとしても点数調整の結果、
不合格となった方が多かったのではないかと推測する。
(推測の域を越えられないので、あくまで参考程度に読んで欲しい。)
今回は真剣に勉強しただけに悔しい。
この悔しさをバネに次につなげていきたい。
そしてもう一つ、改めて感じたこと。
それは、
「点数調整が仮にされていたとしても、
この影響をものともしないぐらいの得点が取れるだけの力が必要」
という点である。
ギリギリでもしかしたら合格するかもではなく、
答案用紙の記載ミスがない限りは大丈夫でしょうというぐらいの
ところまで得点できる力を身に付ける必要がある。
そういう意味では、変に合格しなくてよかったのかもしれない。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験の基準に満たすだけの力が
なかっただけなので、次はもっとレベルアップして臨みたい。
結果は出た。いつまでも過去を見ていても仕方がない。
それに、この領域の知識が0だった私が午後Ⅰ試験の半分以上は
得点できるところまで持ってこれた。
ポジティブに考えると飛躍したと思う。
次は、来年度の春期試験。
ネットワークスペシャリスト試験の2回目の受験に向けて、
しっかりと計画を立てて努力を積み重ねていきたいと思う。
合格された方、おめでとうございます!
自分自身にご褒美を与えてあげてください!
(合格が少し早いX'masプレゼントだと思いますが、+αのご褒美があってもいいと思います!)
残念ながら不合格となってしまった方、
私も頑張りますので一緒に頑張りましょう!
この「そもそもどうして」シリーズが多くの方に読まれ、非常にありがたい。
本日も閲覧いただいた皆様に少しでもなにか得られるものがあればと思い、
投稿していきたいと思う。
~人生の分岐点⑤~
念願の合格
今でも忘れない。
大学3年生の5月中旬。
基本情報技術者試験を受験しつづけて7回目であろうか、、、
大学での授業や自己啓発による学習により、
色々な知識が点から線に変わり始めていた。
手ごたえがようやく出てきて今回こそは!と思っていた。
結果は「合格」。
人生で一番嬉しかったし、苦労と努力を重ねた分喜びが半端なかった。
経済産業大臣が交付する合格証書も受領し、初めて実感がわいた。
勢いで、この年の秋に「初級システムアドミニストレータ」を受験。
基本情報技術者試験に比べると本当に簡単だった。
もちろん結果は「合格」だった。
(ちなみに、初級システムアドミニストレータは現試験制度のITパスポート試験に相当する)
ここから、いろいろなことが変わっていった。
大学4年生になると、基本情報技術者試験の合格が
自分自身に大きな影響を与えるようになる。
例えば、
・どんなに簡単な検定試験であってもそれが将来目指す難関資格の準備になることの理解
・自分に自信がつき、さらに上を目指そうという気持ちになった
・心にゆとりが生まれ、学業にも良い方向で影響を与えるようになった
・就職活動面で苦労することがすくなくなった
と、こんな感じである。
ただ、いい話ばかりではない。
このころから、周囲から残念な言葉も漏れ聞こえるようになってきた。
「そんなに資格取ってどうするの?資格マニアでも目指しているの?」
当然、このような冷ややかな言葉に免疫がなかったため、嫌な気持ちになった。
とある日、高校時代の恩師と話す機会があり、近況報告をした。
(いいことも嫌なことも全てお伝えした)
すると、こんな言葉が返ってきた。
「お前の一番の強みは継続して続けられること。
これは出来るようでできない強みだから、どんな形でも継続するということを続けるべき」
本当に救われた。
試験合格のたびに氏名が校舎に張り出され、目立つようになったこともあり、
周りの目を気にし過ぎていた。
だが、この言葉のおかげで吹っ切ることが出来た。
そして、上記のような冷ややかな言葉を聞いてもまったく気にならなくなった。
なぜなら、夢に向かって少しずつ進むためには学び続けなければならないと感じたから。
大前提として、私は素養がない。
だから必要と思う勉強を資格試験を通じて行っている。
それを続けないと夢に近づけない。
ただ、これだけなのだ。
人それぞれ考え方も違う!
こういう生き方があってもいいと思う!
誰に何言われても、自分が信じる道に全力投球すれば悔いは残らない!
だって、1回きりの人生だし!
資格試験を紹介してくれたのも、少し凹んだ私を救ってくれたのも、
高校時代の恩師たち。
本当に恵まれていたんだと思う。
今日はここまでとしよう。続きは次回。
このシリーズの投稿は非常によく見ていただけるようだ。
非常にありがたいお話であり、閲覧してくださった方や評価していただいた方に感謝である。
さて、今日は大学時代の話をしたいと思う。
目指すべき工業大学の推薦枠を得て、合格することが出来た。
高校2年生で挫折を覚えた「情報処理技術者」試験。
この勉強を続けていた。
~人生の分岐点④~
難関試験に合格するための勉強って実はいろいろと役に立つ??
工業大学では当たり前に数学や物理の授業があり、大変×10 以上苦労した。
ただ、私の出身(高校)の学歴などの背景を理解していただいたうえで
正規授業の後に私のために補講をしてくれて何とか単位が取れた。
一方、簿記や経済学、統計学、情報処理系の授業は本当に楽であった。
情報処理技術者試験の授業を通じて、
いつの間にか多くのことを勉強していたことに気づかされる。
ここで一つ気付かされたことがあった。それは、
「資格試験というのは体系立てて学べることが出来る」
ということ。
効率よく学習ができ、広く浅く満遍なくスキルの習得が出来る。
さらに、試験のレベルが上がると、もう一段広がりと深さが増し、
より専門的になったりする。
つまり、どんどん深く学べるようにカリキュラムが作られている
ことに気付いた。
しかも、自分が勉強したい領域にフォーカスが当たっているため、
効率がいい。
学校の授業と考え方は同じ。
ただ、資格試験は「国や協会などによる客観的な評価」によって、
基準を満たしたものに「合格証書が授与される」という点だ。
これが本当に楽しかったし、嬉しかった。
情報処理技術者試験はこのあたりから第2種情報処理技術者試験から
基本情報技術者に変更となった。
まだ、合格を目指している身であったが、並行して様々な検定試験
などを受験し、合格を勝ち取り、少しずつ成功体験を増やした。
大学の授業といえども、資格の勉強によって専門科目はよく理解できた。
資格試験は独学だったが、そこで曖昧な理解が大学の講義で明確に
理解することができ、相乗効果によっていろいろとつながりが分かってきた。
そろそろ、基本情報技術者試験の合格が見えてきたか?!
そんな大学1、2年生生活を送っていた。
今日はここまでとする。続きは次回。
令和3年度 技術士第一次試験の公式解答が技術士協会のHPに公表された。
本日の正午ごろに発表されていたみたいだ。
早速、自己採点してみる。。。
基礎科目:9/15(正答率:60.0%)
適性科目:8/15(正答率:53.4%)
どちらも基準点ギリギリで通っているようだ。
とりあえずホッとしたが、合格発表(2022年2月)までは結果が分からない。
多分大丈夫だと思っているが、マークミスなどのミスがないとは言い切れない。
しっかりと合格発表日に結果を確かめたいと思う。
とにかくギリギリだった。
良く言えば「一番効率が良いやり方」、悪く言えば「たまたま基準点をクリアしただけ」である。
過去問題(約10年分)に絞って勉強したが、一つ分かったことがある。
技術士第一次試験は
「過去問を繰り返すことで基準点はクリアできる」
ということ。
具体的に分けると以下のような感じで出題される。
・そのまま出題されるもの
・解答群が入れ替わっていたり違う表現にしているもの
・過去問題の知識を応用すれば解答できるもの
・個人的には初見で知識を求められるもの
過去問題を通じてわからない部分を調べていくことで理解が深まり、
本番試験で何とか合格点を勝ち取れたという感じだった。
私は普通科目が大の苦手だ。そのため、数学や物理(基礎科目の3群)は壊滅。
それ以外の所で満遍なく点数を稼げたのが大きかった。
普通科目が得意な人であれば、基礎科目はもっと高得点を叩き出せると思う。
それにしても、適性科目はかなり危なかった。
一般常識や直近で話題になっているテーマが問題になっているように思えた。
(当然技術士法に関する問題も出題されるが、ここは過去問やってれば大丈夫)
個人的な感想になるが、現実世界で起きている問題の解決策や対策
(=つまり法改正や新たな取り組み)を理解しているかという点が根底にあると思った。
技術士第一次試験の適性科目は、
「なぜこのような法律や取り組みが生まれたのかちゃんと理解しているか?」
という部分に尽きるのかもしれない。
これが理解できていないと、今起きている問題、今後発生する問題に対して、
どのように対応していくのかという「考え方」が出来ないと思うからだ。
結果は来年2月。果報は寝て待てということである。
仮にこの試験に合格すると、次は技術士二次試験。
技術力を高めること、技術士として倫理観を高めることなど、
やることがたくさん増えてきた。
積み重ねを続けて、合格に一歩ずつ近づきたいと思う。