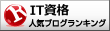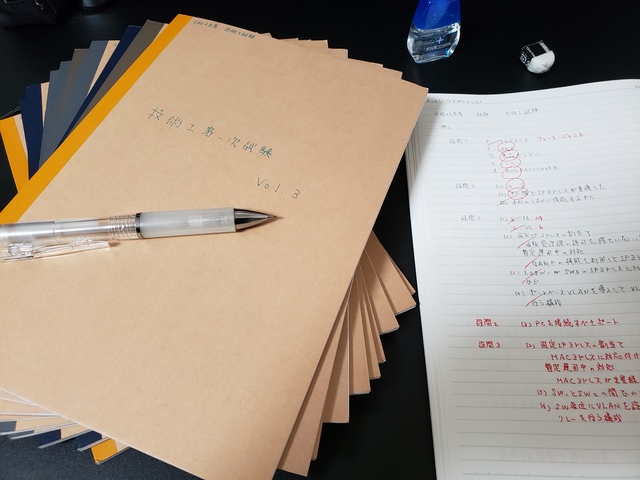前回投稿した記事「そもそもどうして資格試験を目指したの? (その1)」を
さらに多くに皆様に読んでいただけた。大変ありがたいし、感謝である。
さて、前回の続きである。
高校1年生で「第3者からの評価を得ることの大切さ」を学んだ私は、
何の躊躇もなく、受けられるものをすべて受験した。
結果は全て「合格」。
(検定試験は受験料が安く、立派な合格証書ももらえたので親も協力してくれた)
小さな積み重ねを続けて、成果を上げることの楽しさを覚え、
相乗効果となって徐々に大きな力となっていくのを実感した。
この「小さな成功体験」は当然学業や私生活にも反映される。
この時は人生で初めてうまくいっていると感じた。
しかし、人生は甘くなかった。
~人生の分岐点③~
高校2年生:情報処理技術者との出会い
当時高校で情報処理の授業を教えてもらっていたとある先生から、
専門科目が得意で検定試験も継続して合格しているし、
この先工業大学に進もうとするなら、
「通商産業省(現:経済産業省)が主催する国家試験を受験してみたらどうだ?」
と勧められた。
国家試験って美味しいですか???状態の私だったが、
せっかくだし、工業大学への近道につながるならやるしかないと思った。
きっと、これまでのように努力すれば合格できるだろうという軽い気持ちで決意した。
(後にとんでもない試験に目指していることに気づかされのだが、、、)
現在の情報処理技術者試験12区分+情報処理安全確保支援士試験の計13区分。
当時は、第2種情報処理技術者、第1種情報処理技術者など試験区分も少なく、
そして難易度も現試験制度に比べるととても難しかったと思う。
(引用:独立行政法人 情報処理推進機構 平成6年度秋期から平成12年度秋期までの試験制度)
少し、この試験について調べてみた。
すると、社会人から学生までの幅広い受験者層の中から、国として設定した水準
(システム開発・保守・運用に必要となる知識・経験)を満たした者に合格を与えるというものだった。
システム開発?保守??運用???なにこれ????
おれカメラマンになって、芸能人にたくさん会いたいんだけど、、、
とにかく「?」が頭の中にいっぱい並んだ。
試験当日、お父さんに車で試験会場まで送ってもらった。
高校生は数人。あとは大学生や社会人ばかり。
試験監督員も恐ろしい。というか、なんだこの受験者の数、、、
とにかく全てが見慣れない光景だった。
そして、受験。
当然ながら、全く歯が立たなかった。
初めて受験したときの感想はざっくり以下のような感じだ。
問われている知識は意味不明。
プログラミング言語は検定試験に比べると難易度が異常に高い。
大っ嫌いな数学的な要素がふんだんに盛り込まれている。
情報処理って一言で言うけど試験範囲が広すぎるし学校で習ったことないことだらけだし。
結果は当然「不合格」。
国家資格というものを知ってから、挫折を味わった。
だが、国家資格(情報処理技術者試験)に合格できれば就職にも有利だし、
そもそも仕事をしていくために必要なものが詰まっている。
高校2年生でいろいろなものを経験させたかったと先生から言われた。
でも、この経験はこの試験に合格してやろうという気持ちにさせてくれた。
そして、今からしっかりと準備して、大学生卒業までに合格できれば、
少しは差別化図れるのでは?と考えるようになる。
だんだんやってやろうという気持ちになり、悔しさをバネに頑張ろうと決意する。
学校の勉強+資格の勉強。当然、遊びもだ。
ここから、難関資格に臨むようになった。
情報処理技術者試験の勉強を通じて自分がステップアップできる。
そう信じて、さらに小さな積み重ねを日々続けることになる。
今思うとこの決意が今の自分(人生)を決めた気がする。
この挫折のおかげで、工業大学への推薦権である学業成績と
検定試験1級の合格が勝ち取れた。
工業大学推薦に向けての準備が少しずつ整い、
なんとか自分の夢に向かって前進することが出来た。
大学入試(推薦試験)日までさらに準備が必要と感じた年であった。
今日はここまでにする。続きは次回。
前回投稿した記事「振り返るとすごい成功を掴んでた!」の反響がすごかった。
大変ありがたい。読んでくださった方に大変感謝している。
少し役に立つ情報を発信できたのかと思い、大変嬉しく思った。
さて、では「なぜ資格試験をめざしたの?」という部分を発信してみたいと思う。
遡ること中学時代。
とにかくサッカー小僧だった。
キャプテン翼に憧れ、朝から晩までサッカー。
もちろん、雨だろうが雪だろうが構わずサッカー。
とにかく一番楽しい遊びだった。
一方、勉強は全くできなかった。
5教科平均40点行けば良い方だった。
そんな私は先生に恵まれた。
~人生の分岐点①~
中学3年生:「プログラミングって知っているか?」
担任でも何でもない先生から、
普通科目嫌なら工業高校か商業高校に行けば専門的なこと勉強できるし、
5教科もやるけど割合も少ないしいいかもよと助言をいただいた。
みんなスタートラインが一緒になるから頑張れば道開けるかもよとのこと。
このころ、安室奈美恵やMAXなど歌って踊れるアイドルにあこがれを持ち、
カメラマンになりたいと思っていた。
そんなこんなでこの道悪くないなと思い、この道を進もうと決意した。
(カメラマンとプログラミングは全然違うけど、、、)
早くに夢と進むべき道を決めれたことで吹っ切れ、
中学3年生の部活引退後から教科書をひたすら読み、問題を解き、
ノートを汚す日々を繰り返した。
結果的に平均点70点ぐらいまで取れるようになり、
目指すべき高校に進学できた。
~人生の分岐点②~
高校1年生:第3者の評価を受けなさい。
高校時代、情報処理、経済学、パソコン、簿記など、
後の自分に必要となるたくさんの武器に出会うことが出来た。
勉強のやり方を掴んだこともあり、かなり良い状態を進んでいった。
ただ、勘違いしてはいけない。
普通科目が「大の苦手」なのは変わらない。
専門科目が「少し得意」なだけであった。
カメラマンを目指すにはもっと工学的な部分も学ばなければならないことが
分かってきた。このころから工業大学を目指すようになる。
ここでも運命を変える先生に出会えたのが大きい。
専門科目で工業大学を目指すには、
「誰でも一定の理解を示す客観的な評価が必要」
ということを教わった。
これが、検定試験との出会いである。
専門科目が得意だったということもあり、様々な検定試験に合格した。
しかも、中学3年生で掴んだ勉強のやり方がそのまま活かせた。
だから周りが言うほど苦労せず、楽しく合格までたどり着けた。
そして、合格証書をもらった。
これが何よりも嬉しかったし、賞状をもらうことなって
サッカーで県3位になった時以外なかったから楽しかった。
でも一番大事だったことは、「学校の先生以外」の方が問題を作り、
「全国の受験生が同じ問題」を解き、それを「学校の先生以外」の方が
評価する。つまり、私にとっての第3者なのである。
第3者から、あなたこの検定試験〇級に十分値する能力があるよと
合格証書を通じて教えてもらえるのである。
そして、学校の先生からも褒められる。
「褒められる」これが最高に嬉しかった。
これが資格試験を目指すきっかけとなった。
今回はここまでにする。続きは次回。
私は商業高校卒業後、工業大学を出た。
これは中学3年生で勉強のやり方をなんとなく掴んで、それをひたすら繰り返した。
私は普通教科が大の苦手だ。英語も数学もできない。
だから、簿記や情報処理などみんなが一緒のスタートラインにリセットされる商業高校を選んだ。
簿記も情報処理もそれ以外も検定試験からスタートした私だが、
積み重ねを続けることで少しずつ夢が叶い、さらに次を目指している。
それが大学推薦を得て工業大学に進学し、本気で国家試験を目指すようになった。
もともとは勉強が出来ないから、体系立てて広く浅く学べる
資格試験というものを大事にしてきた。
(きっかけは高校時代にある資格を取得しないと大学推薦できなかったから猛勉強した)
最初は
1.教科書を何度も読む
2.ノートに綺麗にまとめて、ある種成果物が増える=分かったつもりになる
3.そろそろ練習問題にとりかかろう! だけど玉砕、、、
4.試験直前に力試しで過去問題やろう! 当然玉砕、、、
5.試験当日は全然わからず、結局運頼み、、、 当然不合格、、、
だった。
今考えると、負(不合格)のスパイラルだった。
私は情報処理技術者試験に思い入れがあり、高校2年生で初めて受験してから、
新型コロナウィルスによる中止・延期以外はこれまでずっと受け続けている。
最初は合格なんて程遠い、、、
素養もないから教科書を理解しようとしても理解ではなく覚えたことで分かった気になる。
でも、本質理解してないから応用効かない、、、
まぁこんな感じだった。
ただ、ある時から
1.教科書は通勤・通学の移動時間に繰り返し読む
2.時間があって椅子と机があるときは過去問をやり続ける
3.可能な限り第3者に見て(評価して)もらう
に変えた。
マークシート式、記述式、論述式、なんでもこれだ。
実践(過去問)に勝るものはないことに徐々に気付き始める。
本質的に問われる問題は、良質の問題。
つまり、過去問題で何度も出るものは大事なものということ。
そこに少しエッセンスを加えてあたかも新出問題のように見せているだけ。
これが少しずつ分かった。
これが分かると、たとえ論述式問題だったとしても、
「これってもしかしたら答えるべきことって〇〇だよな?」
となってくる。
つまり、なんでも核心的な部分はその試験にとって核となるものが問われることに気付く。
それを日々の学習を通じて、過去問から学ぶ。
過去問から感じ取った核心を自分の知識でアウトプットしていく。
それが解答に近いのか遠いのかを評価する(またはしてもらう)。
この繰り返しである。
これが20年以上資格試験を受け続けてわかってきた内容だ。
だから、もしなかなか試験に合格できないと思われる方は是非試してほしい。
試験は所詮ペーパテスト。
人口問題と予算(国家試験は国の予算だからなおさら締め付けがあると思われる)、
効率化を考えたらコスパ高く利益だそうと思うと、
やっぱり過去問から良問を再出題するに流れると確信する。
だから過去問。
とにかく過去問をやることをお勧めする。
これで私は少しずつ右肩上がりとなり、難関国家試験の合格を一つずつ掴んでこれた。
難易度は関係ない。
過去問から出題されることが多いのは間違いない。
簡単な試験から少しずつ勉強の仕方を理解することで、誰だって難関試験に合格できると思う。
(医師免許や司法書士、弁護士などは別物)
もし、少しでも悩んでいる方がいれば、一つの考え方としてこういう生き方があるんだなと
頭の片隅に置いてもらえると幸せだ。
これから、少しずつ私のノウハウをアウトプットしようと思う。
昨日、無事に令和3年度 技術士第一次試験を受験してきた。
私は受験地が東京であったので、日本大学経済学部さんで受験してきた。
関東らしい冬晴れで天気にも恵まれた。
初めての受験となる技術士第一次試験。
教室に入室するや、情報処理技術者試験とは異なり騒がしい。
試験監督員の方が一生懸命マイクを使用して説明しているではないか。
非常に丁寧で好印象。ただ、慣れないからか騒がしく感じた。
そして、受験生が意外と多いことに驚いた。
私は、専門科目が免除であり、午後からの受験となった。
まず、全体的な印象としては、複雑(難易度が極端)な気持ちになった。
それだけ範囲が広く、得意・不得意が出る試験ということである。
試験の性質は過去問からなんとなく感触をつかんでいたため、焦りはなかった。
適性科目と基礎科目をしっかり受験して、帰宅。
テスト終了後に解答速報でも見るかと思い、ググるも情報が全然ない、、、
少しは参考になるかなと思い、私が選択した解答を掲載しようと思う。
あきらかに間違っている問題も絶対にあるので、
くれぐれも「解答速報」ではないことに注意いただきたい。
※基礎科目の3群は全く分からず適当に解答、、、
<適性科目>
③、①、②、②、①、①、⑤、⑤、①、②、④、③、③、⑤、①
<基礎科目>
1群
Ⅰー1-1 ④
Ⅰー1-2 ②
Ⅰー1-3 ②
2群
Ⅰー2-1 ①
Ⅰー2-2 ②
Ⅰー2-5 ①
3群
Ⅰー3-2 ⑤
Ⅰー3-4 ④
Ⅰー3-5 ⑤
4群
Ⅰー4-1 ③
Ⅰー4-3 ①
Ⅰー4-5 ①
5群
Ⅰー5-1 ①
Ⅰー5-2 ④
Ⅰー5-4 ②
合格発表は2022年2月ごろとのこと。
公式解答は12/4に協会HPにアップされるとのことなので、まずは自己採点してみたいと思う。
明日はいよいよ 令和3年度 技術士第一次試験 の受験日である。
最後の追い込みを済ませ、あとは体調を整えることに注力することとした。
私は、専門科目免除のため、適性科目と基礎科目を受験する。
東京会場での受験であり、午後からだ。
試験時間はそれぞれ1時間であるため、合計2時間の試験で合否が決まってしまう。
技術士「第一次試験」だから、マークシート形式の知識解答型である。
なんとかなりそうなレベルにまで持ってきたつもりであるため、
今日はゆっくり休んで明日力をすべて出し切れるように頑張ってきたいと思う。
今年最後になる国家試験。
まずは受験会場にたどり着き、スタートラインに立てるように準備をしようと思う。
明日、同じように受験される方は一緒に頑張ろう!