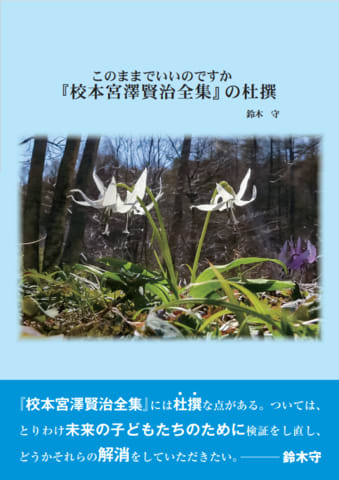
まずは、松田甚次郎の日記を見せてもらいに新庄へと思い付いたのだが、問題はその日記を実際に見ることが出来るか否かだ。学者でも研究者でもない私が松田甚次郎の日記を閲覧出来るはずはないよなと思いつつもやはり見てみたいので、厚かましくも駄目元で、『新庄ふるさと歴史センター』<*1>に問い合わせてみる。
「宜しければ松田甚次郎の大正15年と昭和2年の日記を見せていただけないでしょうか」
と。するとなんと受話器から
「宜しいですよ。それではこちらにお越しになる前にその日をお知らせ下さい。準備しておきますので」
という返事が聞こえてきた。嬉しさのあまり私はあやうく「やったっ!」と叫ぶところだった。
ということですぐさま訪ねたのが2度目の新庄訪問で、それは平成23年2月26日のことであった。新庄に近づくにつれて車窓からの眺めに驚きが増していった、あまりの積雪の多さに。岩手の積雪も少なくはないが、新庄の雪の多さは桁違いだった。新庄駅に下り立ってみると3月間近だというのに積雪が私の背丈よりも高かったからだ。この時期でかくの如くであるなら、真冬とか昭和初頭の頃ならばここの積雪の多さは推して知るべしだ。それだけでも松田甚次郎の実践は凄かったに違いないと直感した。松田甚次郎は農閑期の冬、農民を啓蒙する講演のために猛吹雪の中を幾度も駆けずり回ったと『土に叫ぶ』でたしか語っていたはずだからである。雪の回廊の中、そんなことを思い出しながら『新庄ふるさと歴史センター』に向かった。
そこへ着いたのはまだ昼時だった。恐縮しながら、
「松田甚次郎の日記を見せてもらいたくてやって参りました者です」
と受付の方に告げると、なんとわざわざセンター長が自宅から駆けつけて来て、大正15年と昭和2年の松田甚次郎の日記を見せて下さった。そこで、まずは大正15年の松田甚次郎の日記を手に取り、いの一番に開いて見た頁はもちろん大正15年12月25日の頁である。
幸いにも見ることが出来た松田甚次郎の二冊の日記(大正15年のものと昭和2年のもの)。それらは今まで私が抱えていた2つの懸案事項を一気に解決してくれた。
まず、これが大正15年のものであり、
【『松田甚次郞の日記』(大正15年)】

〈『新庄ふるさと歴史センター』所蔵〉
その中の、大正15年12月25日の日記には次のようなことなどが書かれていた。
…
9.50 for 日詰 下車 役場行
赤石村長ト面会訪問 被害状況
及策枝国庫、縣等ヲ終ッテ
国道ヲ沿ヒテ南日詰行 小供ニ煎餅ノ
分配、二戸訪問慰聞 12.17
for moriork ? ヒテ宿ヘ
後中央入浴 図書館行 施肥 no?t
at room play 7.5 sleep
赤石村行ノ訪問ニ戸?戸のソノ実談の
聞キ難キ想惨メナルモノデアリマシタ.
人情トシテ又一農民トシテ吾々ノ進ミ
タルモノナリ決シテ?ノタメナラザル?
明ナルベシ 12.17 の二乗ラントテ
余リニ走リタルノ結果足ノ環節がイタクテ
困ツタモノデシタ
快晴 赤石村行 大行天皇崩御
<『大正15年 松田甚次郎日記』より>9.50 for 日詰 下車 役場行
赤石村長ト面会訪問 被害状況
及策枝国庫、縣等ヲ終ッテ
国道ヲ沿ヒテ南日詰行 小供ニ煎餅ノ
分配、二戸訪問慰聞 12.17
for moriork ? ヒテ宿ヘ
後中央入浴 図書館行 施肥 no?t
at room play 7.5 sleep
赤石村行ノ訪問ニ戸?戸のソノ実談の
聞キ難キ想惨メナルモノデアリマシタ.
人情トシテ又一農民トシテ吾々ノ進ミ
タルモノナリ決シテ?ノタメナラザル?
明ナルベシ 12.17 の二乗ラントテ
余リニ走リタルノ結果足ノ環節がイタクテ
困ツタモノデシタ
快晴 赤石村行 大行天皇崩御
したがってこの日記に従うならば、松田甚次郎はこの日(12月25日)は花巻にではなくて日詰に行き、大旱魃によって飢饉一歩手前のような惨状にあった赤石村を慰問していたことになる。南部せんべいを一杯買ひ込んで国道を南下しながらそれを子供等に配って歩いたのだろう。そして、盛岡に帰る際に12:17分の汽車に間に合うようにと走りに走ったので足が痛かったというようなことも記している。となれば、慰問後は直接盛岡に帰ったことになり、赤石村慰問後の午後に花巻へ足を延ばしていた訳ではない。因みにこの日に購入した切符は日詰までのものであって、花巻までのものではなかったことも確認出来た。その日記帳には金銭出納も事細かに書かれていたからである。
というわけで、一般には他人の著書よりは本人がしたためた日記の中味の方が遥かに信憑性が高いだろうから、松田甚次郎本人のこの日の日記から、
松田甚次郎の赤石村慰問は一般に3月8日の午前と思われているようだが慰問したのは大正15年12月25日であるし、この12月25日に甚次郎は下根子桜に賢治を訪ねてはいない。
と結論していいであろう。つまり、(ア)松田甚次郎は大正15年12月25日に下根子桜を訪れていない。佐藤隆房著『宮澤賢治』には同日そこを訪れたと書いてあるが、それはフィクションである。
(イ)松田甚次郎は大正15年12月25日に赤石村を訪れて慰問しているが、自身の著書『土に叫ぶ』では昭和2年3月8日に赤石村を訪れたかのように受け止められるような書き方をしている。しかしそれはこの日のことの記憶違いであろう。
ということになろう。(イ)松田甚次郎は大正15年12月25日に赤石村を訪れて慰問しているが、自身の著書『土に叫ぶ』では昭和2年3月8日に赤石村を訪れたかのように受け止められるような書き方をしている。しかしそれはこの日のことの記憶違いであろう。
やった!これで今までのもやもやの一つが晴れた、と私は心の内で抃舞した。新庄は遠かったけれど真実には近づけた。心から『新庄ふるさと歴史センター』とセンター長に感謝した。
それにしても佐藤隆房は「八二 師とその弟子」の中で、大正15年12月25日に松田甚次郎は下根子を訪れたと、それも恰も見ているかの如くその様を生き生きと「書けた」のはなぜなのだろうか。明らかな虚偽がそこにはあるが、さりとて全く無関係な日かというとそうでもなく、大正15年12月25日は旱魃で困窮しているであろうことに心を痛めて松田甚次郎が赤石村を慰問した日ではある。しかし『土に叫ぶ』など一連の松田甚次郎の著書を読んでもそれらからは慰問した日が「大正15年12月25日」であるということを知る由はないはず。なのに、わざわざこの日「大正15年12月25日」を松田甚次郎が初めて下根子桜に賢治を訪問した日として佐藤隆房は「特定」できたののだろうか。
また松田甚次郎自身も、どうして『土に叫ぶ』で、
或る日私は友人と二人で、この村の子供達をなぐさめようと、南部せんべいを一杯買ひ込んで、この村を見舞つた。道々会ふ子供に与へていつた。その日の午後、御礼と御暇乞ひに恩師宮澤賢治先生をお宅に訪問した。
と、自身の日記とは矛盾するような書き方をしたのであろうか。もしかすると松田甚次郎の場合は当日12月25日は大正天皇が亡くなった日だからそのことに遠慮をして書き換えたのだろうか。いずれこれらのことに鑑みて言えることは、活字をそのまま事実であると鵜呑みにしてはいけない、検証せねばならぬということなのだろう。私はつい、出版されているものを読むとそれが真実であると受け止めがちな傾向がある。しかし以前述べた宮澤賢治研究家E氏の〝千葉恭は盛町出身〟といい、今度の佐藤隆房の〝大正15年12月25日〟の件といい、この松田甚次郎の〝昭和2年3月8日〟の件といい、活字になってはいたがいずれも真実そのものではなかったと言える。真実を掴むためにはやはり検証が必要だし、一次情報に立ち返ることが如何に大切かということをいまさらながらに思い知らされる。
とはいえ、やっとこれで一つの懸案事項は解決出来てそれまでの大きな胸のつかえがおりた。ただし松田甚次郎のこれらの日記を元にして確認しなければならないことがもう一つある。それがその時新庄を訪ねた最大の目的であったがゆえに。
<*1:投稿者註> 今までに『新庄ふるさと歴史センター』を訪れたのは下掲の4回があり、お陰様で貴重な資料等を知った。
それから、
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 「〝このままでいいのですか『校本全集』の杜撰〟の目次」へ移る。
「〝このままでいいのですか『校本全集』の杜撰〟の目次」へ移る。***********************************************************************************************************
《新刊案内》この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵教授が目の前で、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだが、そのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
と嘆いたことである。そして、私は定年後ここまでの16年間ほどそのことに関して追究してきた結果、それに対する私なりの答が出た。延いては、
小学校の国語教科書で、嘘かも知れない賢治終焉前日の面談をあたかも事実であるかの如くに教えている現実が今でもあるが、純真な子どもたちを騙している虞れのあるこのようなことをこのまま続けていていいのですか。もう止めていただきたい。
という課題があることを知ったので、 『校本宮澤賢治全集』には幾つかの杜撰な点があるから、とりわけ未来の子どもたちのために検証をし直し、どうかそれらの解消をしていただきたい。
と世に訴えたいという想いがふつふつと沸き起こってきたことが、今回の拙著出版の最大の理由である。しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感した。
まず、周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
きわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながらも道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。
と述べていることを私は思い出した。同時に、石井洋二郎氏が、 あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という、研究における方法論を教えてくれていることもである。すると、この基本を心掛けて取り組めばなんとかなるだろうという根拠のない自信が生まれ、歩き出すことにした。
そして歩いていると、ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているということを知った。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
そうして粘り強く歩き続けていたならば、私にも自分なりの賢治研究が出来た。しかも、それらは従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと嗤われそうなものが多かったのだが、そのような私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、私はその研究結果に対して自信を増している。ちなみに、私が検証出来た仮説に対して、現時点で反例を突きつけて下さった方はまだ誰一人いない。
そこで、私が今までに辿り着けた事柄を述べたのが、この拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます