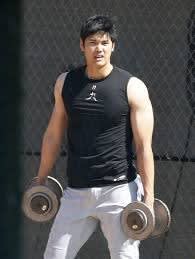「しまった」─ポケットを探っても、バッグの中を改めてもない。
携帯電話を忘れて出てきてしまった。
友人と急ぎ連絡を取らなくてはならないのだが……。
最近は公衆電話を見かけることもめったにない。
仮に見つけても、電話番号を覚えていない。
それは携帯電話の電話帳の中にあり、それを頼りにしているから記憶してはいない。
とにかく公衆電話を探そう。電話帳も備え付けてあるはずだ。
すぐ近くに総合病院がある。あそこなら公衆電話があるはずだ。
やれやれ、そうやってなんとか友人と連絡を取ることが出来たのである。

今は一人一台と言われる携帯電話の時代。
知人、友人、家族からの電話は、ほぼこれである。
あるいはLINEでパッパッと用件を伝え合う。
我が家においては、固定電話はFAXが唯一の出番だが、
それもほとんどが、パソコン、スマホのメールに取って代わられており、
おそらく多くの家庭が似たような状況ではないか。
そうとあって、家庭における固定電話不要論が多くなっているらしい。
確かに携帯電話は日々の生活の中で、
いまや必需品と言ってもよいほどの役割を果たしている。
だが、何事においても便利さには必ず代償が伴う。
さる経営者が社内で若い社員と接していて、最近こんなことを強く感じるという。
「今の若い人たちは、固定電話を使ったことがほとんどないはず。
この固定電話での相手は、たいてい見知らぬ人だ。
それだと、自然と敬語を交えて会話することになり、
意識しないまま社会における言葉遣い、マナーを学ぶことになる。
でも、今は携帯電話の時代。
相手は、主に友人、知人、家族といった、いわば気安い人たちだろう。
敬語を使う必要もなく、対等の相手として馴れ馴れしく話す。
つまり、ため口になってしまう。
そんな彼らが就職し、上司、あるいは取引先と
ため口でやり取りするとしたらどうだろう、受け入れてもらえるはずがない。
そのせいか、ビジネスの場におけるマナーとコミュニケーションについての
彼らの悩みは、相当に大きいようだ」
パソコンでこの一文を書いている。
手書きすることはほとんどなくなった。
ちょっと記憶があやふやな漢字もパソコンが正確に変換してくれるから、
辞書で調べることもなくなった。
以前は間違いなく書けていた漢字が、
正確に書けなくなってしまったのも
やはり便利さの代償であろう。
何ともはや──。