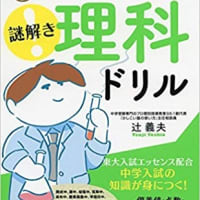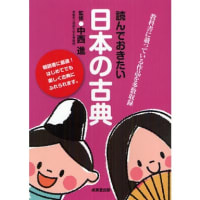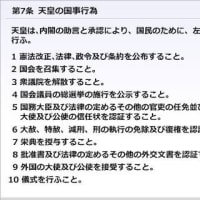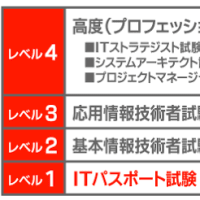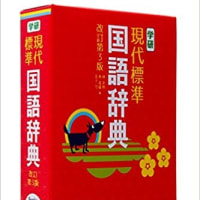新学期が始まりました。小学高学年や中学生なら、コミュニケーションがうまくなる方法を身につけましょう。
「…宿題は…」「宿題は?」「…」
相手に言ってもらえるまで、だまったままの子がいます。言いだしにくいのだろうと、察してあげることもできます。でも大人になるまでに、どう伝えればいいのか練習をさせる必要があります。
【教育ニュース】新卒採用、県内企業の半数が「3年間ゼロ」
>また、新規学卒者を採用する際に重視する能力については、「中学・高校卒」「短大・専門学校卒」「大学(院)卒」のいずれの場合も(1)社会常識、マナー、コミュニケーション能力(2)勤労意欲や責任感-の順だった。
企業にも余力がなくなり、こういった訓練は社会に出る前に済ませておくことを求めるようになりました。また、集団で行動する学校では、個々人のコミュニケーション能力は磨きにくいのです。
自分が言いたいことを、ことばで相手に伝えること。コミュニケーションとは、おしゃべりがうまいということではありません。おしゃべりが苦手でも、コミュニケーションは訓練で必ずうまくなります。
コミュニケーションがうまくなるコツ。まず声を発(はっ)すること。次に、目的と相手をはっきりさせることです。
コミュニケーションがうまくなる(1)|目的や相手をはっきりさせる
2011年度より小学校で実施される新学習指導要領。国語科では「新聞を使用した学習」が明記されています。NIE(教育に新聞を)という活動がそれです。
NIEは、日本新聞協会が中心となった、新聞の販売促進活動です。新聞社が用意したNIEのチラシが、学校でも配布されると思います。
NIE(Newspaper in Education・パソコンむけ)
手軽に知識を求める場合、テレビの情報番組が向きます、池上彰さんの番組を見てみましょう。
テレビは映像中心でわかりやすいのですが、受け身になるのが欠点です。情報をもとに考え、だれかに伝える訓練をするには、文字から読みとる新聞・雑誌・書籍などが効果があります。
(資料)国際学習到達度調査(PISA)2009年度の結果公表
>今回の調査では、新聞をよく読む生徒は読解力も高い傾向がはっきり表れている。学力向上の観点から新聞を見直し、上手に授業などに取り入れていく方法なども考えてみてはどうか。
新聞を活用した、目的と相手を意識して話すトレーニングをご紹介します。お父さんも参加しやすい、コミュニケーションになるでしょう。
家庭で新聞を活用するのは、文字情報に慣れてもらうことと、その"情報と自身との関わり"に気づいてもらうことが目的です。
学校の学習への効果や正確さより、「へぇー」「そっかー」という"関心"が大事です。全文でなくてもかまいません。おうちの方が関心のある記事を,読んであげることから始めるとよいでしょう。
期待するほどよい反応はない、と思います。しかし子どもたちは、外との社会への関心は持っています。初めて聞くことばかりで、いま反応はできないでいるのです。この経験は、かならず身になります。
読みとりや書き方の技術的な訓練は、学校や塾で出来ます。「おうちの方と読む」この経験は、子どもたちが社会と関わる窓になるでしょう。
続きます。(塾長)
「…宿題は…」「宿題は?」「…」
相手に言ってもらえるまで、だまったままの子がいます。言いだしにくいのだろうと、察してあげることもできます。でも大人になるまでに、どう伝えればいいのか練習をさせる必要があります。
【教育ニュース】新卒採用、県内企業の半数が「3年間ゼロ」
>また、新規学卒者を採用する際に重視する能力については、「中学・高校卒」「短大・専門学校卒」「大学(院)卒」のいずれの場合も(1)社会常識、マナー、コミュニケーション能力(2)勤労意欲や責任感-の順だった。
企業にも余力がなくなり、こういった訓練は社会に出る前に済ませておくことを求めるようになりました。また、集団で行動する学校では、個々人のコミュニケーション能力は磨きにくいのです。
自分が言いたいことを、ことばで相手に伝えること。コミュニケーションとは、おしゃべりがうまいということではありません。おしゃべりが苦手でも、コミュニケーションは訓練で必ずうまくなります。
コミュニケーションがうまくなるコツ。まず声を発(はっ)すること。次に、目的と相手をはっきりさせることです。
コミュニケーションがうまくなる(1)|目的や相手をはっきりさせる
2011年度より小学校で実施される新学習指導要領。国語科では「新聞を使用した学習」が明記されています。NIE(教育に新聞を)という活動がそれです。
NIEは、日本新聞協会が中心となった、新聞の販売促進活動です。新聞社が用意したNIEのチラシが、学校でも配布されると思います。
NIE(Newspaper in Education・パソコンむけ)
手軽に知識を求める場合、テレビの情報番組が向きます、池上彰さんの番組を見てみましょう。
テレビは映像中心でわかりやすいのですが、受け身になるのが欠点です。情報をもとに考え、だれかに伝える訓練をするには、文字から読みとる新聞・雑誌・書籍などが効果があります。
(資料)国際学習到達度調査(PISA)2009年度の結果公表
>今回の調査では、新聞をよく読む生徒は読解力も高い傾向がはっきり表れている。学力向上の観点から新聞を見直し、上手に授業などに取り入れていく方法なども考えてみてはどうか。
新聞を活用した、目的と相手を意識して話すトレーニングをご紹介します。お父さんも参加しやすい、コミュニケーションになるでしょう。
家庭で新聞を活用するのは、文字情報に慣れてもらうことと、その"情報と自身との関わり"に気づいてもらうことが目的です。
学校の学習への効果や正確さより、「へぇー」「そっかー」という"関心"が大事です。全文でなくてもかまいません。おうちの方が関心のある記事を,読んであげることから始めるとよいでしょう。
期待するほどよい反応はない、と思います。しかし子どもたちは、外との社会への関心は持っています。初めて聞くことばかりで、いま反応はできないでいるのです。この経験は、かならず身になります。
読みとりや書き方の技術的な訓練は、学校や塾で出来ます。「おうちの方と読む」この経験は、子どもたちが社会と関わる窓になるでしょう。
続きます。(塾長)