激動の時代を経て生まれたブッダの基本思想 (その1)
―ブッダのルーツの真実―
日本の多くの仏教建築、文化財が世界遺産となっており、神社などと並んで日本文化の一部となっている。国勢調査においても、仏教系統が9,600万人、総人口の約74%。
ところがブッダ(通称お釈迦様)の誕生地やシャキア王国の王子として育った城都カピラバスツなど、その歴史的、社会的な背景については、一般には余り知られていない。ブッダの誕生地は「北インド」と習った人が多く、未だに多くの教科書にはそのように記載。
また、ブッダは29歳までシッダールタ王子として‘カピラヴァスツ’で過ごしたが、‘カピラヴァスツ’城址とされる遺跡が、インド側とネパール側にある。これだけ社会科学が発達した今日の世界で、2つのカピラ城の謎が解決されていないのも不思議だ。そのことは、ブッダ誕生のルーツや基本思想が生まれた時代性が十分には解明されていないことを意味する。
ブッダ誕生の歴史的、社会的な背景やルーツを知ることは日本の文化や思想をよりよく知る上で必要。
このような観点や疑問から2011年に著書「お釈迦様のルーツの謎」(東京図書出版)を出版。また2015年、英文著書「The Mystery over Lord Buddha’s Roots」がニューデリーのNirala Publicationsから国際出版致しました。
特に英文では、このようにしてより明らかになった歴史的、文化的な背景を基礎として、ブッダの基本思想やその歴史的な意味合いに注目した。
Ⅰ.ブッダのルーツの真実と歴史的背景
1、ブッダの生誕地ルンビニ(ネパール)
現在、ブッダの誕生地はネパールのルンビニであることが国際的に認められているが、国際的に知られるようになったのはそう古いことではない。インド自体が世界に知られるようになったのは、英国の植民地となり英領インドとなった19世紀になってからだ。
そして1896年12月に、英領インド北西州の考古学調査官フュラー博士が、ネパール南部のルンビニに碑文が刻まれている石柱があるとの噂を聞き、ネパールの許可を得てネパール側と合同で行う形でこの「アショカ・ピラー」(アショカ王の石柱)を発掘し、碑文を解読した。これによりブッダの生誕地を巡る当時の論争は決着した。
アショカ王(在位 紀元前269年より232年頃)は、紀元前2世紀中頃にほぼインド全域を統一しマガダ国マウリア王朝の全盛期を築いたが、カリンガの闘いでの大虐殺への報いを恐れ、不戦と不殺生を誓い、ブッダ教に深く帰依したと言われている。アショカ王は、ブッダゆかりの地を訪問し、ルンビニ他に石柱を建てた。石柱には、パーリー語でアショカ王が即位20年を記念し、“ブッダがここに誕生したことを思い、・・・石柱を建立した”旨刻まれている。
この発見により、19世紀末のブッダの誕生地論争に終止符が打たれたが、インドでは生誕地は北インドと思われていることが多く、英国の著名な百科事典にも1990年代までブッダの生誕地は‘北インド’と記されていた。第一次世界大戦後、インドの独立運動が激化する中で、ネパールはインドからの侵攻を恐れ、これら遺跡を埋め戻すなどの保護策を取ったが、その後再発掘され、1997年にUNESCOの世界文化遺産に登録されるなど、ブッダの生誕地としてのルンビニが国際的に認められるようになった。
インドとネパールの間には、古くから深いジャングルに覆われた国境が残っているが、英国がインドを植民地とした頃から、ネパールは鎖国政策を取ったため、インド領内における欧州の研究家によるブッダ遺跡の発掘や研究はインド領内で行われ、計算や推測でブッダの生誕地などが決められたことから、ブッダの生誕地は‘北インド’という誤った認識が流布された、報道や百科事典にも載ったのであろう。日本の教科書の多くが、未だにブッダの生誕地を‘北インド’と教えている。教科書の通り答えれば試験は通るのであろうが、真実ではないようだ。
ブッダは、紀元前6世紀から5世紀にかけて現在のネパール南部ルンビニでシャキア王国(釈迦族の部族王国)の王子(シッダールタ)として誕生した。当時出産は母の実家で行うことが慣例であったので、母マヤデヴィ王妃はカピラバスツ城から故郷であるコーリア王国に向かう途中、王園であるルンビニ園で出産した。
ブッダの生誕地ルンビニは、カピラバスツ城の位置を特定する上で基点となるので重要。
2、城都カピラバスツ(シャキア部族王国―ブッダ青年期の居城)と周辺の遺跡群
ところがマヤデヴィ王妃が誕生したばかりの王子を連れて帰ったシャキア王国のカピラバスツ城跡が、生誕地ルンビニの西25キロほどのネパール側のテイラウラコット村とルンビニからインド国境を越えた南西87キロほどのピプラワ/ガンワリア村にある。
(1)テイラウラコット村のカピラバスツ城址
ルンビニから西に25キロほどのところにあるテイラウラコット村のカピラバスツ城址には、煉瓦造りの西門やそこから南北に伸びる城壁や内部の建築物の土台などが見られる。また城外に質素な博物館があり、出土品の白色土器や黒色土器などの陶器や貨幣と見られるトークンなどが展示されている。これらの出土品の多くは、紀元前5、6世紀のものであり、時代的にもブッダの時代と一致する。19世紀末から20世紀初頭に掛けて欧州の考古学者等が発掘をしたことが記録に残っているが、風化による損傷や持ち去られることを恐れ、ほとんどが埋め戻されている。
ブッダが属するシャキア(釈迦)族は、北西インドを中心に勢力を広げていたコーサラ族の流れを汲んでいるとされている。インド北西地域には、紀元前2000年頃からアーリア人がイラン高原を経由して長い年月を掛けて流入し、人口圧力の中で先住民との抗争を続けながら南東方向に浸透した。そして紀元前10世紀頃から先住民のトラヴィダ族等との融合が始まるが、アーリアンの支配と種族の保全の観点から、バラモン(司祭・聖職者階級)、クシャトリア(騎士・支配階級)、ヴァイシャ(農業・生産者階級)及びスードラ(従属者階級)というカースト制度が発達したと見られる。
紀元前6世紀頃から紀元前5世紀頃にかけては、インド北西部を中心として16大国が割拠し競い合っていたが、コーサラ国がブッダが修行に向かったマガダ国などと並んで最も有力な国の一つであった。コーサラ国は、現在のインドのウッタル・プラデッシュ州の北西部に位置する。そして時の国王が、故あって第一王妃の王子、王女に森に行き、国を作るよう指示した。王子、王女たちは「ヒマラヤ南麓」に辿り着き、そこで賢者カピラ・ゴータマに出会い、シャキア王国を築いたと言われている。
(2)テイラウラコット村のカピラバスツ城址の周辺に多くの遺跡。
またカピラバスツ城址のあるテイラウラコット村の半径7キロの周辺には、城壁の外側に父王スッドウダナの墳墓と言われている大小2つの仏塔(ツイン・ストウーパ)やブッダが悟りを開いた後帰郷し父王スッドウダナと再会した場所(クダン)、そしてシャキヤ族がコーサラ国のヴィルダカ王に殲滅されたサガルハワなど、素朴ではあるが歴史的には興味ある遺跡が数多くある。
更に、アショカ王はルンビニの他、現在のゴータマ・ブッダ以前に存在したとされる先代ブッダ(賢人、聖職者)の生誕地やゆかりの地を訪問し、ルンビニと同様のチュナール砂岩の石柱を建立し、遺跡が残っている。
ⅰ)寄り添って並ぶ2つの仏塔 (トウウイン・ストウーパ)
ⅱ)歴史を刻む2つのアショカ・ピラー。アショカ王が何度もブッダの郷里に足を運んだ証拠。
・ゴテイハワのアショカ・ピラー
・ニグリハワのアショカ・ピラー石柱上部には、次の趣旨の4行の碑文が刻まれている。
ピヤダシ王(アショカ王の別称)は「・・・即位[20年]を経て国王自ら訪れ
[そして]国王は[この石柱を建立することを]指示した」)
ⅲ)シッダールタ王子が、覚醒後ブッダとして父王と再会した場所クダンー4つの僧院遺跡やマウンドが。
(背景:ブッダは、ラージグリハ(現在のインドのビハール州)で富豪より寄進された竹林の僧院(漢字表記 竹林精舎)からカピラバスツまで約770キロ、2ヶ月ほどの道。)
ⅳ)サガルハワのストウーパ(仏塔)遺跡
法顕伝は、「大城の西北に数百千のストウーパがある。」等と記述。
父スッドーダナ王の逝去後、一族から王位を継承したマハナマ王になった頃、コーサラ国の王位を奪ったヴイルダカ王が、ブッダの再三の制止を振り切ってカピラバスツに攻め入り、攻防の末サガルハワで多数のシャキア族の人々を殺戮したとされている。多くのシャキアの人々は、この悲劇を前にしてこの地を去り、アフガニスタン地域を含め各地に移動したが、多くはブッダのインドの活動拠点であった南東方向に移動したと言われている。
このような歴史的な遺跡の存在は、ここにシャキア王国の城都カピラバスツがあったことを如実に物語っていると共に、カピラ城址周辺には古代ブッダ文化地帯とも言える知的文化があったこと示している。
3、もう一つのカピラバスツ遺跡は何かーインドのピプラワとガンワリア
ところがインド側のピプラワ村にもカピラバスツとされる遺跡がある。その南東1キロほどのところに「パレス」と表示されている遺跡がある。ネパール国境に接するウッタル・プラデッシュ州にあり、直線距離ではルンビニの西南西約16キロのところに位置するが、インドーネパール国境沿いは古くから存在するジャングルがあり、国境をまたぐ道は少ないので、地域住民のみが行き来できる道では87キロ近くある。
ピプラワのカピラバスツには、大きな仏塔遺跡があり、仏舎利が入った骨壷が発見されている。その周囲に煉瓦造りの建物の遺跡がある。四方の建物はほぼ同様の構造となっており、中央の広間を独居房が囲む内部の構造から、仏塔を中心とする僧院群のように見える。周囲に「城壁」もない。「パレス」と称されるガンワリアの遺跡も同様の構造の僧院群に見える。その中にひときわ重厚な僧院遺跡が一つある。それが「パレス」とは思えない。
ピプラワの遺跡も貴重なブッダ遺跡の一つではあるが、遺跡を比較するとネパール側の遺跡がカピラバスツ城跡と見られる。
4、歴史の証人―決め手となる法顕と玄奘の記録
シャキア王国が「ヒマラヤ南麓」に築かれたとの記録はあるが、その居城カピラバスツがあった所在地を含め、それ以上詳細な記録はない。しかし西暦5世紀と7世紀にこの地を訪れた者がおり、それぞれ記録を残している。中国の僧侶法顕がブッダの聖地を訪問し、その200年ほど後に玄奘が法顕の道を辿るように訪問している。
法顕は仏国記の「カピラバスツ城」の項で、城址の様子を述べた後、「城の東50里に王園がある。王園の名は論民(ルンビニのこと)と言う。」と記述している。中国の「里」を換算すると、「城の東25キロのところに王園がある」ことになるので、逆にルンビニを基点とすると25キロ西にカピラバスツ城があることになる。実際にブッダの生誕地ルンビニから西に25キロほどのところにテイラウラコット村があり、そこにカピラバスツ城址とされる遺跡がある。
玄奘も、法顕と同様のルートを辿りコーサラ国の首都シュラバステイや僧院などを経てカピラヴァスツを訪問し、「大唐西域記」においては「カピラヴァスツ国」の項で記述しているが、法顕とは異なる記述をしている。カピラヴァスツを「城」ではなく「国」と捉えている。その状況を、「周囲4千里ある。空城(人気のない町)は十数あり、荒廃は既に甚だしい。王城は崩れ落ちて、周囲の量もさだかでない。」などとしており、およそ法顕とは異なる記述をしている。嘗て欧州の研究家が、玄奘の足取りを詳しくトレースしたが、複雑なジグザグ状態の道程で、法顕の足取りとは異なることが分かっている。
法顕の同地訪問後200年以上も経っているので、遺跡は壊れ、ジャングルに覆われて、地域住民の意識からも薄れていたと思われるので、別のところに案内された可能性が強い。
ルンビニについても、法顕で記述されている石柱には触れておらず、周囲は草木に覆われ、虎や象などの野獣も出没するので、長居は無用と早々に退散していることが描かれている。玄奘の「天竺」訪問を伝奇風に描いた‘三蔵法師’(「西遊記」)では、孫悟空やサゴジョウなどが従者として法師を色々な外敵から守っているが、もとより「大唐西域記」にはそのような記述はない。
玄奘が描写した「カピラバスツ国」の状況は、現在のインド側のカピラバスツの風情と非常に似ている。ブッダに関連する貴重な遺跡ではあるが、城壁はなく、周囲に民家なども無く、正に「周囲の量もさだかでない。」そもそもカピラバスツは、シャキア王国の城であるので、国王になっていないブッダをまつる仏塔が中心に据えられることはない。ブッダは、29歳で城を出て、修行し、ブッダとなって何回も郷里を訪れているが、カピラバスツ城には宿泊せず、父王スッドウダナが用意したクダンの僧院に滞在した。ピプラワ村にあるカピラバスツは、コーサラ国のビルダカ王がシャキア王国を攻めた際に、シャキア族が難を逃れてた時に建てられた僧院群か、ブッダ没後に建てられた仏塔を中心とする僧院群であろう。因みに、仏舎利は当初8つの部族王国に分けられ、その後マガダ国のアショカ王がインド地域を統一した後に各所から仏舎利を集め、多くの場所に分散したと言われている。だから仏舎利が多くの場所で祭られていても不思議はない。
Ⅱ、激動の時代を経て、相対的安定期に生まれたブッダの基本思想
(その2に掲載)
1、 根底にバラモンの思想と先代ブッダの存在
―知的文化(古代ブッダ文化)の存在―
2、 王子の地位を捨て悟りの道を決断した基本思想―人類平等と人類共通の課題
3、 生きることに立脚した悟り
4、 不殺生、非暴力の思想
5、 ヨーロッパ、アジアを大陸横断的に見た思想の流れ
(Copy Rights Reserved.)












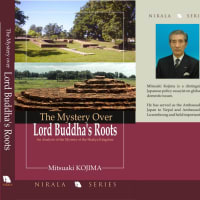






手塚治の漫画は面白いですね。
しかし「天竺」がどこかは何の記述もありません。
ブッダがどこで生まれどのような時代性の中でブッダ思想が生まれたかを拙著が明らかにしています。これは世界で初めての歴史書です。
そこから思想の意義がより分かります。
「お釈迦様のルーツの謎」
「The Mystery over Lord Buddha's Roots]