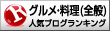(神学校での恩師の著作)
クリスチャントゥデイ社の許可を得まして、私が同ニュースサイトに連載しておりました「コヘレト書を読む」をこのブログでも連載させていただきます。クリスチャントゥデイ掲載分から少し変更させる場合もあります。
エルサレムの王、ダビデの子、コヘレトの言葉。(1:1、新共同訳)
今回からコヘレト書を読んでまいりたいと思います。私はまだ学びの途上にありますが、コヘレト書について考えているさまざまなことを世に問いたい思いもあり、コラムの執筆を引き受けさせていただきました。皆様のご意見をいろいろと伺えれば幸いです。
私自身は、口語訳聖書を使用していたときの「伝道の書」と題されていたこの書の、以下の4つの聖句を鮮明に記憶しています。
空の空、空の空、いっさいは空である。(1:2)
天(あま)が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。(3:1)
神のなされることは皆その時にかなって美しい。(3:11)
あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ。(12:1)
掛軸や御言葉カードなどに記されていた聖句であったように思います。そのような印象深い聖句がちりばめられている本書を、丁寧に読み進めてまいりたいと思います。
ヘブライ語聖書のコヘレト書の表題“QHLT”に、一番近い発音の日本語表記は「コヘレト」でしょうか。ユダヤ人が旧約聖書を朗読している録音を聞いてみても「コヘレト」と聞き取れます。コヘレトとはヘブライ語の動詞カーハールの分詞形で、「集める人」といった意味の語です。
日本の各翻訳聖書でのこの書のタイトルを見てみますと、「コヘレトの言葉」(新共同訳、聖書協会共同訳)、「伝道の書」(口語訳)、「伝道者の書」(新改訳、旧版・2017年版共に)、「コーヘレト書」(岩波書店版月本昭男訳)、「コヘレト」(フランシスコ会訳)、「コーヘレト」(関根正雄訳)となっています。
「伝道の書」あるいは「伝道者の書」という解釈は、この書の七十人訳(ギリシャ語訳)聖書のタイトルが「エクレシアステース」であり、その意味が「集会で語る人」ともなり得ることによるものでしょう。しかし「集める人」とは、「書かれているものを集める人」(12章9節参照)と解することもできます。筆者がこの書を読む限りでは、どうもそのような要素が強いように思えます。「古今東西の書物を集め、探求し尽くした人」の言葉集であるように思えるのです。
ですから「伝道(者)の書」と狭義に解釈してしまうよりは、「コヘレト」とヘブライ語の表題そのままに呼ぶ方がふさわしいと考えています。また、旧約聖書の預言書などが日本語では「○○書」と呼ばれていることにも鑑み、本コラムにおいてはこの書を「コヘレト書」と呼ばせていただきます。
さて、コヘレト書は1章1節において「エルサレムの王、ダビデの子、コヘレトの言葉」と書き出されています。ダビデ王の子といえば、通常はダビデ王の次の、紀元前10世紀のイスラエルの王、ソロモンを指しますから、この書は「ソロモン王の言葉集である」とも読めるでしょう。実際、伝統的にはそう解釈されてきたようです。しかし、今日においては、この書をソロモン王自身の言葉集であるとする説は、聖書学的にはほとんど受入れられていないようです。私もソロモン王のものではないと解していますが、その理由を私自身の視点で3点挙げておきます。
理由1:1章12節に「わたしコヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいた」とあり、コヘレトとされる人が、王としてエルサレムに滞在していたことが過去形(ヘブライ語聖書では完了形)で記されています。しかし、列王記上11章42節によれば、ソロモン王は終世エルサレムで王でした。ですから「エルサレムに滞在していたことが完了形」は考えにくいのです。つまり「コヘレトとされる人が、自分をソロモン王にしたてていることは虚構である」ということが、ここでバレてしまっているのです。というよりも「わざとバレさせている」と解した方が良いかもしれません。
理由2:8章9節に「今は、人間が人間を支配して苦しみをもたらすような時だ」とあります。このことは、コヘレトとされる人が生きた時代のイスラエルが、他国に支配されていたことをほのめかしています。ソロモン王の時代であればそれはあり得ません。
理由3:8章11節に「条例」という語があります(口語訳、フランシスコ会訳、聖書協会共同訳は「判決」、新改訳は旧版・2017版共に「宣告」)。この語は原文ではピトゥガームですが、これはペルシャ語からの借用語です。そうであれば、コヘレト書が書かれたのはペルシャ支配時代以後、つまり捕囚帰還後の第2神殿時代である、紀元前5世紀以後であるということが言えましょう。したがってこの書は、紀元前10世紀のソロモン王によるものではないことになります。
以上3点が、私自身が「コヘレト書はソロモン王自身の言葉集ではない」と考える理由です。コヘレト書の注解書・研究書の多くは「この書は、イスラエルがプトレマイオス王朝支配下にあった紀元前3世紀に書かれた、コヘレトとされるある賢者の言葉集である」としています。そこまで断言する解釈力は私にはありませんが、そのように見ることが妥当なのでしょう。ただ、ソロモン王の言葉集とされているということは、コヘレトが知恵者ソロモン王を受継いでいることを意味していることではあり、「ソロモン王はこのように言っています」としているような、コヘレト書を引用した説教文などを読んでも、違和感を感じるようなことは私にはありません。
著者や執筆年代の問題には、それほどこだわる必要はないのかもしれませんが、この書のところどころに見いだされる「時代の影」を読み取るためには、押さえておいた方が良いと思います。コヘレトは、彼が生きていた時代に、神様のなさってくださる御業を、どのように捉えていたのでしょうか。そして彼は、何を探求し、何を見いだして、何を大切にしていたのでしょうか。そんなことに着目しながら、コヘレト書を読み進めてまいりたいと思います。